�@�Ƃ����w�̐H���B�ዾ�����������������l�q�̐N�ƁA���Â��e��тт����N�������ɂ����B�ዾ���������N �\�\ �W���b�N�E
�u�p�����B�������ꂽ�������ɏo�Ă�����ǂ��Ȃ��Ă������ȁv
�@�p�����ƌĂꂽ���N�́A�m�[�gPC�����������邱�ƂȂ����t��Ԃ��B
�u��s���B�����������肵�Čv�Z�ł���̂����������ᖳ�����Ǝv����v
�@�p�����́A���܂苻���Ȃ����ɂ����������B�܂�ő��l���̂悤�Ȓ��q���B
�u����͂��́A�A�[�X�o�E���h����ɏ��������v�Z�ł���̂��H�@������肶��Ȃ��̂��v
�@�����A�Ƃ������͏����Ɏv�l�������y����ł���悤�ɂ��f��B
�u�g�ݍ��킹����B�w�������ƌ����Ă����M�����[�Ƃ���ȊO�ɂ͍������邩��B���̓���ւ��ɂ�����������Ԏ���Ă�B���̂T�Ԏ�O��͑_���ڂ��B���Ȃ�����Ȃ��́v
�@���E�̓R�[�q�[�����݂Ȃ��瓪�̒��ŃV�~�����[�V�������d�˂Ă݂�B���ӕ���ł͂��������A�v�l�̌��ʂ̓p�����̂���Ƃ��܂�ς��Ȃ������B�����Ȃ��ƌ����Έ����Ȃ��B
�u���E�A�����ʂ������A�l�����L���O�v�@�u�U�Q�ʂ��B���\�オ�����ȁv
�u�P�O�ԑ䂩�Q�O�ԑ�܂ł����Ă����Ə�������Ă��B�F�X�ƒ���Ƃ��v
�u���ꂱ��Team Earthbound�̘A�����P�l�Q�l�d���߂�̂������B���������āA�J�[�h�V���b�v���܂���ėV�Ԃ̂��O���Ă����B����ł��Ȃɂ��ƖZ�����A����́v
�u����������������̃`�[���ɓ��낤���Ċ���Ȃ�����邩������Ȃ��B���[�h�͂����������Ɏv���Ă�B�Ȃ�ł� "�������܂�̒m�I�Ńf�L��ዾ�j�q" �c�c�v
�u���Ȃ��W���[�N���B�����ɂ͊m���ɉ��Ȃ��B�Ƃ����āA��ֈĂ����Ƃ����̂��ȁv
�u�ʎq���W�܂�Ȃ��Ƙb�ɂȂ�Ȃ�����ˁB�����������[�h�������Ă��B�������̂��ƁA�ꂩ���ĂĂ��܂�������Ȃ����B��������Ό��܂łǂ��Ղ蓦�����Ȃ��v
�u�N����Ă�H�v�@�u��ɂ����ȁB���[�h�͈ꎖ�������G������v
�u���ق��Ă����v�@�u�l�Ԃ̉\���ɋ����������B�Ȃ�D�s�����v
�u�l�Ԍ�����������������v
�u�l�Ԃ������Ȃ�Ȃ��v
�u�u�قƂ�ǂ̂�����܂��܌����������������v�v
�@������킸�������A��U�Q�l�͉����ق�B���̊ԁA���E�͊{�Ɏ�����Ăčl�����݁A�P�O�b�c�c�Q�O�b�c�c�R�O�b�A�����ނ�Ɍ����J���B���_���o���悤���B
�u���̂ɂ��B�V�ːN�����҂̗��Ȃ炻����ʔ����v
�u�t�́H�v�@�u�}�f�ȏ����H�@���ɂ���͂�����Ƃȁc�c�v
�@�s�тȉ�b����i���A�����Ńp�������ʐM�ɋC�Â��B���[�����B
�u���[�h����B�f���G���u���b�N�ƃf���G���O���[���͍����� �w�w�u���Y�A�b�p�[�x �܂ŗ���悤�ɁB���������ȏ�����\���̎肩��~�o���ׂ��c�c�Ƃ��Ȃ�Ƃ��ӂ��������ƌ����Ă�v
�u�ӂ������b���B�����͂Ȃɂ�����Ă�H�@�n����ɗJ�����炵���H�v
�u���낤�ˁB�ǂ�����H�@�����H�v�@�u���傤���Ȃ��B�������B�܂����������Ƃ�����v
Turn 6
���C�G���[�i���j
�@Hand 2
�@Monster 3�i�s������m �u���C�J�[�t�^�s�h�������C�h�t�^�s�f�[�����E�\���W���[�t�j
�@Magic�Trap 2�i�s���r���O�f�b�h�̌Ăѐ��t�^�Z�b�g�j
�@Life 5700
���`�����h��
�@Hand 3
�@Monster 0
�@Magic�Trap 0
�@Life 4100
�u�u���[�g���c�c�u���[�g���c�c�u���[�A�u���[�A�u���[�g���A�T�[�E�u���[�g���v
�@�`�����h���ł���B���邢�́A���ă`�����h���ł������y���w�I�]���r�z�ł���B
�u�Ȃɂ��̐l�v�@�~�B�͌��Ɏ�Ĉ����ނ���B�������Ȃ��B���w�I�ɉ߂���B
�u�Ȃ�قǂˁv�@�C�G���[�i���j�͋C���������߂�悤�ɂق�̏��������������J���B���R�̔������B
�u�J�J�J�J�J�I�@�h���[�I�v�@���� �\�\�@�u��D����s�������t���B�������𐔂��Ă��炨�����v
�u �w�W�x �v�ň��̉\��������ɓ��ꂽ�ޏ��̎w��B����Ԃ��A������̓t���[�p�X�B
�u���x���S�I�@�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�a����ꏢ���B�_�[�N�\�[�h�a���w�肵�ās�����X�^�[�E�X���b�g�t���B��n�́s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�`�����O�A�P�������B�������J�[�h���_�[�N�\�[�h�Ɠ������x��4�Ȃ�A���̂܂܁c�c�J�[�J�J�J�I�@���x���S�A�s�_�[�N�E�G���t�t����ꏢ���v
�@�s�������t�Ɂs�����X�^�[�E�X���b�g�t�B�ꌩ����Ɖ^�C���ɂ��f�錈���B�������A�u���[�g���̖T��ɗ����S�̏��A�S�[�h���E�X�N�����u���G�b�O�͊m�M�������Ă��̎��Ԃ����B
�u���Ƀ`�����h���͕��w�I�m�M�ɏ[�������Ă���B���̗���͕K�R�v
�u�Ȃ�قǂȂ�قǁB���̓����̗ǂ��B�����������Ƃˁv�@�h��Ȕ������j�A�e�C���ł���B
�u����ɂ�낤�́A���̂܂܂���ƂĂ����̖��ɏ��ĂȂ��ƒm���āA�A�ł�H������̂��������ƂɕK�v�ȏ�ɐ����悭�|�ꍞ�B�ӎU�L���Ǝv���Ă���ȁB����Łc�c�v
�u�ǂ���珟���������悤���ȃS�[�h���B����œz�������܂����v
�u���̒ʂ肾�Z�����X�B�`�����h���̓T�[�E�u���[�g���̕��w�I�����ɂ���ĕ��������B����ƍĐ��̃_�C�i�~�Y���ɂ��`�����h���̌����͖�������B�I舂ȍU���͋t���ʂƂ������Ƃ��v
�@�Z�����X�ƃS�[�h���������ւ����A���[�h�ƃe�C������ʂ��c������B
�u�Ȃ�قǁB�y���w�I�����h���z���v�@�u���䂱�ƁB��������ɂ���Ƃ��͋C�����ȁv
�u�Q�O�O�O���ւ�s�_�[�N�E�G���t�t�̍U���͂Ȃ�A���܂��̃����X�^�[���ꌂ�B�o�g�����I�v
�@�s�_�[�N�E�G���t�t�̍U�����C�G���[�i���j�ɔ���A���A�ޏ��͍Q�Ă邱�ƂȂ���ǂ菄�点���B�g���b�v�J�[�h�s�a�r�̎g�ҁt�B���̃^�[���̍U�����V���b�g�A�E�g����B
�u������I�@�U�����~�߂��I�v�@�͂��Ⴎ�~�B�B�ɂ���`�����h���B
�u�ꂵ���ꂾ�ȁB�U������x����~�߂����x�̂��ƁB���̕��w�͈���ɒ��y�������Ȃ��B���C���t�F�C�Y�Q�A�}�W�b�N�E�g���b�v���Q�������ă^�[���G���h�B�����j�Ă݂�B�J�[�J�J�J�J�I�v
�u�܂��I�@��������x�͂Q���B�Q�̂̃����X�^�[�ɂQ���̃Z�b�g�v
�u���w�I�ɋ����h�����ꂽ�ȏ�A�{�̕z�w�����R�Ƃ������Ƃ��v
�u������C�����˂��B�}�P���L�K�V�l�G�B�}�P���c�c�L�K�c�c�V�l�G�v
�u�ӂ���v�@�e�C���́A�����[�����ɃC�G���[�i���j�̔w�߂�B
�i������ݔq�����ȁB���́y���w�I�]���r�z�A�ǂ��J���H�j
Turn 7
���C�G���[�i���j
�@Hand 2
�@Monster 3�i�s������m �u���C�J�[�t�^�s�h�������C�h�t�^�s�f�[�����E�\���W���[�t�j
�@Magic�Trap 1�i�s���r���O�f�b�h�̌Ăѐ��t�j
�@Life 5700
���`�����h��
�@Hand 0
�@Monster 2�i�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�́^�s�_�[�N�E�G���t�t�j
�@Magic�Trap 2�i�Z�b�g�^�Z�b�g�j
�@Life 3100
�@�~�B�͗����g�B�F��悤�Ȏp�������A���̎��A���̒��͌����ʼnQ�����Ă���B
�i�Q���̃Z�b�g�B���P���́s�ł̉��ʁt�ʼn�������s�Q�b�g���C�h�I�t�B�������݂��̂ƈꏏ���B�s������m �u���C�J�[�t�̌��ʂɃ`�F�[���A���������킵�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�������ł���B�I舂Ɍ��ʂ͎g���Ȃ��B�Q���̓��A�s�Q�b�g���C�h�I�t����Ȃ�����ł�������Ƃ͌���Ȃ����j
�@�~�B�͔Ֆʂ�����ł��邱�Ƃ�c�������B�t�B�[���h��ł͋����h�����ꂽ�`�����h�����j�������ނ������悤�ȏ����ׂĂ���B���w�I�_�������̂����Ă���̂��B
�u���L�K�~�}�b�^�i�B�\�E�_�g���B���m
�u����B����������C�ɂȂ��Ă����Nj������Ȃ�Ȃ��́H�v
�u�i�j�H�@���V�C�_�g�H�@�R�m���w�I�[�������c�J�}�G�e�v
�u�ڂƎ��̗ǂ��ɂ͎��M�����邩��B���̐U�镑������͖{���������������Ȃ��B�v���C�h�𑼐l�Ɉς˂Ă邠�͌��������ĂȂ��B�����̂ĂāA�������܂��Ă�v
�u�n�b�^�����C�C�g�R���_�i�B�R�m���n����G�n��O���b�N�^�E�����w���b�e���c���j�I���g�C�j�V�e�u���[�g�����w�m�z�����S�E�땺�B�����҃m�����j���R�\�[�`���`�e �\�\�v
�u�ӎv���̂Ă��]���r���v���C�h�����ȁv
�i�Ȃ� �\�\ �j�@�`�����h���A���˓I�ɂ��̂̂��B
�u�]���r�ɂȂ�̂͏���B�ł��ˁB�����݂��A�a���˂��錢���v���C�h���`���t������Ȃ�āv
�u�J�[�J�J�J�J�I�@�Y�������I�@�R�m����G�n��O���b�N�^�E���ŋ��m���j�I���g �\�\�v
�u����
�u�i���_�g�c�c�v�@�`�����h���́A����A���̏�̑S���������^���B
�u�n�������E�i�I�@���\�m�f�b�L�n�����m���B�\���K���E�ŋ��_�g�c�c�v
�u�蕨���낤�������i���낤���A�Ȃ�ł����Ă����E�ŋ��͐��E�ŋ��B��������ˁB���ꂪ�킽���̃v���C�h���B�C�ɂ���Ȃ��Ȃ�ł��ӂ��Ă݂�����v
�u���E�ŋ��I�H�@���惋�_�P�i���N�f���f�L���I�@�\���i���b�|�C�v���C�h�K�A���J�I�v
�u�������ˁB�}�����炦�̈����ۂ��v���C�h�B����ł��A�^�_���͍����B�Ȃ��v���C�h���͂���B�킽���̌����݈Ⴂ�Ȃ�A���̃v���C�h���{���Ȃ�A�ȒP�ɒ��˕Ԃ��锤���ˁv
�@�`�����h���͍X�ɂ����������ɉ�����B���ӎ��̍s���B���ӎ��̓��ɁA�`�����h���͋����Ă����B
�u�J�[�J�J�J�I�@���l�ԃV�e�����B�s������m �u���C�J�[�t�m���ʃ��g�b�e�~���B��ґ���_�B�s�Q�b�g���C�h�I�t�������e���o���m���`�A���^���i�P���o�I�}�G�m���`�B�T�A�A���e�e�~���v
�u���̌����͂����������B�h���[�B�s�h�������C�h�t������\���ɕύX�B�o�g���t�F�C�Y�A�s�f�[�����E�\���W���[�t�Łs�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t��ATTACK�I�v
�u�s�Q�b�g���C�h�I�t�B�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�ɕ�n�́s�R���t���v
�C�G���[�F�S�X�O�OLP
�`�����h���F�R�P�O�OLP
�u�c�O�_�b�^�i�B�U���͂Q�V�O�O�A���x�R�\��I�T�Z�e�����b�^�[�v
�@"�Ⴄ" �s�f�[�����E�\���W���[�t���ʍӂ����ɂ�������炸�A�~�B�͔ޏ��̏������m�M����B
�i�����ւ�Ȃ�Ăǂ������Ă���B���̐l�̃I�[���́c�c������l�̃I�[������Ȃ��j
�u�o�g���t�F�C�Y�I���B�s������m �u���C�J�[�t�̌��ʂ������B��Ɏc�����Z�b�g��j��v
�@�C�G���[�i���j�́@�u��͂�v�@�ƌ������\��Ŕj�ꂽ�J�[�h�����͂���B�~�B�͖ڂ��ۂ������B
�i�����A�s�Q�b�g���C�h�I�t�B�Q���̃Z�b�g�͗����Ƃ��s�Q�b�g���C�h�I�t�������́H�j
�u�_�[�N�\�[�h�ɂ����郆�j�I���͂P�������B�`�F�[���͂ł��Ȃ��ˁB���ꂶ�Ⴀ������v
�i�����P�H�j�@���̑̐�����Ȃɂ����Ƃ����̂��낤�B
�u�킽���̓u���C�J�[�ƃh�������C�h���тɁc�c�v
�@�C�G���[�i���j�͐g�̂��|�̂悤�Ɉ����i��A�����悭�Ղ𓊂���B
�@�~�B�͂������܋C���t�����B�����Ȃ郂���X�^�[���o��̂����B
�i�܂����킽���́c�c�킽���̃f�b�L�̃G�[�X�J�[�h���c�c�j
�@���Ղ̖����A���[�h�ƃe�C������e���V�������グ��B
�u�ŏ㋉�BAMP-24�^�Ƃ��Ȃ�c�c�v
�u���ɏo�����B�_�b���o���o���c�c�v
�u�s�a�e�|���k�̃A�u���I���X�t�������v
�u�͂��H�v�@�u�͂��H�v
�u�}�W�b�N�E�g���b�v��1���Z�b�g���ă^�[���G���h�B�����A�ǂ�����H�v
�i�ǂ����邾�ƁH�@�U���Ɍ��܂��Ă���B�U���ȊO�̕��w�͗L�蓾�Ȃ��j
Turn 7
���C�G���[�i���j
�@Hand 1
�@Monster 1�i�s�a�e�|���k�̃A�u���I���X�t�j
�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j
�@Life 5700
���`�����h��
�@Hand 0
�@Monster 3�i�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�^�s�_�[�N�E�G���t�t�j
�@Magic�Trap 1�i�s�R���t�j
�@Life 3100
�u�h���[�_�I�@�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�twith�s�R���t�f�A�u���I���X���U���X���D�I�@�\�m���C�r�S�g����C�e�������B�_�[�N�\�[�h�E���^�[���X���b�V���I�v
�@
�u���̏u�ԁs�a�e�|���k�̃A�u���I���X�t�̌��ʂ��B���̃J�[�h�ƃo�g�����������X�^�[�͔j�ꂸ�A�_���[�W�v�Z��Ɏ�����̎�D�ɖ߂�c�c���k�̃o�E���X�E�B���O�I�v
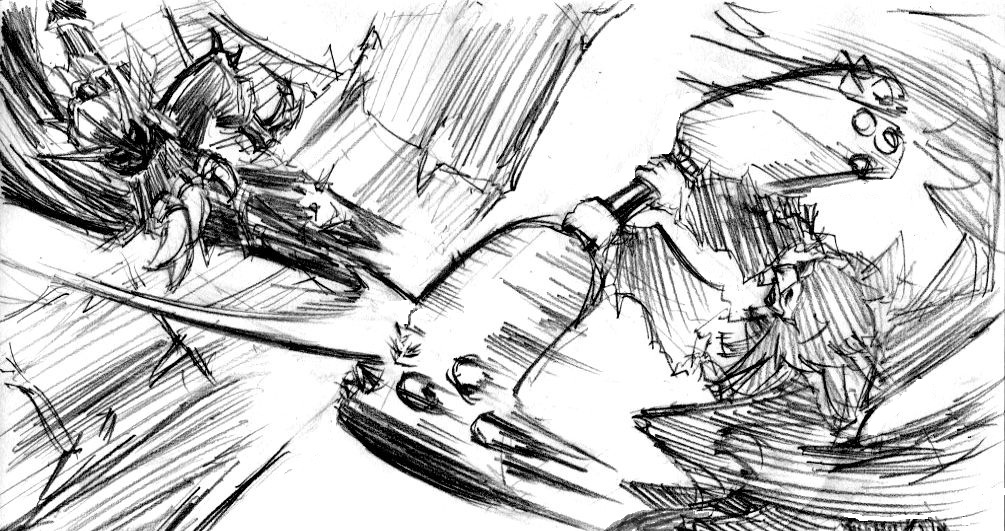
�@�A�u���I���X�͎莝���̞��_�Ń_�[�N�\�[�h��ガ�����A�P�ނ�����B
�u�n���i�B�\���i�n���i�B���m���w�K�\���i���m�j���������P�c�c�v
�@�����A�j��ꂽ�B�T������`�����h���B���[�h�́A��A�̍U�h���ȉ��̂悤�ɕ]����B
�u�Ȃ�قǁB��肢�ȁB�����̓�ґ���ȂǍŏ����瑶�݂��Ȃ������B�s�f�[�����E�\���W���[�t�͎̂ċ�B����̍U������A�U���͂ɗ��s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�E�\�[�h�t���̂Ă邩�A�����łȂ���Ή�������s�Q�b�g���C�h�I�t�Ō}���������Ȃ��B���R�`�����h���͌}������ȁB�_�[�N�\�[�h�ɋ����������̂����͂��Ă����āA�퓬�ɎQ�������Ȃ������s������m �u���C�J�[�t�̓���\�͂Ŏc��̂P����ׂ��B����Ń`�����h���̓n���h�[���ɃZ�b�g�[���B�����܂ł����V���āB���C���Q�ʼn��߂ăA�u���I���X���A�h�o���X�����B�J�[�h�̖������͌ܕ��ł��A�`�����h���͑S�Ă��o���s�����Ă���B��������A�݂��Ă�J�[�h���ǂ��ɂ���������B�ɓ˂�����ł����Ƃ���Ɂs�a�r�̎g�ҁt�Ƃ̃R���{�Ō��ށB�s�R���t�͕�n�ɑ�����B����ł����ɂ͑ł肪�Ȃ��v
�@�����ɉ�����郊�[�h�ɑ��A�e�C���̓e�C���Ŗ������������B
�u�Z�b�g�������Ƃ��s�Q�b�g���C�h�I�t���ƃC�G���[�i���j�͌������Ă��B�y
�u�����A�ŏ���������Ă܂����v�@�u�o���o���X�́v�@�u�Ȃ��ł��v�@�u�s�Ǖi����ˁA����v
�u�Ȃ�łł����I�@�A�u���I���X�ł���A�u���I���X�B�i�D�ǂ�����Ȃ��ł����I�v
�u�킩�����킩�����B�ɂ��Ă����̃`�����h���B���̂ő����ł��Ă�ȁv�@
�u���̖�Y�B���̉��̕��w�I�c�c���w�I�c�c�v�@�u���w���c�c�Ȃ��āH�v
�u�������̐����������Ă�B�Ȃ낤�B�Ȃɂ��ɍs���l�܂��Ă�݂����v
�@�~�B�̋^����A���[�h�͏����|���ƌ��Œ@���B�[�������A�炪���������Ă���B
�u����Ă���邺�B�I舂Ƀ_�E����D���Ε��w�I�ɋ����h������Ă��܂��B�����炠���͌}�������A�J����@���Ƃ����B����œz�͕��w�I�ɋ����h�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��v
�u�������B���̐l�͂����_���āB�y���w�I�����h���z��j�����v
�u�����B��͓K���Ɋԍ������l�߂āA��C�Ƀ��C�t���[���ɂ�������v
�u�ȁ[��v�@�ƌ��������b�ȕ\����ׂ�҂������B�e�C�����B
�i�������Ƃ͎v�����ǁA�ق�̏����Ȃ���������ȁB�Ȃ�j
�u��������B������킽���ɂ͏��ĂȂ��B���͓G����Ȃ��v
�u�u���[�g������c�c�u���[�g������c�c�Ȃ����B�Ȃ����ĂȂ��v
�u���̊Ŕ���͖{���̃v���C�h�������Ȃ��B���l�Ɏ����̌����̃P�c�������Ă��炤�A����Ȏp�����Ꮯ�������邱�ƂȂ�Ăł��Ȃ��B���������Ȃ猾���Ă݂ȁv
�u�Ȃɂ��v�@�u �w���̃��j�I�������E�ŋ��̃��j�I�����x ���āv�@�u�ȁc�c�v
�u���� �w��������x ����͕ېg�������Ă݂����B����ɂ��B���E�ŋ���AMP-24��|���̂ɁA����G�n��O���b�N�^�E���̃��j�I���̒��ł��ŋ��̃��j�I�����ᑫ��Ȃ��Ǝv��Ȃ��H�v
�u���C�Ă�ȁv�@�����ꂢ���̂́A�y�G�b�`���O�E�}���g���s�[�X�z���哱�����Z�����X�B
�u�u���[�g������̏����ŁA���x�ɕ��w�I���t�����`�����h�����h�炢�ł���v
�@�`�����h���͋C������Ă����B�ׂ��ꂻ���ɂȂ�Ȃ���A���낤���đ����q���ł����B
�u�����Ŏ������m�肵�Ă݂�B���������Ă݂�B�{���̊Ŕf���Ă݂Ȃ�v
�u���q�ɂ̂�₪���āB�������B�������x�Ŕ���������Ǝv���Ă��Ƃ��낾�v
�i�������j
�u���ꂪ�����c�c���������c�c��������c�c�������������c�c�������傳���c�c�v
�i�������j
�@�\�\ �Ԃ����Ⴏ���j�I���Ȃ�čD���ł��Ȃ�ł��Ȃ������B�Ȃ摕�����x�P�������r�߂Ă�̂��B�債�Đ��\�������Ȃ��ȂɁB����ł��g���肪���Ȃ��̂͗L�������B���͐l���݂̓w�͂𑱂��X�ň�Ԃ̃��j�I���g���ɂȂꂽ�B���ɂQ�l�������Ȃ���������ȁB���̋@�\�����h�����邩�炩�A�������炢�̎��͂́A�Ⴄ�f�b�L���g����Ɣ�ׂĂȂ�ƂȂ���ڒu����₷������(�悤�ȋC������)�B���̍����牴�̓��j�I���g���Ƃ����L�������ϋl�߂��B �w���̓��j�I�����킩���Ă�x �����A�s�[�����邽�߂̎��_�����������B������ۂ���悩�����B�ǂ������j�I���̂��ƂȂ�ĒN���킩��Ⴕ�Ȃ��B�Ȃ̂ɂ��̖�Y�B�����̃��j�I���́A�����́yVWXYZ�z�͈�����B�������j�I�������ł�̂ɂǂꂾ�����������Ǝv���ĂB�Ȃ��̏Ί�B���̏Ί�͉����{���B���j�I���Ȃf�ň����Ă�˂��I�@���ĂȂ��̂�������B����G�n��O���b�N�^�E���̊O�ɂ͂����Ȃ��B����ȉ��ɁA���̎��_�Ƀu���[�g������� �w���w��������x �ƌ����Ă��ꂽ�B���͂���ł悩�����B
�u�u���[�g������I�@���ɕ��w�������Ă���I�v
�@�`�����h���́A������ɔ��œ|�ꍞ�ݐ⋩����B
�u�u���[�g������I�@���w���A���ɕ��w���c�c�����I�v
�u����Ȃ�߁B����Ȃ����炳�܂Ȏ��������w���ƌ����邩�I�v
�@�`�����h���̕������𐨂��悭�������̂̓Z�����X�B�����牌�������o���ƃ��C�^�[�Œ��A�`�����h���ɉ�������B����`�����h���́A���w�I�Ă��]���r�Ɛ���ʂĂĂ��܂��B�������s�s�\�B�Z�����X�͌����Ղ��\���A�C�G���[�i���j���Ɍ�������B
�u�`�����h���̕��w��_�j�������B���������̒��x�ł����C�ɂȂ��Ă�����Ă͍���B�M�l���k�قȂǂ��̃Z�����X���A�_�d��R�₵�s�������̋����������w�������ď����Y�ɂ��Ă����v
�u�킩���B���̓`�����h�����������v
�@�Q�l�̊ԂɎ��ꂪ�ł���B�����Ō����Ō���鎥��B�~�B�͎����̗�����Y��ċ��������B������|�����Z�����X�Ƃ̓����B�Z�����X�͌������B�@�u�Α��̑O�ɖ��O���炢�͕����Ă��������v
�u�c�c�A���A�v
Duel Episode �Q
����������
�`�R�ĂƎ_�f�Ɠ�_���Y�f�`
Starting Disc Throwing Standby�\�\
Three�\�\
Two�\�\
One�\�\
Go�I Fight a Technological Card Duel�I
�@���ˁB�~�B������⏬�Ԃ��
�u�Ȃ�قǁv�@�Z�����X�́A�߂��Ă��������Ղ�͂ނƖ������Ɏ����N���B
�u�v�����ʂ�ǂ��Η͂�SDT�B�����B��U�̕������������Ƃ������̂��v
�u���ɓ����Ȃ����v�@���[�h���ڂ̑O�̌��i�����ς���B�@�u�O�̌�����������Ŏ��M�����邩��łĂ����B���Z�̂P��Q�͓��R���̓��Ɏ����Ă�B�����łȂ���Η]���̃A�z���v
�@�����A�A���A�͕ʂ̂��Ƃɒ��ڂ��Ă����B
�u�ǂ����ł݂����Ƃ���Ǝv������B���A���̗L���ȉ��̃`�[���ɂ��Ȃ������H�v
�u �w���x ���B����͍߂�����ꂽ�B���ł��Ȃ��u���[�g�����w�Ƃ̏o��łȁv
�u�ւ��B���̎q��g�̑��ň͂ޏ��āA�ǂ��̏@���̂ǂ��̐����ɂ̂��Ă�́A����v
�u�s���ȍ����͂�߂Ă��炨�����B�������Ƃ��Ă��s�����ɂ܂�Ȃ�����ȁB�@���ł͂Ȃ��B���w���B���̃Z�����X�����r�����y
�@���X���~�̐����J��L���A�Z�����X�̓A���A�̑f����T��B
�i�����́A���̏��́A���̕ӂ̃{���N�����Ƃ͈Ⴄ�j
�@�F�߂�Ƃ������ƁB�G�R�̏��̉��l��F�߂�B����͌����ėe�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B�����Z�����X�́A���鎟���ɂ����Ă͂���𐬂��������B�̂ɁA��萸���ȕ��͂��\�ƂȂ�B
�i�������A��͂͂����炪��B�f�b�L���蕨�ł͖{���̗͂��o���܂��j
�u����_�炩�ɁB�Ώ������獢�邩��ˁB�킽���̃^�[���c�c�h���[�I�v
�@�������h���[�ɂ���������Ă��܂��B�~�B�́A�O�̎����ȏ�ɂ��̎������Î������B��������������Ɏ����̃f�b�L����ėՂށB�����ɍ�������A�����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B�������肷����B����ŁA���҂��Ă��鎩�����m���ɂ��āB�@ �u�撣���Ă��������I�v�@�A���A�͐e�w�𗧂Ă�B
�u�������v
�@�ޏ��͋����قǓ�炩�ȔP�肩��A�͋��������₩�ȓ��ՂƋ��Ɍ������J�n����B
�u��D����s�f�[�����E�\���W���[�t��ʏ폢���B���x���K���K��������B�������͂��A����т���т����悤�ȍ��ʂ�����Ȃ�����ˁB�}�W�b�N�E�g���b�v���P���Z�b�g���ă^�[���G���h�v
�@��G�ɑ��Ă����C�ȑԓx������Ȃ��A���A�B��� �\�\
�u���C�ȃv���C���O�����������B���̒��x�Ő�����Ƃ͂͂Ȃ͂��������B�ɂ��݂Ȃ������X�^�[��W�J����B������ґ�Ȃ��Ƃ��B�������A���܂����ґ�ɂ͕��w������Ȃ��I�@�^���ґ�Ƃ́B�D�����������č��V���邱�Ƃ��B�Ⴄ�B�������炵�ĉ��y�ɓM��邱�Ƃ��B�Ⴄ�B�^���ґ�Ƃ͉����B���̃Z�����X������^���ґ�Ƃ͉����B���ڂ���I�@���ꂱ�����A���w�I�ɐ������^���ґI�v
�@�Z�����X�͉����烉�C�^�[�����o���Ɖ�t���A�E�̌��p�b�g�ɛƂ߂�B�A���A������X�����B
�u���̂�����́H�v�@�u���ꂱ�����ґB����ɏ�����̂͂Ȃ��v�@�u������A���̂�����́H�v
�u�l���Ă��݂�B�_�f�����l�ލő�̍��Y�B�_�f�����Ă̐l�ށB�Ȃ�A�_�f��ɂ��݂Ȃ��g�����R�Ă��������ɂ��ґ�B���Ă��鐬���͎D���ɉ�t������ɂ����Ƃ����B���z�͈����Ȃ��B�܂��Ɏ���d�B�������A���ꂪ�w�̂Ȃ������̌��E�B�_�f�͕��w�B�_�f���������w���I�v
�u�����A�]���̃A�z�Ȃ�Ȃ��́H�v�@�e�C���������悤�Ɍ������B
�u����v�@���[�h�����_����B�@�u�����Ƃ���͌�����Ȃ����c�c�v
�u�������I�v
�@�Z�����X�n���B�傫�������A�_�f���z���đ̓��R�Ă��J�n����B
�u�h���[�B�n���h����ܔM�̗[���A�s���H���J�j�b�N�E�G�b�W�t�������v
�@�s���H���J�j�b�N�E�G�b�W�t���A���A����̉��˂���Ƃ��납��Z�����X�̖ҍU���n�܂����B����f���������G�b�W�͗p�ς݂Ƃ���ɔj��A���̒�����s���O�̍� �Ɖt�������ďo��B�U���͂Q�Q�O�O�ɒB�����������̃A���f�b�g�B���l�ɖ��������͔R������̋ʂ��T���U�炷�B����A��n�ɑ���ꂽ�G�b�W�͕�������s���̐��� �C�t���[�g�t�̔R���ƂȂ��Ă����B�����������A�U���͂P�V�O�O�B����R���ڂ邱�ƂŁA�Q�O�O�O�̈�ɂ܂ŔR���オ��B
�i�����ˁj
�@��Âȕ��͂��A���̗L���ɂ����Ă̓^�C�����O�ł����Ȃ��B��[�U�߂ɉ��ƁA��[���t���Ƃ����Ƃ����ԂɔR���L����̂��������̎������B�R�����鉅�O��O�ɂ��āA�s�f�[�����E�\���W���[�t�͂��̂̐��b�ŔR���s�����B�C�t���[�g�̓S�����A���A�̕���P��B�@�u�M�����S�̊댯����m�����悤���ȁB�o�[�x�L���[���I�v�@�Z�����X�͎~�܂�Ȃ��B�@ �u�}�W�b�N�E�g���b�v���P���Z�b�g���ă^�[���G���h�v
�@�҂�Z�����X�B������~�B�B���炩�ɈႤ�B
�i����ς�B���̐l�͂������̐l���� �\�\ �j
Turn 3
���A���A
�@Hand 4
�@Monster 0
�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j
�@Life 5200
���Z�����X
�@Hand 2
�@Monster 2�i�s���O�̍� �Ɖt�^�s���̐��� �C�t���[�g�t�j
�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j
�@Life 8000
�u�h���[�v�@�u��������������I�@���܂��Ɖ��Ƃł͔R�Č������Ⴄ�̂��v
�u�R�₵�ĔR�₵�āB�n�����g���̑��i�L�����y�[���ł�����Ă�́H�@���`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�������l�ނ̖ŖS�����܂邩���v
�@���b�V��������������ɂ�����Ƃ������́B���B���ꂷ���� �\�\
�u���������ȁv�@�u�͂��H�v�@�u�悵�I�v�@�u�Z�����X��㩂ɂ��������I�v
�u�l�ޖŖS�͂��ꂱ�����w�̓ƒd��ł͂Ȃ����B�ЊQ�A�Q�[�A�u�a�A�����Đ푈�B���ĂȂ���@�ɍۂ��āA�s�q�Ɍ������܂��ꂽ�����͊����̗D�ꂽ���w�ݏo���Ă����B�Ȃ�����A�l�ޖŖS�Ƃ����l�ގj��ő�̗L���ɂ����ẮA�ǂꂾ���̌��삪���܂�邱�Ƃ��낤���B���Ƃ�����̉��̂��̍s�ׂ́A���w����������̂Ƃ��Ēn���ɂ��Ċm���ȍv���ƌ����邾�낤�B�b�܂�Ȃ��q���Ɉ��̕���𐿂����Ƃŕ��w�͐��܂�Ȃ��B�����݂̔R�Ă������Ă������w�͐��܂��B�������Ƃ��B�l�̍\���̒��Ő�����߂銄���ƁA�l�ޖŖS�̒��ŕ��w����߂銄���͂قړ����v
�@�_�f�̕��w���ŖS�̕��w���ĂԁB���w�A���ł���B
�@���܂����Z�����X�͉���������P�̃��C�^�[�����o���A���x�͍��̌��p�b�g�ɃZ�b�g�B�Q�{�̔R�Ă��s���B�@�u�ł��I�@�Z�����X�̕��w�A���v�@�u
�u�݂��������I�@���ꂪ���̕��w���I�v
�u�����������v�@�u�s�����ȁv�@�u�s������ł����H�@���[�h����v
�u�G���[�V�����E�^�C�v�͒��q�ɏ悹��ƕ|���B�^�C�v�̓`�����h���Ɠ����ł��A�����̓u���[�g���̏����𐿂����Ɩ����Ɏ�����R�₵�Ă���B���܂ł����ۂ���ēz���B���̕������̎d�|���͑����v
�u���̂܂��̋�C�������Ȃ肻������˂���B���C���t�F�C�Y�v
�@�A���A�́A�����X�^�[���P���Z�b�g���ăG���h�錾����ɗ��߂�B
�u�Â��ȁB���̒��x�Œ��ł���ƁB�M���R�������鉴�̃^�[���A�h���[�I�v
�@�Z�b�g�Ŏ����ł߂Ă����Ă͎~�܂�Ȃ��B�̋ʃg�[�N���ƁsUFO�^�[�g���t��W�J�B�������Ƃ���ɃZ�b�g��j��B�s�L���[�E�g�}�g�t�B�Ȃ�Ƃ��������C�t���[�g�A�^�[�g���A�^�[�g���o�R�́s�v���~�l���X�E�h���S���t�Ɨ��đ����ɏP��������B�s�L���[�E�g�}�g�t��������������s�j���[�h�����A�t�̌��ʂ��B�Ȃ�Ƃ��ƉA��ɂ�����̂́A�s�v���~�l���X�E�h���S���t�̉����A���A���P���B
�A���A�F�S�P�O�OLP
�Z�����X�F�W�O�O�OLP
Turn 5
���A���A
�@Hand 4
�@Monster 0
�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j
�@Life 4100
���Z�����X
�@Hand 2
�@Monster 3�i�s���̐��� �C�t���[�g�t�^�s�v���~�l���X�E�h���S���t�^�̋ʃg�[�N���j
�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j
�@Life 8000
�u�����Ƃ����ԂɃ��C�t�������ɂȂ���������v
�@�s�����Ɍ����~�B�B���̌����͐g�̂�������B���ۂɔR���邱�Ƃ͂Ȃ����̂́A�Ռ��͎��́B�M��тт��Ռ��g�A�Ƃ����ƕs�v�c�ȕ\���ɂȂ邪�A�̊��I�ɂ͂���������B
�u�����S�O�O�O���B�������ˁv�@�u�������ȁB�ނ���S�����ƕ]�����悤�v
�u�킽���̃^�[���A�h���[�B�s������m �u���C�J�[�t��ʏ폢���v
�@���ʔ����B�@�i�ʖځj�@�~�B���S�̒��ř�B�����悬��Z�����X�Ƃ̈��B�s������m �u���C�J�[�t�̌��ʂ��Z�����X�̃Z�b�g�J�[�h�ɋy�u�ԁA��F���ʂŗ��Ԃ��B
�u�Â��Â��A�Â�����B������͂��̂Ƃ���҂��Ă����B���߁I�v
�@�҂��Ă����̂́s�Η�p�|�u�g�v�t�B�U���͂ɗ��s�v���~�l���X�E�h���S���t����֒e�ɕς���D��B���C�t�͂����Ƃ����ԂɂQ�U�O�O�B�~�B�͎v�����B���̂܂܂ł́B
�u��l�����K�[�h���������������B�����܂ꂽ�������B�C�������H�v
�@�~�B�͂����Ƃ����B����͂킽���ׂ̈̓������B����ł�������܂��ł�������B
�@�A���A�͗��������������\�������Ȃ��B�u���C�J�[�ʼn̋ʃg�[�N�������B
�@�s���̐��� �C�t���[�g�t�Ɓs������m �u���C�J�[�t�B��Ɏc�����̂͂Q�̂̂݁B
�u��ɂ͏オ������Č��������ɁA�t�B�[���h�ł͒��ǂ���R�ł��B�債�����ƂȂ��ˁv
�u�ق��B�܂��]�T������悤���ȁB���̃^�[���A�h���[�B�������낤�B����Ńg�h��������Ă��v
�@��n�́s�v���~�l���X�E�h���S���t�����O�B�s�C���t�F���m�t����ꏢ���B���̂�R���ɂ��邱�ƂŁA�g�F��₦�ԂȂ��R�₵������B�s���g���E�L�����t�A�s�o�[�j���O�u���b�h�t�B�X�ɔR���Ă����B
���g���E�L�����i���ʃ����X�^�[�j
���Q/������/�b��/�U 600/�� 550
���̃J�[�h���t�B�[���h��ɕ\���\���ő��݂������A�t�B�[���h��̉����������X�^�[�̍U���͂͂T�O�O�|�C���g�A�b�v���A�����������X�^�[�̍U���͂͂S�O�O�|�C���g�_�E������B
�o�[�j���O�u���b�h�i�t�B�[���h���@�j
�t�B�[���h��ɕ\���\���ő��݂��鉊���������X�^�[�̍U���͂͂T�O�O�|�C���g�A�b�v���A����͂͂S�O�O�|�C���g�_�E������B
�u�~�Q���邩�B���Ȃ����낤�ȁB�Ȃ�R����I�v
�u���C�t�Q�O�O�O�A�������ȁv�@�u�I��肾�v
�u���Ȃ���������Č����ׂ������v
�@��ɂ͌��A�n�ɂ�㩁B���o�[�X �\�\
�u�s�a�r�̎g�ҁt���v
�u�������B������I�v
�u�������������Ƃ���Ȃ��B����ɁA���낻�둧���ꂵ���Ȃ��Ă�����Ȃ��́H�v
�u���c�c�܂����B���ꂪ���܂��̑_�����B�s�L���[�E�g�}�g�t���A�s�a�r�̎g�ҁt�����ׂ̈̕z�B���ԉ҂������Ă�����̎_����_���ƁB�Ȃ�قǁc�c�N�c�c�N�N�N�N�c�c�t�n�n�n�c�c�n�[�b�n�b�n�b�n�I�@���ꂾ�ȃA���A�I�@���̒��x�̎��ԉ҂��łǂ��ɂ��Ȃ�Ƃł��c�c�������낤�B���̂܂܂ł��\���߂���قǂ��܂���R�₵����邪�A�����āI�@��]�̕��w���Ȃ邩���[�ւ��悤�ł͂Ȃ����v
�@�Z�����X�̓{�^�����O���ď㒅���͂������B�ނ̋����ɂ́A�ǂ̕t���������ȃ}�X�N���Ԃ炳�����Ă���B�Z�����X�̓}�X�N��͂݁A�����Č����ɑ�������B�S�Ă͏�������Ă����B
�u�_�f�{���x���I�v�@�u�����A����Ȃ��̂܂ŁI�v�@�u�����ʖځI�v
�u�v���Ԃ肾�ȁB�Z�����X�����S�̂ɂȂ�̂́v
�u�Z�����X�̕��w�͍��A���n�̎����}�����v
�u�����邪�����B���ꂪ���S�Ȃ镶�w���v
Turn 7
���A���A
�@Hand 4
�@Monster 0
�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j
�@Life 2600
���Z�����X
�@Hand 0
�@Monster 4�i�s���̐��� �C�t���[�g�t�^�s�v���~�l���X�E�h���S���t�^�s�C���t�F���m�t�^�s���g���E�L�����t�j
�@Magic�Trap 1�i�s�o�[�j���O�u���b�h�t�j
�@Life 8000
�u�h���[�v
�@���B�ɂ�������炸�B �w���������x �Ƃ����̂��K��������Ȃ��B�R��������Ή��̗��������A�܂�őނ��Ȃ����̎p�ɁB���̏����� �\�\ ����Ӗ��� �\�\���z�������B
�u�P�����H�v
�u����A�ł͂Ȃ����v
�u�l�ނ͖ŖS����́H�v
�i�ցH�j �~�B�͎v�킸��傷��B�Z�����X�͊��������ɓ������B
�u���̒ʂ�B�M�l���`�����h����f�킷���߂ɂł������������E�ŋ��Ƃ������^���b�B�����ĔF�߂悤�B���̏�ɂ����āA���܂��͐��E�ŋ��Ƃ������ƂɂȂ�B���������܂��̌��t�͂��ꂪ���E�B���̌��t�͐l�ޖŖS���������Ă���B�����A�l�ޖŖS�̑O�ɂ͉��҂����́B�����r���͕̂��w�̗��B��O�͂������Đl�Ԃ̍Ĕ�����ڎw�����w�ɖڊo�߂邾�낤�B���܂������X�ڊo�߂邪�����v
�u����͂ǂ����ȁv
�u�ȂƁH�v
�u�����l�ނ��ŖS����Ȃ�A�������͔�����̓e�݂����Ɍ����̂��ƍl���Ă�Ǝv���B�l�ނ��ŖS����O�Ɍ����Ŏ��ʂׂ����ǂ����Ƃ��B�����䂤�́v
�u�~���������ȁv
�u����͂��܂����v
�u�ȂƁI�H�v
�u���������ȁB�����܂ꂽ�������ƁB�G�Ȃ悠�̌����́B�܂����ƌ����B�����҂Ƃ́A�Ȃ̓��������f���邩�猈���҂Ƃ����B����������������R�����Ƃ��A�Ȃ�łQ�Z���`����_��Ȃ������B�}���ł��}���ȊO�ł��Ȃ��A����Ȕ��[�ȂƂ�����R�荞�ގG�������̌����B�P�����Ƃ���B���͐܂����̂���Ȃ��܂���̂��B
�@�A���A�͉E�r��O�ɏo���ĕG��܂�O�X�p���ƂȂ��Č��h���B�E�r�ɕt���������Ղ����̂悤�ɈЈ��B�V�������r���A�낤���܂ł̌����Ƃ��ċ@�\����B
�u�����c�c�����l�ޖŖS�͖ڑO�B���܂��ɂȂɂ��ł���I�v
�u�l�ޖŖS�̑O�ɂ͐��E�ŋ��̌����҂����́B���͂����������B�����������Ԉ���Ă�B���E�ŋ��̌����҂���_���Y�f���z�����猈���ɂȂ��đ̒��̌��Ƃ���������łĂ���B�����҂͌������z���Đ����L�т�B�l�ނ͎��ł��Ă������҂͐����c��v
�i�ȂB�Ȃɂ������Ă��邩�܂�ł킩���B�܂����A���̉��𗽉킷�镶�w�������Ă���Ƃ����̂��B����Ȕ��͂Ȃ��B�u���[�g�����w�������A���̉���������̕��w���������j
�u�z���͂��n�����ȃA���A�B�l���Ă��݂邪�����B�_�f�������Ȃ�Ύ_�f�������Đ푈���N���邾�낤�B�����āI�@���@�����̉Q�̒��A�n�セ�̂��̂����̐��������������̂��v
�u�����n�オ�����Ă��܂��Ȃ�A�V���ɂł������Ă����Ō��������A�����҂́v
�u���ɗ������ȁI�@����͏@���B���w�ł͂Ȃ��B�����ēV���ȂǑ��݂��Ȃ��v
�u�Ȃ��Ȃ����B�V�������āA�����ɉ��Ԃ����ĂČ�������v�@�u�n���ȁv
�u�r�߂�Ȃƌ������͂��B�_�k�����͌L�������A������͋|�������A���������͎D�������B�_�k�������앨�����߂č�������悤�ɁB��������l�������߂ĕ��Q����悤�ɁB���������͌��������߂ĂȂ�ł����B�ŖS�̂P��Q�ł������鐶������Ȃ��v
�u�n���ȁB�n�����B�n���߁B�Ȃ�Ƃ����c�c�v
�u���̖��͐������v�@�e�C�����B�@�u�������n�����Ă�v
�@�����e�C���B�@�u�ꐶ�܂���ʂ��̂����B������ȁv
�@�X�Ƀe�C���B�@�u�܂���ʂ����n���͂����n������Ȃ��v
�@�̂Ƀe�C���B�@�u���ꂪ�������Ă��v�@�ق�̈�u�A�ނ̔�����E�C���R���B
�u
�@�ޏ��̏��Ɍ����h��B�}�W�b�N�J�[�h�̌��B���܂ł̂ǂ���������đ傫�Ȍ��B�n�b�Ƃ����B�����g���̂��~�B�ɂ͂킩��B�~�B�������Ă�J�[�h���j�b�g�̒��ł�������������o���̂͂P�����B���̒��ɂ��̎��̗l�q�����肠��ƁB��x������ "�����ꂽ" ���Ƃ̂Ȃ�����x�����B��n�Ƀn���h�R�X�g���P������B��D���R���Ȃ��n�͂��Ȃ��甭�d���B����������ꌂ�̓h���S���̃u���X�Ƃ͌���Ȃ��B�h���S�������ꌂ�͓`���̐�m�̈ꑾ���Ƃ͌���Ȃ��B�y���U��グ���E�̏����A�ʂ�`���悤�ɐU�艺�낳��āB�����ɑM�����A�܂�œV���瑄���ӂ��Ă��邩�̂悤�ɓV�ƒn�̊Ԃ𑖂蔲����B���𗣂��Η����قǂɑM���� �w���x �Ƃ��ẮA�{���̎p�������āB�t�B�[���h����绂���4�̍�����ԑŐs�ɏ�������Ă����B�Z�����X����悤�Ɍ������B
�u
�@�Z�����X������قNj����ł͂Ȃ��B�S�̂��̂����ׂ���u�ɂ��ď������A�S�邽����i���݂Č�����B�`�����h���Ƃ̓����ő�ʓW�J�����݂��̂͂��ׂ̈̕z�B����ꂽ�B�܂�܂ƁB���R���������B�A���A�͂������ƍ��𗎂Ƃ�����Ō����Ղ�͂ށB�����B�`�e����Ȃ炻�̓��B�E�r�������A�ܐ���n�Ɍ������đł����݁A�S�g�̔P����g���ē�����B�s�f�[�����E�\���W���[�t�ė��B
�i����B�����B���̕��w�ɏ��͂Ȃ��B��B�ǂ��ŁB���B���Ȃ��B�������c�c�j
�u���͂��I�v
�@���̂̐��b�ŗh�炮�F���B�A���A�̉s�����ݍ��݂Ɍĉ��������̂悤�ȁs�f�[�����E�\���W���[�t�̓��ݍ��݁B�߂S�T�x�̊p�x����J��o�����s�p�̃{�f�B�u���[�B
�i�n���ȁB�A�g���g��łȂ��P���̉����B������蕨�̃f�b�L�B�Ȃ̂ɂ��̈З́j
�@���̒��x���ᗬ�ɐ܂�Ȃ��B����ł��~�ς͂̂�B
�@�������ނ��덜���݂�悤�Ȏ����B�Z�����X�͎����𗬂��A���̂̂�������B
�i�ԈႢ�Ȃ��B�`�����h���̎��ɂ͎���������Ă����̂��B�����͌������B �w�]�T�ŗ��Ă邾�낤���ǁx �����������B���R���B��S�������Ă����̂�����j
�u���̉����A���̉���ނ����ȁB�A���A�I�v
�u����Ȃ�����p�ł��Ȃ����ǁB�l���~���������ґ�͌����Ă��Ȃ��ˁv
�i�Ȃɂ��l���~�����B�E���C���B�E����Ȃ�E���C���B���́s�f�[�����E�\���W���[�t�̃{�f�B�u���[�ɍ��߂�ꂽ�E�C�B�z�́A�l�̂��ǂ��������킩���Ă���j
�@�������̂̓~�B�B�@�u����Ă��B�s���C�g�j���O�E�{���e�b�N�X�t�v
�u�ΏƓI���ˁv�@�e�C���� �\�\ �����K���ɔ��킹�Ȃ��� �\�\ �����ɂ͂����������B
�u���ڂŌ��������`�����h���͏���Ɂs���҂ւ̎�����t�������Ă����B���̖��́s���C�g�j���O�E�{���e�b�N�X�t�����������B����T�C�h�ɒu���Ă��́H�@���H�@�g���Ȃ��H�@���������������Ƃ��B�u�����ςɂ��Ă��͉̂^���ǂ������ˁB���Ƀp���[�s�������������̖��͍r�点��J�[�h��T���āA����ł���ɖڂ�t�����B���ڂ́s���C�g�j���O�E�{���e�b�N�X�t���݂����ɕЂ��[����A�z�݂��������X�^�[����������B�����������j�B���̏��l���Ă݂�Ίy�Ȃ���B�Z�b�g�̓u���C�J�[�Ō����B�s���҂ւ̎�����t�g���Ă�z���A���ꂱ���s���C�g�j���O�E�{���e�b�N�X�t���Ȃ����낤���ȁv
�u���ȁB�����̏���Ȃ̂ɏ����̌X�����N���A�����ɂ����͂����v�@�Ƃ̓��[�h�̕فB
�u�u���[�g����h�̓J���V�E��������ĂȂ��Z�C�Ȕ]�ؑ������낤���燀�����炩�烉�C�g�j���O�E�{���e�b�N�X���݂��Ȃ����臁�R���āA���q�ɏ���đ�ʓW�J���Ԃ��Ă���B�����Ȃ���߂����́B������L�т������Ƃ���𗋂ňꌂ�B�W�E�G���h���v
�u�}�W�b�N�E�g���b�v���P���Z�b�g�B�^�[���G���h�B������H�v
�u�r�߂�Ȃ�B�n���h�[���ł��R���Ă��B�R���Ă�邼�v
�i�u���[�g������̑O�œ������邩�B���F�͎蕨�̃f�b�L���j
�u�h���[�B�s�v���~�l���X�E�h���S���t��ʏ폢���B�Ή��e��ł����߁I�@�o�g���t�F�C�Y�A�������I�@�s�v���~�l���X�E�h���S���t�Łs�f�[�����E�\���W���[�t���U������I�v
�u�T�O�O���C�t�����ās�c�C�X�^�[�t�B�s�o�[�j���O�u���b�h�t��j��A�s�v���~�l���X�E�h���S���t�̍U���͂͌��ɖ߂�B�}�������Ă�����A�s�f�[�����E�\���W���[�t�v
�u�I������ȁv�@�ƁA���[�h�B�u�������ˁv�@�ƁA�e�C���B
Turn 9
���A���A
�@Hand 1
�@Monster 1�i�s�f�[�����E�\���W���[�t�j
�@Magic�Trap 1
�@Life 1600
���Z�����X
�@Hand 0
�@Monster 0
�@Magic�Trap 0
�@Life 5700
�u�h���[�B�ʏ폢���A�s������m �u���C�J�[�t�B�������@�c�c�v
�i���ڂ��M��ځB�������S�O�͂Ȃ��B�ʖڂ��B�E����j
�@
�u�Z�����X�B�U������Ŏ���ɂ��C��Ȃ��Ƒ������d���邼�v
�u�܌�墂��B���������A���̍D���ɔR�Ă�����B�_�f�z�킹��v
�u���܂��̂��߂��v���Č����Ă�B���܂��͍��Y�̂悤�ɐƂ��B�����g���̂����A�w�C�x���g�������E�ŌȂ����Z�p���Ȃ��A��g������B����Ȃ点�߂ĕ���b����v
�u�Ȃɂ������B����̔��w�ɂ��������̂͂���˂���I�v
�i�b���Ă����Ηǂ������B�ۍ��B�ۍ��������܂ŕ|���Ȃ�ĉ��͒m��Ȃ������j
�@�o�g���t�F�C�Y�B�s������m �u���C�J�[�t������Ƃ�������w�߂��A�ˌ��B
�u�����I�v�@�i���w�c�c�j
�@�s������m �u���C�J�[�t�̕I�S�A���̋��Ђ͈ӊO�Ȃ܂łɒm���Ă��Ȃ��B�}�W�b�N���^���̓ˋN����̕��߂����ĉ������邻�̍U�����@�́A���n�I�ł͂��邪����̂ɋ��͖���B���̎��ɐ܂�Ȃ���Z�����X�B������ �\�\
�u�����I�v�@�i���w����c�c���w�c�c�j
�@�s���r���O�f�b�h�̌Ăѐ��t���A�Ō������Z�����X�̋���t�����B�s�j���[�h�����A�t�̏���͔h�肳�����Ȃ����̂́A�m���ȏՌ��Ƃ��Đg�̂ɋ����B
�u��A��߁c�c�v�@�i���w����́c�c����́c�c�j
�@�Ō������ׂ������ɂ����̂́A�s�f�[�����̕��t�������s�f�[�����E�\���W���[�t�������B���ł͂��邪�A�S�ɋ��_�Ƃ�������ۂ����ł��Z�����X�Ɏv���N��������B��̂Q�̂��U������Ԃɐg�̂����E�܂ŔP��A���ɍU�������͊������Ă����B
�@�\���ȉ���]�������Ă�����y��B
�u���͂��I�v�@�i�����c�c���������Ȃ��c�c�_�f���c�c�_�f���z���Ȃ��c�c�j
�@�m�ۂ��ꂽ�O���_�f���A�ċz��H�Ɉُ����ΈӖ����Ȃ��B
�u���̕��w�Ƃ����ґ���B������ғ�����B����Ȃ�A�Z�����X�v
�@�Z�����X�̓��C�t�Ǝ_�f���Ɏ����_�E���B����Ȃ��̊��S�����B
�@�c�c�A���A�́A���̎����ɂ����債�����l�����o���Ȃ������B
�i�������b�Ȃ̂ɁA���ꂾ������Ă� �\�\�B���� �\�\ �݂��Ă�j
�@�|���Z�����X�A���\��̃A���A�B�e�C���͊��������ɔޏ������B
�u���������Ǝv���Ă��B�P��ځA�����ƃS�������ł����Ă��Ȃ����A����ȋC�����Ă����ǂ��B�����������Ƃ������B�P��ڂ��s���C�g�j���O�E�{���e�b�N�X�t�����Ă��āA�����Ďg��Ȃ��I�������̂����̂����B�������̂Ƃ��n���h�ɂ���A�����Ƒ������Ă�^�C�~���O���������������B�Ȃ̂Ɏg��Ȃ��B�P��ڂ́s���C�g�j���O�E�{���e�b�N�X�t���g�킸�ɗ͂��Z�[�u���Č������I���āA�Q��ڂւ̉a���T���B���X�N���Ȃ��킯����Ȃ��B�͂��Z�[�u������Ă����̂͌����N�����Ă̂Ɠ������ƁB�P�O�O���m���ɂP��ڂ����Ă�Œ���̎d���ɂ͂Ȃ�킯������A���X�N������ƌ������X�N������B����ł��A�m������������Ăł��Q��ڂ��×~�Ɏ��ɍs�����c�c�v
�@�e�C���́A�Ō�ɏ����������������B
�u���������B�������������B����ȕ��ɑ��̍����~�ߍ��������v
�u�������v
�@�~�B���܂��ޏ��̈ꋓ�ꓮ�Ɏ䂫�t�����Ă����B�~�B�́A�ޏ��̌����Ղ����R���݂ɑ����ău���[�g����h���o�b�^�o�b�^�Ɠガ�|���Ă����̂������͕̂s�v�c�ȋC���������B �w���̃f�b�L��������肭����Ȃ�āx �Ɖ���������܂���ǂ���ł͂Ȃ��B���������A�܂��������B���������w���̐g����A�ނ��炢�f�p�ɁA�s�u�ԑg�ŕǂ�o���Ă�A�C�h�����݂��Ƃ����炢�P���� �w�킽��������ȕ��������炢���̂ɂȂ��x �Ɗ����Ă����B�����Ղ̓������瑦���̐헪�Ɏ���܂ŁA�ɒ[�Șb�X���[�C���O�̍ۂ̖����Ȃ��L�т������������w��@�\�\ ���̎�ڂł������Ȃ��L�т��������[�͔����� �\�\ ���~�B�ɂ͑A�܂��������B���������A�܂��������B�~�B�̎����̐�A�A���A�͎������������B
�i���낻����E���ȁB�܁A����������������������Ƃ���܂ł����Ă݂邩�j
�@����A�������Ă݂悤�B
�y����Ȍ��������͎��ʂ̖��ʂ��I�z
�����ǗL���������܂��B�}�G�̓f���G���̂Q�P���I�g�y�i����N���`���Ă���܂����B���ӁB
�������ł��n�j�^�u�ǂv�u�ʔ��������v���A�ꌾ����ł��A������ɂ͋��에�����鏀�����o���Ă���܂��B
���O�b�@���\���@�����b