�@
�@��ɓ������̂͒���ҁB�S�O���̃J�[�h���j�b�g�𑩂˂� �w�f�b�L�x ����A�E��ōr�X�������P��
�u�s�f�����Y�E�`�F�[���t�I�H�@�_�C���N�g�A�^�b�N���Ă���B�r�߂Ă���̂��v
�@�{���͍U����H���~�߂�ׂɎg����g���b�v�J�[�h�A�s�f�����Y�E�`�F�[���t���A�U����H����Ă��甭������B���Ӗ��Ƃ��v����s�ׂɕ��S�A���̈ӂ�\�����钧��ҁB�������_�C���N�g�A�^�b�N���������j�́A�̂̚������������ɂ���������B
�u�����ɋ����Ă݂��������B�U�炴��{�S�����A����Ȃ�̌����͂���B���������悤�v
�@������ɂ���A�����͈����̍��ɂ���Ă��̌��ʂ���������ꂽ�B�^�[���̈ڍs�B����҂͖����̂܂� �w�o�g���t�F�C�Y�x ���I�� �w�^�[���G���h�x ��錾�B
�@�^�[���E�����v��_���������j�̃^�[���B�����悭�J�[�h�������ƁA�ώ������Ձi�����@���A�u���E�f���G���f�B�X�N�B���Ղɍۂ��ĉ~�`�ɕς��^�C�v�̌����Ձj����蓊���A�P�̂̃����X�^�[�� �w�ʏ폢���x ����B�s�S�S�S�W���C�A���g�t�B���ʔ����B��n�́s�S�S�S�S�[�����t��ނ�グ��B
�@���ׁ̈H�@����͂����ɂ킩��B
�u�S�[�����ƃW���C�A���g�ŃI�[�o�[���C�l�b�g���[�N���\�z�B�����v
�@��n�ɕ`���ꂽ�����w�����U��̑匕���o���B���������ԁA���̖��́\�\
�u�G�N�V�[�Y�����I�@�s�m���D�R�X ��]�c�z�[�v�t������Ԃ���o�ꂵ�����������������I�v
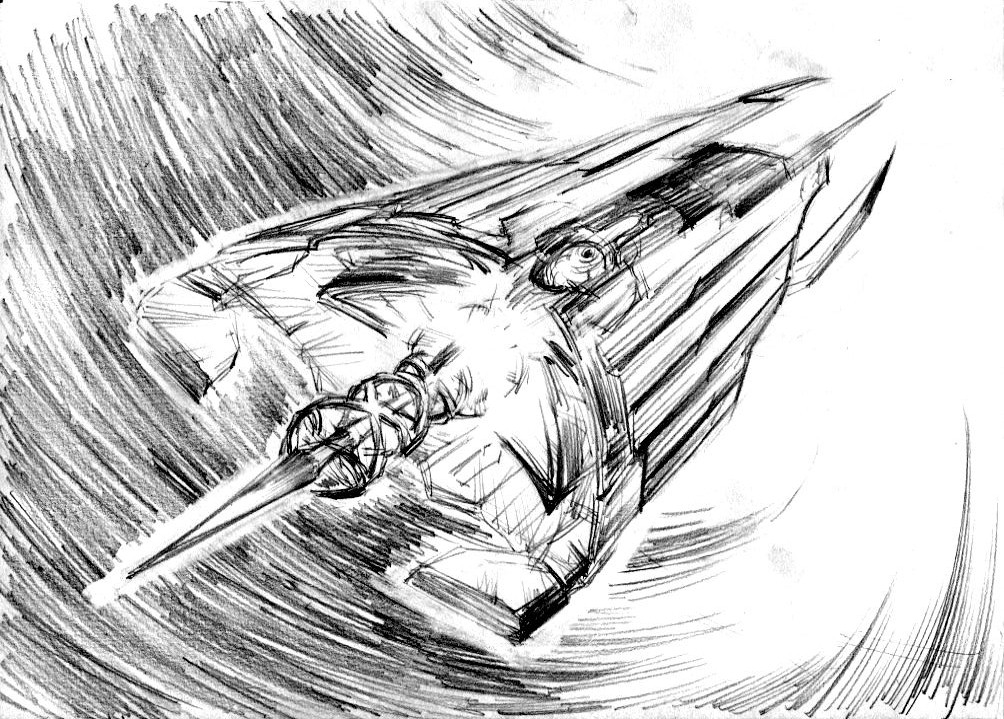
�@�����ۂ����������t�B�[���h�ɕ��サ���̂��A�����̒���グ�������X�^�W�A���ɂ����܂���B
�w�����������炪�^�����B���ł��鑤���猕��U�邤���ւ̈��]���B�������͂����������A���̃t�B�[���h��Ɉ������̊�]���Ăэ���ł����̂��I�x
�@�w
�w�ό`���Ȃ��I�@�\�[�h�t�H�[���̂܂܃O���b�v��͂݁A�z�[�v�������グ���I�x
�@�j�́A�z�[�v���c�[�n���h�\�[�h�ɂ݂��ĂĐU��グ���̂��B�@�u�n���ȁv�@���h���钧��ҁB�������w������Ƃ������͂ނ��떂����U��グ��ْ[�̏��ƁB�j�͑S�g�� �w�C�x �����ɒ����B�w�悩��A�O���b�v����A�G�N�V�[�Y�����̍۔������閂���w������ɂ܂ŏ㏸���Ă����B
�u�J�I�X�G�N�V�[�Y�`�F���W�I�@�z�[�v�\�[�h���z�[�v���C�\�[�h�ɐi�������������I�v
�@�s�b�m��.�R�X ��]�c�z�[�v���C�t�B�������A�炵�Đ���������B�j�́A��O�̖����Ɍ������Đ����悭�U���a��B�����͗���Ă��邪�W�Ȃ��B�a�����Ռ��g�ƂȂ��Ė����𑨂���B�|��͂��Ȃ������B����ł悩�����B�ނ��낻��ł悩�����̂��B�|���̂͂�������B�w�U���x �ł͂Ȃ� �w���ʁx
�u������̎c�胉�C�t���P�O�O�O�ȉ��ł��邱�Ƃ������ɁA�z�[�v���C�\�[�h�̌��ʂ������A�\�\�\�\�@�̍U���͂��O�ɂ܂ʼn����A�s�b�m��.�R�X ��]�c�z�[�v���C�t�̍U���͂͂S�O�O�O�ɂ܂ł�����v
�@�j�͑匕����U���ɍ\�������A�E��A�����Ɍ������ēːi����B��̌U����͍��ォ��E���ւ̈ꌂ�B���Ɏa��ׂ��ꏊ�͌��܂��Ă����B��������E��A�a���̐Ղ�X��`���悤�ɋt�U���Ŏa��B�a��邾�낤���B�z�[�v���C�\�[�h�ɂ͐n�����Ă��Ȃ��B�����܂ʼn��̎p�B��ʂƍl������������邾�낤�B�������A�ނ���₢�����B�Ȃ��a��ʂƎv���̂��B�n�̗L�����͍����Ȗ��B�����҂̐n�Ƃ͂��ꑦ�����̐n�ł���B�����ƌ����҂̉\�������������Ƃ��V���Ȕ��͊J�����B�a��Ȃ����������낤���B�@�u�n���ȁv�@����҂͂����R�炷�̂�����t�������B
�w���܂������I�@��M�c�c�������Ƃ��̂܂܂̐����Ŕ�I�@�g�h�����h���C�������I�x
�@����яオ�����j�́A��������Ɍ����A�O���b�v���R���Ė����̔]�V�ɗ��Ƃ��i����̓O���b�v�ƌ����ɂ͐�肷���Ă������A�ނɂ̓O���b�v�ł����Ȃ������j�B���h���ł���B
�w���܂������I�@�_�C���N�g�E�J�I�X�X���b�V���I�@���̈ꌂ�͋��I�x
�@�j�͏d�͂ɏ]���A��n�ɓ˂����Ă�ꂽ�z�[�v���C�̖��[�ɒܐ�ŗ��B
�@�ނ͊�O�̑�����������������B�@�u�����œ|���v�@�����������Č������B
�u�s���r���O�f�b�h�̌Ăѐ��t���B�Ώۂ͕�n�́c�c�s�A�[���Y�E�G�C�h�t�v
�@�j�̓z�[�v���C�\�[�h�̃O���b�v���R���Ĕ�ԁB�ǂ��ցH�@�m�ꂽ���ƁB�s���r���O�f�b�h�̌Ăѐ��t�œ��ꏢ�����ꂽ�̂́s�A�[���Y�E�G�C�h�t�B�s���܂����A�r�̌`�����������A���邢�͈��̑��g��B�j�͔��Ă̖T��E�r�Ɂs�A�[���Y�E�G�C�h�t���A����҂Ɍ������ėE��B
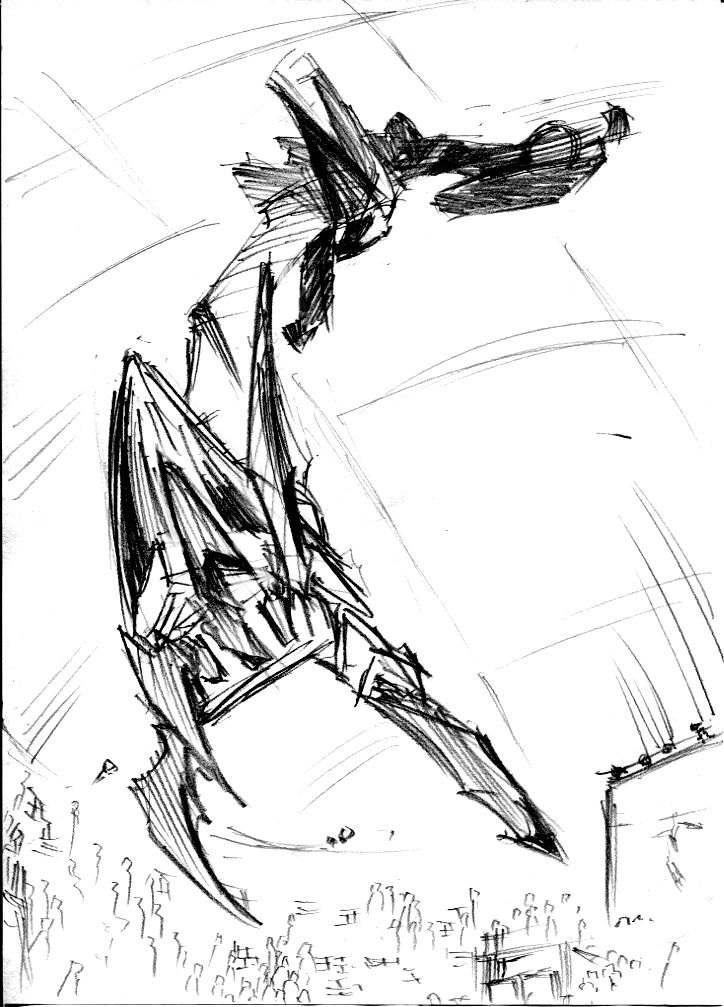
�@�Y�X�����������j�͍��r�őΐ�҂̉��֒��n�A�Ɠ����ɉE�r��U��B
�@�����ʂ�\�\�_�C���N�g�A�^�b�N���B
�w���܂������������������������������������������������I�I�I�@�ǂ��z���I�@������˂������āI�@�Ɂc�c���܂Ȃ��I�@���˂āI�@���˂āI�@���˂āI�@���˂āI�@�p���[�E�M�A�E�V���[�g�ł������c�c�t�B�j�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�b�V���I�I�I�I�x
�@�����ƌ����҂̑�����ʂɂ���đ������ꂽ�Ռ��g�B����҂��ǂ��܂Ő�������Ռ��g�B�j�́A�_�C���N�g�A�^�b�N�̔���p�𗘗p���čĂђ���A��n�ɓ˂��h�������z�[�v���C�\�[�h�̖��[�܂Ŕ�сA��͂�ܐ�Œ��n�B�Ȃ̐�ʂ����͂����̂��A���r���L���A�����ā\�\
�u���N�A��X��
�@�����̕���Ƃ������́A�ނ��날����̕���B
�@����̑O�Ɏ���������B�����ɂ�
�@���̕���͒N���̈��L�ł��Ȃ���Ή��炩�̎�������Ɉ��������̂ł��Ȃ��B���E�����Ɏn�܂��Ă���̂Ɠ������炢�ɂ́A�n�܂��Ă���Ƃ����Ƃ����Ɏn�܂��Ă���B�債�Ďn�܂��Ă��Ȃ��Ƃ�����͂�債�Ďn�܂��Ă��Ȃ��B���̕���ɂ�����͂��߂̈�����q�ϓI�ɋK�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�K�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�������A�K�肷��K�v�͂���B���ǂ̂Ƃ���A���ǂ��ŒN�����������������Ƃ������Ă��̕���̔��[�Ƃ�������ȊO�ɂȂ����낤�B�����Ă��ꂪ�����ƌ�����ATCG���W�Q�N�Ƃ��邱�ƂŁA����ɂ��Ă͓��Ɉ٘_�����ސl�Ԃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�������A�ǂ��łƌ�����Ə�������ʓ|��������Ȃ��B�k�̑�n�ɎY�������������̉傪�D���B�̘r�����ɐ��߂Ă��������Ƃ������Ĕ��[�ƌ�������̂��������낤���B���邢�́A���̃f���G���g�[�i�����g�ŗD���҂����܂����u�ԁA����̍Đ������L�^��啝�ɍX�V�������Ƃ������Ĕ��[�ƌ�������ׂ����낤���B���邢�͓�̌����ٔ��ň�l�̌����҂��M���`���ƃJ�[�h�̓N�w��_������Ɍ������Ƃ������Ĕ��[�ƌ����ׂ����낤���B���邢�͒����A���邢�͐��E�A�O�l�����́c�c�m���ɂ����͖��͓I�ȏo������������Ȃ��B�������A�����Č����Ȃ�� �\�\
�@TCG���W�Q�N�A�āB�~�B�Ƃ������̏��������ōs�����K�͑����ϐ킷�ׂ������𑖂��Ă����B�~�B�������~�����ׂ́A�Ⴂ���������ɂ� �w�w�u���Y�A�b�p�[�x �Ȃ鎄�c�̃J�[�h�V���b�v�������Ă���B�����������̂悤�Ȏ����W�����݂��Ă����B
�@����́A
Duel Episode �P
����������
�`���X�ƒg�F�Ɩ��@�g���`
�u�H�����v
�@�~�B�͊���ׂ߁A����Ƃ�����ŊŔ��݂Ȃ���v���B����B�킩��B���̕ӂ͎��ƊJ���̂܂��������B�����Ƃ͌���Ȃ��B�H����������ʍs�~�߂Ƃ����̂��킩��B����ł� �\�\ �~�B�͕��S�����B�I�[�g�� "��" �̎����Ȃ��B�Ȃ�ƕs�e�Ȃ̂��낤�B���̃��b�g�[�̓t�H�A�E�U�E�`�[���ł͂Ȃ������̂��B����ɋC���g���Ƃ��������͂Ȃ����̂��B�����������B�m���Ɏ����ɂ������x�͂��邩������Ȃ��B�}�����������܂�A��ʂ���g��Ȃ����������ɂ��ӔC�̈�[�͂��邩������Ȃ��B
�@����ł� �\�\
�u�����ł��������ł����B���X�Ɩ߂邾���߂��đ�ʂ���s���Ƃ������Ⴂ�܂����v
�@���̕ӂ̗�����ʂ�悤�Ȓ��ԊO��͂��̏��������X�Ƃ��炢�܂킵�ɂ���Ă��\��Ȃ��Ƃ��������܂����B�����������B�~�B�͎��Ԃ������Ă��邱�Ƃ��Y�ꕨ�v���ɂӂ������B
�i���ԊO��͂����������B���̕Ȏ����̂�G��悤�� �w�˂��~�B�H�@���v�H�x ���āc�c�Ⴄ�Ⴄ�B����Ȃ��ƍl���Ă�ꍇ����Ȃ��B�ǂ����悤�B���X�����Ԃ��Ȃ�āj
�@�M���B���̕����悶�o�������B���p�ɂȂ��Ă邩��N���ɂ݂���S�z���Ȃ��B�s�V�������͔̂ۂ߂Ȃ����A�����͍̂s�V�ł͂Ȃ��s�����B����������[��������B
�i���������āA�ǂ̌������́c�c���A�J�[�h�V���b�v�j
�@�J�[�h�V���b�v�B
�@���͖S�����ꂳ�����Ă����B�~�B��
�i����ɍ��͒��B�s�ǂ̎��Ԃ���Ȃ��B�������Ⴆ�B�ق�����v�c�c�j
�@����������ƁA����́A�ō��̃v���C���O�~�X�������̂�������Ȃ��B
�u�����̃u���[�g������ɂԂ����Ƃ��āA�R�X�g�̎x�������Ȃ��Ƃ��r�߂Ƃ�́v
�@�~�B�̊炪��������B���v����Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A���ꂾ���͊m���������B
�u���B���߂�Ȃ����B���́A�ق�ƁA���́c�c���߂�Ȃ����B���߂�Ȃ����I�v
�@���ӂ�B���ꂵ���Ȃ��悤�Ɏv��ꂽ�B�ʗp���邩�ǂ����͂܂��ʂ̂��b�B
�u�S�����ł��琾����ʂ͂���Ȃ���˂��B���������ē��ݓ|���C�H�v
�u������Ƃ������̃��C���t�F�C�Y�݂��Ă��炨������Ȃ��́B�ł���˃u���[�g������v
�u�ӂ�������Ȃ��ł����B����ɁA���́A���́A�킽���A�}���ł��ł��B�ʂ��Ă��������v
�@�T���Ƌ��|�Ɣ����ƁB�����������Ԃ����ĂȂǂ��Ȃ��B�ق�̈�u���ƕ����G�ꂽ�����B�Ȃ��ӂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��B����ȃ~�B�̕s���ȂǁA"�ނ�" ���l�����锤���Ȃ��B
�u�ǂ��ɂ����̂��ȁH�v�@���Ɣ�ׂāA��◎�������������~�B�ɖ₢������B
�u���c�c���w�Ɂc�c�v
�u���H�@���݂�������������Ɂc�c����͌��F�̑�K�͑��ł����̂��ȁB��H�v
�@�~�B�͗��������B���̒j���u���[�g���Ȃ̂��B���˓I�Ɏv�����B�����ȃ^�C�v���ƁB
�u���̃u���[�g�������������݂�������������ɂ��������B �w�x���A���x �����Ă���v
�@��������Ƃ��������Ȃ��Ƃ��B�Ȃ�����Șb�ɂȂ��Ă���̂��B�~�B�ɂ͂킩��Ȃ��B
�u�u���[�g������Ǝ荇�킹�ł���`�����X���ق��ۂ肾���āH�@���肦�Ȃ��ˁH�@���肦�Ȃ��ˁH�@����ȃ��x���̒Ⴂ���Ƀ_�b�V���������j���O����Ƃ����肦�Ȃ��ˁH�v
�u�u���[�g������A�݂Ă����B�����̃o�b�O�Ɍ����ՁB�Y����Y��Ȍ����Ձv
�i���̊ԂɁB���ꂪ���c�̃J�[�h�V���b�v�H�@�f�B�X�N�̓�����k��������Ȃ�āj
�u�Ԃ��āB�Ԃ��Ă��������v�@�u�������Ⴈ�����Ȃ��B���ĂĂň������Ⴈ�����Ȃ��v
�@�}�C�z�[����y���œ��ݍr�炷�悤�ȏ��ƁB�ƂĂ�������킯���Ȃ������B
�i���ł�B��������ł�B�U�X�ӂ����Ă����āA�܂���ʂ�Ǝv���Ă�j
�u�����̃u���[�g������ւ̂��l�т̂��邵�A�D���Ȃ����h���[���Ă��炤�̂���������ȁv
�u����ȁI�v�@�厖�ȑ厖�Ȍ����ՁB�������������q�����B�@�i�_�l�����B�s���������j
�u������B�����������������v�@�u���[�g���ƌĂꂽ���̊i�����r��傫�����ɍL���A���Ɍy������킹��B���ɂ܂����悤�ȕ\��ŁA�ނ͏d�X�������������B
�u�n�܂����B���ꂱ�������w���B�����c�c���܂ꂽ�B�V�������w���������Ő��܂ꂽ�v
�u�������������B���B�̃u���[�g������A�C���X�s�����菄���Ă˂��݉ԉ��x���Ă邺�v
�u���̃u���[�g���A�J�ɖ���������ҒB�Ƃ͊T�O���炵�ĈႤ�B���̂ł͂Ȃ������Ղւ̃X�s���`���A���A�^�b�N�B�F����MTP�����́A���F�̔]�זE���~�g���ĐV���Ȓn���ɂ����Ȃ����낤�B���̂Ɏw��{�G�ꂸ�Ƃ��A�u���[�g���̒鍑�͂��̐��_�I�̓y���g��ł���̂��v
�uMTP�Ƃ̓��^�t�@�[�̈ӁB���B�̃u���[�g������͍������펯���u���C�N�U�o�b�N�v
�u�u���[�g������͈��400mm��MTP�ێ悪�̑�Ȃ��]���[������ƐM���ċ^��˂��v
�u�C�[���b�z�E�I�@�u���[�g������̖��������������B�̒m�����ݍ���ł���邺���v
�u�����͎ؗ�`��_�j����V����B�l�I�E�f���G���E���^���`���[�̑䓪�B�r�o�E�u���[�g���v
�@�~�B�͈��|����Ă����B�ӂƎv���B���Ȃ瓦������̂ł͂Ȃ����B���������Ăʂ悤�E�ё��B�ς��ƌ����Ղ�͂�ő���o���c�c��m�b�ɉ߂��Ȃ������B�r��͂܂��~�B�B
�@�����͂����ނ�̃t�B�[���h�B
�u�ى��������Ȃ猈���ŕ����Ƃ����B���̃u���[�g���A�����̕��w�ɗD�����፷���������ʂł��Ȃ��B�Z�����X�A���܂������������B���܂��̉��ō߂Ɣ����v�邪�����v
�u�u���[�g������̗��݂Ƃ���Βf�闝�R�͂���܂���B�������̌����Ղ����Ȃ��삿���B�����ǂ܂��܂��A��Ȃ��B�킩�邾��H�@�Ȃ�Č����������A�킩�邾��H�v
�i�����������j
����Ȃ������ɋ߂��₢�����B�~�B�́A�L�������킹�ʗ��s�s�ɗ��ߎ���Ă����B
�i���v�Ȃ��ƂȂ�ĂȂɂ��Ȃ��B������@�u�����āv�@�Ȃ�Ďv�����Ⴂ���Ȃ��j
�@�P�m���Ɍ����邱�ƂƁB�~�B�͒m���Ă����B�Ȃ������Ă邩���߂悤��A�Ȃ�ċ�C�̓ǂ߂Ȃ����Ƃ������Ă��̎��]�Ԃ���~�낵�Ă����l�Ȃ�Ă��Ȃ����Ƃ��B�����Ȃ��͖̂����Ȃ�A�Ȃ�Ęb�̂킩�邱�Ƃ������Ă��̕s�����h���b�V���O�̂��������������̃T���_�����������Ă����l�Ȃ�Ă��Ȃ����Ƃ��B���̏�ł����ł݂��邵���Ȃ��B���̏�ŐH�ׂĂ݂��邵���Ȃ��B
�@�N�����̂ɂȂ邩�A���ꂪ���Ȃ�[���ɖ߂������Ȃ��B
�i�킽���������ׂ����t�͂P�B�@�w�킩��܂����B�킽���Ə������Ă��������x�@�j
�@���Ă邾�낤���B�������Ǝv�����B���炭�A�������������v���Ă��邾�낤�B
�i��������m�ł킽����j�����ȂB�Ȃ�Ĕڗ�Ȑl�B���낤�j
�@�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃɒ��킵�Ȃ�������Ȃ��̂��B�l���͓w�́A�w�Z�ň�Ԑl�C�̂���搶�͂����������B���߂�ȁA�w�Z�ň�Ԑl�C������搶�͂����������B
�u���������ǂ������H�@���t��Y�ꂿ������̂��H�@���ꂶ�Ⴀ���w�ɂȂ�Ȃ����v
�@�~�B�Ɍ��킹��A���̋��t�͂Ȃɂ���������̂��Ȃ��l�Ԃ́A���̈�����Ȃ��������Ƃɂ��邽�߂����̓w�͂̈Ӗ���m��Ȃ��B���������Ȃ��B�S���炻���v�����B���������Ă��傤���Ȃ��B�����͗]�v���邾���ȂB�����猾�������Ȃ��B���������Ȃ��B���������Ȃ��B
�u�킽���ƌ������Ă��������B�킽�����������炱�����������Ă��������v
�@���̌����Ղ͑厖�Ȃ��̂������B�G�ꑱ����`�����X������̂Ȃ�A�������������ƂȂǂǂ����Ăł��邾�낤�B �w���v�x �~�B�͂����S�̒��ł����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@--OZONE--
�@�����Փ��m�̋����`���A���킸�ƒm�ꂽ�����ҒB�̎���B���̋�Ԃ̒��ł͏��ʂƕ���������d�B�_���Ɣg������������ՎD�̈�B�����͂��̈Зe���A�����͂��̈З͂��Ռ��g�Ƃ��Ĕ���������B�~�B�ƃZ�����X�͎���̌����Ղ𑀍�A���D�`��(�f���G�����[�h)�Ɉڍs�A��������B���N������錕���m�̂悤�ɗY�X�������������Q�̌����ՁB�~�B�͉E�r�ɕt���Ă��������Ղ𗘂��r�ł��鍶�r�Œ͂ނƁA�����č\����B�T�C�h�X���[�BTCG�ɂ����ĕW���Ƃ���邠��ӂꂽ���ՁB���ꂪ�T�C�h�X���[�B�Z�����X���E��Ō����Ղ�͂݁A���l�̍\���ŊJ�n�̍��}��҂B
�@�����ā\�\
Starting Disc Throwing Standby�\�\
Three�\�\
Two�\�\
One�\�\
Go�I Fight a Technological Card Duel�I
�@�~�B�ƃZ�����X�������Ɍ����Ղ������[�X�A�t�B�[���h�����̃f���G���T�[�N���łQ�̌����Ղ��������Ȃ̑��݂��咣�������BTCG�̓^�[�����̋��Z�B�펯���̏펯�B�����̑ł��������K�X�`�F�[����g�ށB�T�Ύ��ł��m���Ă���B���ꂪ�����B�����ɂ͗�O�BTCG�ɂ͓����i�s�ōs����ŏ��ōŌ�Ƃ�������u�Ԃ�����B���ꂪ�����J�n�����Starting Disc Throwing�iSDT�j�B�����X�^�[�E�}�W�b�N�E�g���b�v�ɈӖ��ƏՌ���^����f���G���t�B�[���h �w--OZONE--�x �Ɍ����Ղ��o��������ƂƂ��ɁA��U��U�����߂�d�v�ȋV���B�����J�n��錾����̂͗���l�A�����J�n���\�ɂ���̂� �w--OZONE--�x �������A�����J�n�̏���炷�̂͌����ҁA���̐��_�̕\��Ƃ�������̂�SDT�B
�@����A�����̈ӂ�ʂ����̂̓Z�����X�������B�~�B�̌����Ղ͈���ɂ��e���ꎝ����̏��ɖ߂�BSDT�𐧂��A��U���l�������̂̓Z�����X�B�@�u�����q���d������悤�Ɂc�c�h���[�v�@�ނ́A�P���̃J�[�h���j�b�g�������ՂɃZ�b�g����ƁA���̃X�i�b�v�𗘂����ē�����B
�@���̓��ՁA���ꂱ����TCG�B���ꂱ����Technological Card Game�B
�u�s���H���J�j�b�N�E�G�b�W�t��ʏ폢�����Č��ʔ����B�Â��Ȃ铔�c�c
�@�s���H���J�j�b�N�E�G�b�W�t�̉����~�B���P���B���e�ӏ��ɒɂ݂�������~�B�B�����Ƃ��A�{���̉��ł͂Ȃ��B �w--OZONE--�x �ɂ���ĕ]�����ꂽ�s���H���J�j�b�N�E�G�b�W�t�̉����A�Ռ��g�ƂȂ��ă~�B���P���B�T�O�O�ɂ��Ă͈З͂������B�~�B�͓��S�����Ă����B
�i���̌����B���ꂪ�ق�̏��蒲�ׁH�@�ǂ����悤�B���̐l�͂����Ɨe�͂��Ȃ��j
�u�R������悤�ɍr�X�����I�@�}�W�b�N�E�g���b�v���P���Z�b�g���ă^�[���G���h�v
�@�~�B�̃^�[��������B�@�u�h���[�v�@�����Ղ���J�[�h���P�������Ĕ����J�n�B�s���H���J�j�b�N�E�G�b�W�t�̍U���͂͂P�W�O�O�B�|���Ȃ�����ł͂Ȃ��B�����Ƒ��v�A�����M���Č����Ղ� �w�C�x �����߂�B���_����ł͂Ȃ��B���Ղɕs���ȍ�ƁB�l�ނȂ瓖�R�����Ă��锤�̌����C��(�f���G���I�[��)�������Ղɒ������݁A�X�J�[�g���߂���Ȃ����x�ɐU�肩�Ԃ��ē�����i�����[�X�j�B�s�b�f�̊�{����B
�u�s�f�[�����E�\���W���[�t��ʏ폢���c�c�����v
�u���������ǂ������H�@�����X�^�[�P�����ł��Ȃ����B�����̂��Ȃ���Łv
�@�~�X�B�ʏ폢���ł͂�����x�`�����X������Ƃ͂����A�����ŏ��̓��Ղ����s����̂͐S���I�ɂ��ɂ��B�~�B���g�A���X��肢���ł͂Ȃ��A�ނ��뉺��ɂ�����Ƃ͂����A�����Ŏ��s�����̂͂�͂�v���b�V���[�v�f�ɂ��đ�B�T�l�Ɉ͂܂�鐸�_�I�d�����~�B�̐S����ߕt����B
�i���v�A���v�A���v�c�c�j�@���F��̂悤�ȘA�āB�@��͂܂�����B
�u�Z�J���h�X���[�c�c���肢�c�c�ł����B���̂܂܃o�g���t�F�C�Y�c�c�v
�@�������A�Z�����X�̖W�Q���Ȃ��̂��݂ĂƂ����~�B�́A�A������Ńo�g���t�F�C�Y�ɓ˓��B�ꑫ��тŁs���H���J�j�b�N�E�G�b�W�t�̊�O�܂Ŕ������s�f�[�����E�\���W���[�t�́A�g�ɂ��Ă����}���g���O���ăG�b�W�ɔ킹��B���E���ǂ���p�͂܂����������B�\���ȏ��Z�������ās�f�[�����E�\���W���[�t�͌����}���g�̏ォ��U�艺�낷�B�������A�艞�����Ȃ��B
�u�Ȃ�Łc�c�v�@�����ɂ킩�����B�Z�����X�̌����R���Ă���B�s�Η�p�|�u�g�v�t�B
�Η�p�|�u�g�v�i�ʏ�㩁j
�����t�B�[���h��̉����������X�^�[�P�̂������[�X���Ĕ����ł���B
�����[�X���������X�^�[�̌��X�̍U���͕��̃_���[�W�胉�C�t�ɗ^����B
�u���炦�v�@�Z�����X�̌�����������Ή��e�B�~�B�̐g�̂������e���B
�i�ɂ��B���킹�ĂQ�R�O�O�_���[�W�B���Ȃ��ƁA���Ȃ��Ƃ��ꂿ�Ⴄ�j
�u���C���t�F�C�Y�Q�B�}�W�b�N�E�g���b�v���P���Z�b�g���ă^�[���G���h�v
�@�u�ԁA�����������B�~�B�͂������܋C�������B�Ȃ�Ƃ����}�~�X�B
�u���������B�܊p�ǂ��������̂ɁA���́s�f�[�����E�\���W���[�t�͒u�����H�v
�@�s���H���J�j�b�N�E�G�b�W�t���s�Η�p�|�u�g�v�t�Ń����[�X���ꂽ���Ƃɂ���͂���B���̂܂܉���P�X�O�O�_���[�W�B�ܕ��̏Ɏ����čs�����B����Ȃ̂ɁB
�u���������قǔR����悤�ȃh���[�I�@���S����B�����A�^�b�N�`�����X�͂��Ȃ��B�_�C���N�g�A�^�b�N���Ă��悤�����Ă��܂����W�Ȃ��W�J�ɂ��Ă��B������Ȃ��Ă��ނ���H�@�s�\���m�`���E�����t��ʏ폢���A�ƁA�����Ō��ʔ����B���܂��̕����J�[�h�̓g���b�v���v
�u���H�v�@�u�s�y�����b�t���B�c�O���ȁB���̃J�[�h�͂��������ł��Ȃ��v
�u�Z�����X�߁B���ӂ̍����퓬�ň�C�Ɏd���߂���肾�ȁv
�u��n�̉��������Q�[�����珜�O�B�s���̐��� �C�t���[�g�t����ꏢ���B�o�g���I�v
�@�Z�����X�̓����͎~�܂�Ȃ��B�����Ղ���p�ɑ����ĘA���������ʂ����B�s�f�[�����E�\���W���[�t�͈�u�ŔR���s���A����̏�ɗ\���m�̈ꌂ�B���C�t���������v
�u�^�[���G���h�B����B����Ă݂��B������̂Ȃ����Ă݂��v
�u�h���[�c�c�킽���́c�c�����X�^�[�J�[�h���P���Z�b�g���ă^�[���G���h�v
�u���̃^�[���A�h���[�B�I��肾�B�s�\���m�`���E�����t�̌��ʂŁs�y�����b�t�E�B�sUFO�^�[�g���t��ʏ폢���c�c������R�₵�A�s���O�̍� �Ɖt����ꏢ���v
�i�U���͂ƓW�J�͂��Ⴂ������B�܂�ŏ����ɂȂ�Ȃ��B��������j
�u�R�₹�R�₹�B�g�}�g�P����c���ȁB�S�Ă̔����Ă������I�@�s���O�̍� �Ɖt�̍U���B�u���[�g�����w�u���I "
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\���v�Ȃ��ƂȂ�ĂȂɂ��Ȃ��\
�u�����Ȃ��삿���B������̂͂ȁA�Ƃ��鉊���E���ɂ����A���ۂ͎��C���}�b�`�݂����ȃ`�[���ɂ�����B���������������œ| �w�A�[�X�o�E���h�x �̈�_����ŃK�b�`�K�`�B���K������Ȃ��������炾���āA�����܂�̃Z���t�ŁY���������߂����ɑ��o�Ă�悤�Ȃ������B�����ւ����ƃu���[�g������� �w�x���A���x �͎��R���݁B���S�Ȃ镶�w�v
�@�ł��ӂ���A�u�E���ꂽ�~�B�̓Z�����X�̕ق����悤�Ȋ�ŕ����Ă����B
�u�u���[�g������̈ꕔ�ɂȂ��B���������~����B���܂��̌����Ղ���f�b�L�����삫�A�u���[�g������̍��̃f�b�L�P�[�X�ɑ}�������B����Ń`�������B�`�����`�������v
�i�`�����B�[���B��������Ȃ��B����Ň����v���j
�u�u���[�g���c�c����c�c����c�c�v
�@�Ⴆ�S�߂ȕ������ł����Ă� �\�\
�u���I�@��Ɍ��I�v �͂��Ȃ��܂ł̒�R�̈ӎv�������B
�u�u���[�g������́A�쌴�ɍ炭��ւ̉Ԃ������悤�ȗD�����፷�������₷��̂��B�������܂���y�G�b�`���O�E�}���g���s�[�X�z�̑Ԑ��ɓ���B�u���[�g������̖��_�����v
�i���H�@�ȂɁH�@�͂܂ꂽ�H�@���_�A����Ȃ̃��_�j
�u����͂��������A����͂��������g�F���͂ރ}���g���s�[�X�̂悤�Ɂv
�u����͂��������A����͂��������g�F���͂����ރ}���g���s�[�X�̂悤�Ɂv
�@�Ȃ�Ƃ������Ƃ��B4�l�������1�l���͂ށB�����Ȃ��Ă͂�����������Ȃ��B
�u���܂��͂���
�u�܂��Ƀu���[�g�����w�̐^�����B�ЂƂ��уh���[���ꂽ���Ō�A���C���t�F�C�Y����G���h�t�F�C�Y�܂ŁA�t�B�[���h�����n�܂ŁA�u���[�g������̏��̏�B���y���͊m���v
�u�����u���[�g�����������������B���_����邽�߂Ɂv
�i�����B����Ȃ̌� �\�\ �j
�u����
�i���H�j
�u�N���v
�i�N�H�j
�@�������A���������Ȃ鏭�����n��܂ŔG�炷�Ƃ��A�ނ�͖��ʂ��D�u�ƌ��ꂽ�B
�u�����Ă����B�R�A�������[�J���̗t���͂މ����B�f���G���O���[���v
�@���̒j�́@�u������݂�B�ނ��남����݂�v�@�ƌ�������ł������B
�i�͂��H�j
�u�f�B�X�N�͐o���K����ⴁB���������|���撣�낤�B�f���G���u���[�v
�@���̒j�́A���̕ӂ肩��K���Ƃ��ڂ����ӂ��ӂ��ȉ�����L���Ă����B
�i�ӂ��H�j
�u�����`���ƁA����ǂ���������ȁv
�u�͂��I�@�ǂ����v�@�u�ǂ����I�v
�u�����ڗ��������Ȃ�����ǁA�Ȃ�Ƃ������킽�������Q�����Ȃ��킯�ɂ������Ȃ��āB����܂�݂Ȃ��Ńf���G���C�G���[�c�c�f���G���C�G���[�c�c�����̂��ȁA����Łv
�@���̏��́A����������������h�炵�A�o�c���������ɘȂ�ł����B
�i�c�c�Ȃɂ��̒��ԁj
�u�������܂���c�c�v�@�Z�����X���E��Ō��t�����ށB���B�������Ⴂ�Ȃ��B
�u������Ƒ҂āB�Ȃ�ŃC�G���[�H�@���b�h����B���b�h�����Ȃ����낻���́v
�u���Ɉނ���Ȃ��B���̃W�����p�[���F�H�@���߂āA���߂ăs���N�ł���v
�u���������܂�킩��Ȃ��āB����A���b�h���s���N�̓�ґ�����ĂƂ���܂ł͂��������ǁA����ǂ����������̂��킩��Ȃ���������Ԃ��Ƃ��ăC�G���[���Ȃ��āv
�u�Ԃ��Ƃ����牓�����邾��v�@�u����Ȃɂ����Ȃ炠�����b�h���悩�����̂Ɂv
�u������(���u���[)���������悤�ɐ^���ԂȃW�����p�[�Ɍh�ӂ�\������B�����킩�����킩�����B���Ⴀ���ꂪ���b�h�ȁB�f���G���O���[�����߃f���G�����b�h�����Ɍ��Q�B�������A�������v
�u�U�ߒU�߁B���̂��A�m���m���ł̂������Ƃ��Ă��ꂾ���ǂȂ�Ő�����������Ȃ�H�v
�u�������͂T�l����B�������͂R�l�B��������Ă����Ƃ��Ή��R���Q�l����̂͂��v
�u���������B�ʔ�����킾�ˁB������ɂ��ꂪ�`����Ă邩�ǂ����͓䂾���ǁv
�u���傤���Ȃ��B�����Ƃ����B���̂��A����獡��Ƃ��R�l�����ǁA�����́A�ق�A�����������B���Ƃʼn��R���Q�l�قǁA�O���[���ƃu���b�N�����銴��������v
�i�Ȃ�Ȃ́B���̐l�B�j�@�~�B�́A���C�ɂƂ�ꂽ�܂ܓ����Ȃ��B
�u�ӂ�����ȁB���܂��炢���������҂��B�����̃_�`���Z�킩�v
�u���Ζʂ��B������͏��Ζʂ���������̂���B����
�@�x�܂��Ȃ���~�B�͗��������B�ނ�͂ӂ����Ă���̂��B��������͓��ΐ��ɉ�t�����������B�r�߂��Ă���ƒm���āA�u���[�g����h�͕��{�̏��˂��グ��B
�u���̃u���[�g�����Â����ς��邩�B���̂܂ܖق��Ĉ���������Ɓv
�u���̒ʂ肾���B�p�Ɩ��_��m��u���[�g�������߂��߈���������Ȃ��肦�˂��v
�u�����̓u���[�g������ɂԂ����ăZ�����X�ɕ������B���Ƃ��O�͂��Ă��炤�v
�u�ǂ����������Ɏ�������B�܁A�������B����Ȃ炻��ŁB�������炱�����悤����Ȃ����B���ꂽ���Ƃ��܂���Ń`�[���f���G���������Ȃ��B���ꂽ�����������炱�̖����������B�ܘ_����������Ȃ��B���܂��������������炱�̖����D���Ƀh���[���Ă������v
�i����H�@�Ȃ��������悤�ȁB�����Ă����̂͊��������ǁc�c����H�j
�u�ق��B �w�x���A���x �Ɍ����ނ��B���X���T�S�A����ł������Ɓv
�i���R����̂��R�����Ă�Ă�j�@������O���B�~�B�͂�������Ƃ����B
�@�~�B�̐�]��m���Ēm�炸���A���b�h�i���j�͈ӋC�g�X�ƌ����グ��B
�u���������߂��P�l�B�����Ɋ������ދC�Ȃ�ĂȂ����v
�u���C���ȁB���� "�u���[�g���`���̉Ă̖����n�`" ��O�ɂ��āv
�u�N�N�c�c�݂��邺�B "�u���[�g���`���̉Ă̖����n�`" ���҂�u�Ԃ��v
�u���A�ٖ��Ȃ���B �w�Q�S�G���A�̖ҌՁx �Ƃ��A���������̂Ɠ����m���H�v
�@�C�G���[�i���j�̈ꌾ�͌y���������B��Ăs����̂̓��b�h�i���j�B�@
�u�ׂ������[���͂������Ō��߂����Ă���Ȃ����B�V���� �w�x���A���x �Ȃ�v
�u�������낤�B�������B���������Ƃ��́A����ނ��돟�����ł͂ǂ��Ȃ邩�킩���Ă�ȁv
�u�����B�f���̎v���ł��̖��������o�����B�ς�Ȃ�Ă��Ȃ�����Ȃ蕚����Ȃ�R�X�g�Ȃ�v���C�Ȃ�D���ɂ�������B�ǂ����悤�����܂������̎��R���v
�u�킩�����B�ςďĂ��ċ�ɂȂ�܂ň������āA���̐F�ɐ��ߏグ���f�b�L�Ŗ�����\���e�B�A�ɋy���āA�V���ȕ��w���a������܂��r�߂�悤�ɊϏ܂��Ă������Ƃ����ȁv
�u���̖����Ȃ��v�@�u������c�c�v�@���b�h�i���j���A�g���g�����q�Ō��߂Ă����B
�u���[���͏����������̕ϑ��ŁB�P�u�r�P�Ō������ď������������̑���Ɠ����B�����ĂȂ���Ȃ�N���o�Ă������B����ȍ~�̃T�C�h�{�[�h�͂Ȃ��B�����z�����Ȃ��B�G���g���[�͍ő�ł��T�l�B�T�l�����邩�A����܂łɐ킦�������Ȃ��Ȃ�����I�����B�~�[�e�B���O�^�C���͂P�����B���S�����B���ԂƂ���������ē����₵�Ȃ��B�V�т�������ȁv
�u�����̋��ł���Ă��炨���B���܂������ɐ��������w�I��@�������Ă��v
�i�S�R�������낭�Ȃ��B���������B���}���~������݂�Ȃ��������j
�u�N����ł�H�@�����������̗��ꂩ�炷��ƁA����̓��X�g���ȁv
�u�ǂ������Ă�������B�����Ō��߂�Ƃ��ł�����Ȃ��́H�v
�@ �f���G�����b�h�i���j�ƃf���G���u���[�i���j���ۋC�ȉ�b�𑱂��Ă���B���I�s��������ɂ��ւ�炸�A�����ɂ͂����̗]�T���݂ĂƂ��B���B���̗]�T�������܂ł������B
�u���̂��v�@�u�ȂɁH�@������̃f�[�g�̂��U���H�@�܂������˃z���g�B�S�R�������v
�u��������Ȃ��āA���������A�����Վ����ĂȂ����ǁv�@�u�}�W�H�v�@�u�}�W�H�v
�i�}�W�H�@�Ȃɂ���ǂ�ȋ~����H�@�s�n������̎g���t�H�j
�u�Ȃ�ł��̘b�ɂ̂����̂��T�O�O�����ȓ��ŏ����āB�搶�{��Ȃ�����v
�@�ӂ�����u���[�i���j�ɑ��C�G���[�i���j�́A�j���w�ł����Ȃ��瓚����B
�u����A���ɗ���Ƃ��Ď��������A��̂��_�����Ȃ��āB�ǂ�����B���߂�v
�@�f�ō����Ă����B���܂�ɑf���ڋ������āA�~�B�����l���Ȃ���Ă������낤�B
�u�����B�����A�X�̑O�Ȃ���A�����̓X���Ɍ����Վ�������Ȃ��́v
�@�u���[�i���j�̒�ĂɃ~�B�̓R�N�R�N�ƃL�c�c�L�̂悤���������B�ǂ����Ďv�����Ȃ������̂��B�����̓J�[�h�V���b�v�̗��B�J�[�h�V���b�v�ŋN�������������Ȃ�J�[�h�V���b�v�̓X���ɏ����Ă��炦�����B�����ɓ���Z���Ă�l�B�������N�����͓̂X�������č��锤�B
�u����A����͂ǂ����ȁB�����������̗��Ɍ����Ă�A���c�̃J�[�h�V���b�v�̓X���͏�A�ɊÂ��B����͂����܂ʼn\�Ȃ��A �w�w�u���Y�A�b�p�[�x �̌��X���Ƃ����̂́A���͇��V�����Ȃ�댯�l�����ĉ\������B����܉I舂ɂ��Ȃ����������Ǝv�����v
�u�V���B���������Ε��������Ƃ��邩���B�Q�O���̃f���G���V���b�v��X�ɒǂ����ݕ\�̐��E��������A���ł͒n�������̈ł̒��ɐ�������ƌ����錈���̖����B�����Ӗ���
�@�~�B�́A���̃J�[�h�V���b�v�ɂ͂����Q�x�Ɨ��Ȃ����ӂ��ł߂�B
�u���傤���Ȃ����ꂪ�S�A�����邩�炨�܂��c�c�v �ƃ��b�h�i���j�B�@
�u���傤���Ȃ��B���ꂪ�T�A�����Ă������c�c�v �ƃu���[�i���j�B
�u���A�������B�˂��M���A�M���̌����Ց݂��Ă���Ȃ��H�v
�u���I�H�v�@�Ȃɂ������������悤�Ɏv����B
�@�^���ɍl���悤�B���l�Ɏ����̌����Ղ�G����Ȃ�Č����Ƃ����̂��o���_�Ƃ��Ă������B�ߋ��`�B�����Ɛ[���Șb�ɂȂ��Ă���B�����~�B�������Ղ�݂��Ȃ��̂������ŕ����Ă��܂�����H�@�����B�����������̂��B�ň��A�Â��n�����ɕ����߂��Ĕp���������O�̎c�т݂����ȃJ�[�h�����Ă����A���������f�b�L��g�ݏグ�Ắ@�u����Ȏ����Ō������ł��邩�v�@�ƂԂ��܂����A������J��Ԃ����ɓ������������Ȃ��ās�c�C�X�^�[�t�P���x�����Ă��炤���߂ɂQ�S���ԂԂ��ʂ��Łc�c
�i����Ȃ̂��āc�c�����j
�u����A�g���Ă��������B�M���ɂȂ�c�c�����܂��v
�u���肪�ƁB�厖�ɂ��邩��B���ꂶ�Ⴀ�܂���n�߂ɁA��������ׂɐF�X�撣��Ȃ��ƂˁB���������f�b�L�\���Ƃ��M�邩�炿����Ƒ҂��ĂāB���Ɖ�������H�v
�u�Q���v�@�u�]�T�v
�i���܁A������ƂƂ�ł��Ȃ����ƌ������B�l�̃f�b�L�Ȃ̂Ɂj
�uAMP-24�^(�p���[��)�B���X��������g���Ă�ˁB�����ł��傱��v
�u���H�@�����c�c�v
�u���炨�炱�̃`�����h���l�����肵�Ă�邺�B�������Əo�ė��₪��I�v
�u�������B�Ԃɍ���Ȃ���Ȃ�f���G���u���[����ɍs�������H�v
�u���v�B�ł����B���Ⴀ�����Ă���B������낵���ˁB���`���Ɩ��O�́c�c�v
�u�~�B�ł��v
�u���������A�~�B�v
�@�~�B�͓��S�V���Ă����B�{���ɂł���̂��낤���B���l�̌����Ղɂ͕Ȃ�����B���l�̃f�b�L�ɂ��Ȃ�����B�Ȃ̂ɁH�@�S�O���̃J�[�h���j�b�g�A���̑S�Ă��ł���Ƃ����̂��낤���B���̂ڂ낳�Ƃ͗�����(�{���ɂڂ낢�I)�A���ȗ����������������B�t�B�[���h��A�Q�l�̌����҂���������悤�Ɏ��������A�����č\����B�C�G���[�i���j�͍������E���̑O�Ɍy���킹��悤�ɒu���ĕG���Ȃ��A���𗎂Ƃ��Ęr�������B�~�B�͔ޏ��́A�v���|�[�V�����̂Ƃꂽ�̂��ɂ����ŋC�Â��B�v�킸���Ƃ����̔������B�����A�`�����h���͑�����Њd����悤�ȃK�j�҂̑̐��B����͂���ňЈ���������B
�@�����ā\�\
Starting Disc Throwing Standby�\�\
Three�\�\
Two�\�\
One�\�\
Go�I Fight a Technological Card Duel�I
�i�A���_�[�X���[�B�Y��B���̃X���[�C���O�E�t�H�[���c�c�������Y��j
�u���X�v���Ă����ǁv�@���b�h�i���j���������B�@�u�����A������肢�ȁv
�@�~�B�͂��̏u�Ԃ��D���������B���݂��̌����Ղ������Ō��˂��邻�̏u�ԁA���E���h��ς�邱�̏u�ԁc�c�ƁA�~�B�͂��鎖���ɋC�������B�u�����A������肢�ȁv�@�܂�Łc�c�B
�u�Ƃ���Ńf���G�����b�h�i���j�ɕ����������ǂ��v
�u�Ȃf���G���u���[�i���j�v�@�u���A���O�́H�v�@
�i���H�@���ΖʁH�@���̐l�B���Ă݂�ȏ��Ζʓ��m�H�j
�u���[�h���B���܂��́H�v�@�u�e�C���B���Ⴛ���������Ƃł�낵���v
�i���̐l�͌����Ղ��������ɁA���c�̃J�[�h�V���b�v�ɂP�l�ŁH�j
Turn 1
���C�G���[�i���j
�@Hand 6
�@Monster 0
�@Magic�Trap 0
�@Life 8000
���`�����h��
�@Hand 5
�@Monster 0
�@Magic�Trap 0
�@Life 8000
�u��U�A�����������v
�@�������ׂ�K�v���Ȃ����炢�͂�����Ɛ�U�����܂����B�����Ղ��T�[�N���̒��ł܂���Ă���B���邮��B��U�����܂����炢�������Ղ�߂��Ē����͂�̎��ԁB�J�[�h�E�{�b�N�X����J�[�h�E���j�b�g �\�\ �ʏ�̓J�[�h�Ɨ������ �\�\ ���P�������B��U�P�^�[���ڂ̃t�@�[�X�g�A�N�V�����B���̏ꍇ����̓����X�^�[�̏����BSDT�̎����͌y���r�������A�I����肭�g���Č����Ղ����B������Ƃ������͕���C���[�W�B�U���͂P�X�O�O���ւ鉺���ʏ탂���X�^�[�s�f�[�����E�\���W���[�t��ʏ폢���B���ɂ��͎̂����̐ݒu�B�~�B�͂��̉��C�Ȃ�����̂P�P�Ɍ�����Ă����B�����Ղ̎�肪��X�_�炩���B�����Ƃ́A�m���ȈႢ�������Ă����B
�u�^�[���G���h�v
Turn 2
���C�G���[�i���j
�@Hand 4
�@Monster 1�i�s�f�[�����E�\���W���[�t�j
�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j
�@Life 8000
���`�����h��
�@Hand 5
�@Monster 0
�@Magic�Trap 0
�@Life 8000
�u�`�����h���B����ȏ��ɕ������珳�m���Ȃ�����ȁB�����̓��g���b�N�̐ێ���ւ��邼�v
�u�C���Ă��������u���[�g������B�h���[�B�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�������I�v
�@�U���͂P�W�O�O�B���̏u�ԁA�`�����h���͖ܘ_�A���̂S�l���j�����Ə��B���͑̂������Ƃ͂悭���������́B�Z�ɕt�����s���g�Q�ŁA���l�����t���Ȃ��ł̋R�m�B�������A�U���͂Ō����P�X�O�O���ւ�s�f�[�����E�\���W���[�t�̕����͂��ɏ�B�ɂ�������炸�U���\���B���R�Ȃɂ�����ɈႢ�Ȃ��B����������H�@�g���b�v�ŗU���H �R���o�b�g�g���b�N�H�@������B�`�����h���́s�f�[�����E�\���W���[�t�Ɍ����Ęr��L�������������ƁA���_����_�ɏW������B��_�A���_�A���̈�_�Ƃ͏��ɂ��Ă���f���G���I�[�u�B�Ȃɂ����邩�͂��̎��_�ł����܂��ɂ킩��B
�@��������������肾�B
�u�s�R���t���n�Ɏ̂Ĕ�������B��炦�I�@�}�W�b�N�E�J�[�h�s���҂ւ̎�����t�v
�@�`�����h���̏������т��i���m�ɂ͕�т̃C���[�W�Ƃ���ɕt������Ռ��g���j�s�f�[�����E�\���W���[�t�Ɍ������ĂT�`�U�{��яo���M�`�M�`�ɗ��ߎ��B���ߎ���āA�������爬��ׂ��B�����҂͒ʏ�A��������l(������)�ɔ�אg�̂��キ�ĔR��������B�̂ɁA���i�͌���ɑҋ@����B���B�����X�^�[�ɂ��ꂱ�ꖽ�߂��o���������\����Ȃ��B�@�u�܂�Ŗ��@�g���v�@�~�B�͂����v���B
�u�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�Ń_�C���N�g�A�^�b�N�v
�C�G���[�F�U�Q�O�OLP
�`�����h���F�W�O�O�OLP
�@��m�̌�����U�肳��āA�f���G���C�G���[�̐g�ɏՌ��g���q�b�g����B
�u�ǂ��������̌����́B������}�W�b�N�E�g���b�v���P���ݒu�B�^�[���G���h�v
Turn 3
���C�G���[(��)
�@Hand 4
�@Monster 0
�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j
�@Life 6200
���`�����h��
�@Hand 2
�@Monster 1�i�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�j
�@Magic�Trap 1�i�Z�b�g�j
�@Life 8000
�u�t�@�[�X�g�_���[�W�����ꂽ�B���v�c�c�Ȃ�ł��傤���v
�@�v�킸�s�������ɂ���~�B�����A������݂ăe�C�����������B
�u�~�B��������B����Ȃ̂킩�Ȃ��킩��Ȃ��B�����đ��l������B�킩��̂́A���̖��������ꒃ���킢���āA���ꂪ�I������炨���ɗU�����Ă��Ƃ������v
�u�h���[�B�s������m �u���C�J�[�t�������B���ꂶ�Ⴀ�ڂ��ڂ����������v
������m �u���C�J�[�i���ʃ����X�^�[�j
���S/�ő���/���@�g����/�U1600/��1000
���̃J�[�h�������ɐ��������ꍇ�ɔ�������B���̃J�[�h�ɖ��̓J�E���^�[���P�u���i�ő�P�܂Łj�B���̃J�[�h�̍U���͂́A���̃J�[�h�̖��̓J�E���^�[�̐��~�R�O�O�A�b�v����B���̃J�[�h�̖��̓J�E���^�[���P��菜���A�t�B�[���h�̖��@�E㩃J�[�h�P����ΏۂƂ��Ĕ����ł���B���̖��@�E㩃J�[�h��j��B
�@�s�v�c�������B�ޏ��� "�h���[" �ƌ������u�ԁA�������s���������Ă����B
�u�s������m �u���C�J�[�t�H�@�J�E���^�[���悹�āc�c��菜�����Ă��H�v
�@�s�G�ɏ��`�����h���B�֖҂Ȃ�ނ́A������m��O�ɂ��Ă����܂Ȃ��B
�u������ȁv�@�ƃ��[�h�B�u�����A������v�@�ƃe�C���B
�u����c�c�v�@�~�B�͍l�����B���̈Ӗ����B
�i���O�Ƀ}�W�b�N�E�g���b�v��j��\�͂��g���ƍU���͂��P�U�O�O�܂ŗ�����B��������ƃ_�[�N�\�[�h�͂����|���Ȃ��B�_�[�N�\�[�h��|���Ă���\�͂��g���P���łQ���̃J�[�h��j�����ƂɂȂ�B�����ǁA��������ƃg���b�v���|���B�ǂ�����H�@���̐l�͂ǂ�����́H�j
�@�~�B�̒��œ��������܂����ɁA�C�G���[�i���j�͑I�����I���Ă����B
�u�J�E���^�[�͏����Ȃ��B�o�g���t�F�C�Y�ֈڍs�B�s������m �u���C�J�[�t�A�����v
�@�����X�^�[���m�̃o�g���B���݂��������������ғ��m�B�����͈�u�\�\�i���I�j
�u�������悤�����܂����ǂ��]��ł����܂��̕������B�s�Q�b�g���C�h�I�t���B��n�̃��j�I�������X�^�[�s�R���t���s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�ɑ����B���ꂪ����G�n��O���b�N�^�E���̃��j�I���̒��ł��ŋ����ւ鉴�̃��j�I���f�b�L���I�v
�Ŗ��E�̐�m���� �_�[�N�\�[�h�i�ʏ탂���X�^�[�j
���S/�ő���/��m��/�U1800/��1500
�h���S���𑀂�ƌ����Ă���Ŗ��E�̐�m�B���ȃp���[�Ŏa�肩����U���͂����܂����B
�R���i���j�I�������X�^�[�j
���T/�ő���/�h���S����/�U2000/��1500
�P�^�[���ɂP�x���������̃��C���t�F�C�Y�ɑ����J�[�h�����Ƃ��Ď����́u�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�v�ɑ����A�܂��͑������������ĕ\���U���\���œ��ꏢ�����鎖���ł���B���̌��ʂő����J�[�h�ɂȂ��Ă��鎞�̂݁A���������X�^�[�̍U���́E����͂͂X�O�O�|�C���g�A�b�v����B������Ԃ̂��̃J�[�h���тɕ����鎖�ŁA���������X�^�[�͂��̃^�[������v���C���[�ɒ��ڍU�����ł���B�i�P�̂̃����X�^�[�������ł��郆�j�I���͂P���܂ŁB���������X�^�[���퓬�ɂ���Ĕj���ꍇ�́A����ɂ��̃J�[�h��j��B�j
�@�������ꂽ�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�E�\�[�h�t�̍U���͂͂Q�V�O�O�܂ŏ㏸����B�@�u�������v�@�����`�����h�������Ƃ��A�u���C�J�[�̃V���[�g�A�b�p�[���_�[�N�\�[�h�̎�_�ł���{�ɃN���[���q�b�g���Ă����B�@�u�T�O�O���C�t�x�����Ĕ����B�s�c�C�X�^�[�t�v�@�ޏ��͂����������B
�C�G���[�F�T�V�O�OLP
�`�����h���F�V�X�O�OLP
�u�^�̂����z�߁v�@�u�s�c�C�X�^�[�t�������ł����̂͂��������B�P���Z�b�g���ă^�[���G���h�v
�u�������̒��x�Œ��q�ɂ̂�Ȃ�B�h���[�B���w�I�Ƀ����X�^�[���Z�b�g�B�������B���y���݂͂��ꂩ�炾���B�����ɓM����A�u���[�g�����w�ɂȁI�v
�u�Ȃ��Ȃ����[�h�A���͂ǂ��v���H�v
�u�r���ǂ������Ȃ̂͂��̃u���[�g���ƁA�����̗��T�C�h�ɗ����Ă�z�炾�ȁv
�@���[�h���w�E�����̂́A���F�̔������� �w�Z�����X�x �ƖV�哪�� �w�S�[�h���x
�u�����B���̏����͊ᒆ�ɂȂ����Ă��ƁH�v�@�u���̂܂܂��������炭�ȁv
�u���̂܂܂����ˁB�����ǂ��Ȃ邩�v�@�e�C���͊܂݂���������悤�əꂢ���B
Turn 5
���C�G���[�i���j
�@Hand 2
�@Monster 1�i�s������m �u���C�J�[�t�j
�@Magic�Trap 2�i�Z�b�g�^�Z�b�g�j
�@Life 5700
���`�����h��
�@Hand 2
�@Monster 1�i�Z�b�g�j
�@Magic�Trap 0
�@Life 7900
�u�j���̂͋�肾���痤�ōU�߂��B�h���[�B��D����c�c�������I�@�s�h�������C�h�t�v
�@�����Ղ����邭��Ɖ�]���Ȃ���t�B�[���h�̍��[�ɒ��ՁB�����ɐ����B�o�Ă����̂̓~�B�̃f�b�L�̃}�X�R�b�g�s�h�������C�h�t�B�~�B�H�� �w�����������킢���̂��~�����x
�u�o�g���t�F�C�Y�A�s�h�������C�h�t�ōU���B���ʂ͒m���Ă�H�@�ǂ�j��v
�u���o�[�X���ʂ͔������邾��B�s�ł̉��ʁt�̌��ʔ����B�s�Q�b�g���C�h�I�t���n���h�Ɂv
�u�s�Q�b�g���C�h�I�t������B�Ȃ�قǂˁB���͂��������|���Ȃc�c�v
�@�`�����h���̓j�����Ə����B�ނ͗��r�ŁA���͂�傫�������܂킷�B
�u�Ȃ����v�@�u���̎v�킹�Ԃ�ȓ����B�Ȃɂ�_���Ă�H�v
�u�ł邩�v�@�u�`�����h���̕��w���v�@�u�n�܂�ȁB����ł�������܂����v
�u���̃`�����h�����₤�B�Ȃ�łP�̂̃����X�^�[�ɂ������ł��郆�j�I�����P����Ȃ̂��킩�邩�H�@���̕��w���킩�邩�H�@�����A���S���ɗ��ł����ꂽ�ߕs���̂Ȃ����ӎ����v
�u�ł��I�@�`�����h���́y�����̕��w(���j�I���E���^���`���[)�z�v
�u���̃L���B��̓��j�I���w�I�ɋɂ߂��I�v
�u�ʂɉ���2��������n�����ǂ��ɂ���I�@�Q�Ŋ����Ȃ̂��B���̃}�C���K�[V�͌㔼��J�X�N�����_�[��w���ɕt���ăp���[�A�b�v���邪�A�����őS�Ă͊��������B��_������������ȏ㉽���K�v�Ƃ��Ȃ������ȑ��݂ɂȂ����̂��B�킩�������I�@�s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�\�[�h�t�̔w���Ɂs�R���t���h�b�L���O�����Ƃ��A���̕��w�͊��c�c�����I�v
�@�Ō�܂Ō����邱�Ƃ͂Ȃ������B�ʕق����₵���u���C�J�[�̂Ȃ�������M�B���ꂾ���ł͏I���Ȃ��B�ޏ��͉E�G��O�ɓ˂��o���A�E�肪���̍���ʂ�߂��邩�߂��Ȃ����̂Ƃ���܂Őg�̂�P����A��������E��ցA�꒼���ɘr���ӂ�B���o�[�X�J�[�h�����B�s���r���O�f�b�h�̌Ăѐ��t�B�Ώۂ́A�s���҂ւ̎�����t�œ|���ꂽ�s�f�[�����E�\���W���[�t�B
�@�����B�����Ă����̂́s���r���O�f�b�h�̌Ăѐ��t�B���̂Ƃ���O�̃^�[���A�ޏ��ɂ͑I�������������B�s������m �u���C�J�[�t�ŃZ�b�g�������A�s���r���O�f�b�h�̌Ăѐ��t�Łs�f�[�����E�\���W���[�t����ꏢ���A�U���͂P�X�O�O�́s�f�[�����E�\���W���[�t�ōU���͂P�W�O�O�́s�Ŗ��E�̐�m �_�[�N�E�\�[�h�t��|���Ƃ����I���������݂����̂��B�������ޏ��͓ǂ�ł����B�`�����h���������Ă����J�[�h�A���̐��̂��`�F�[���\�ȁs�Q�b�g���C�h�I�t�ł��邱�Ƃ��B�����i�Ɖ������s�R���t��ł�������J�[�h �\�\ �s�c�C�X�^�[�t �\�\�������Ă������Ƃ͋��R�B�������Ă��̗���͕K�R�B�n���h�R�X�g��K�v�Ƃ���s���҂ւ̎�����t���`�����h��������Ƃ������_�ŁA���̗���͕K�R�B�s������m �u���C�J�[�t�̖��̓J�E���^�[�ʂɏ���邱�ƂȂ��U�߂�����A�����A�������̏�ʂŊ�P��������B�u���C�J�[�̈ꌂ�Őg�̂����̎��ɐ܂����`�����h���̕��ɁA�s�f�[�����E�\���W���[�t�̎蓁���˂��h����B
�C�G���[�F�T�V�O�OLP
�`�����h���F�S�P�O�OLP
�u�o�g���t�F�C�Y���ɂ���ܒ���Ɛ�����ނ�B�C���������������Ǝv���v
�@�d���ΉA�{���̍U���Ń_�E����D���B���C�t�����c���Ă͂��������̍��͗�R�B�s������m �u���C�J�[�t�̌����ʼnI舂ɃZ�b�g�͒u���Ȃ��B���������������ƂɂR�̂�����ōU�߂�����f���G���C�G���[�B���̍U�߂͗��̔@���B�܂���S�O���Ȃ��B
�u���̍U�h�A�ǂ�����v�@�������̂̓��[�h�B�������̂̓e�C���B
�u�T�ڂɂ͒����t�����炢���C���ˁB�o���郂����Ђ��[����o���܂����Ă�B�P�ɖ����ꒃ����Ă�̂��A�S�̏����Ȃ�ė���킯�Ȃ�������ă^�J�������Ă�̂��B��҂��ȁB�s������m �u���C�J�[�t��u���Ă������㩂͕����������R�B����Ƃ���Ζ��@�c�c�v
�u�����́s���҂ւ̎�����t������ɂ����B�I�������N���Ă�v
�i�I�����H�@���̐l�B�A�Ȃɂ��Ă�낤�c�c�j
�@�Q�l�̉�b�ɕ������𗧂Ă�T��A�C�G���[�i���j���₽���������B
�u���Ă�Ƃ͎v�����Ǘ����Ȃ��Ă����B���͂킽���̓G����Ȃ��v
�@�Ԏ����Ȃ��B�`�����h���̓s�N���Ƃ������Ȃ������B���������B�F�������v�����B�����̂��������ƌ����Ă��|��Ă鎞�Ԃ���������B�C�G���[�i���j�͈ٕρA���邢�͈�a���ɋC�������B�u���[�g����h���܂�ŏł��Ă��Ȃ��B���͍��͗�R���Ƃ����̂ɁB�Ȃ��H
�u�u���[�g������A�`�����h�����|��܂����B���w�I���߂������v
�u�S�[�h���A�`�����h���͓|�ꂽ�B�������A����͔���ꖇ�ɉ߂��Ȃ��̂��v
�@���������āA�Ƃ����\������������������Ȃ��B�u���[�g���������J�����̂��B
�u�`�����h����B���͐V���Ȃ镶�w�����܂��Ɏ�����B�����A���w�I���n���猾���A���܂��̃��j�I���ƃ����X�^�[�̊W�͉��̌��t�Ƃ��܂��̊W�ɓ������B���܂��͎���Ă���B����n�ɒu���ꂽ�̂́A���̕��w�̂ق�̌��Ђɉ߂��Ȃ��B�����������B�����ĉH�����������v
�u��������A�`�����h���̗l�q�����������v�@�u�ȂB���̕s�C���ȕ��͋C�v
�@���̂̂悤�ɂȂ��Ă����`�����h�������������Ɠ����o���A���̏u�Ԓ��ˋN�����B�������ꂽ��ꂩ��]���r�������o�ł邩�̂悤�ɁA�`�����h�����ĂуC�G���[�i���j�ɔ���B
�u�J�[�J�J�J�J�b�I�@���肪�Ƃ���B���C�t�͌�ނ��������w�I�ɂ͂ނ���O�i�����v
�u�����A�����������e�C�������Ă���v�@�u�ǂ���炱��Ŗ{�̔������Ă킯���v�@�u����ȁI�v
�u�J�[�J�J�J�J�b�I�@���܂����|�����͉̂����Z���Ă������w(���j�I��)�ɉ߂��Ȃ��B���̉����g�͕����Ƃꂽ�B�����āA�u���[�g�����������V���Ȃ镶�w(���j�I��)���������������B�������A�u���[�g�����w��������肨��͕s���g�Ȃ̂��I�@�J�[�J�b�J�b�J�b�I�@���ꂱ�����I�v
�@���w�I�����h���B���܂��͂��������܂����B
�y����Ȍ��������͎��ʂ̖��ʂ��z
�����ƌ����܂��B�����ǗL���������܂����B���ꂩ��������D������������̍K���ł��B
�������ł��n�j�^�u�ǂv�u�ʔ��������v���A�ꌾ����ł��A������ɂ͋��에�����鏀�����o���Ă���܂��B
���\���@�����b