【ROUND4】
新堂翔(2勝)VSエリザべート(1勝)
| 2週目 |
| ショウ:ハンド5/モンスター1(セット)/スペル0 |
| エリー:ハンド4/モンスター1(セット)/スペル1(セット) |
「ドロー! リバース! 《X・E・N・O》の効果を発動」
(そんな……いきなりそんなカード。対応が間に合わない)
エリー、初手の反応が遅れる。ショウ、それを見逃さない。
「初手が《X・E・N・O》。んなカード使うなよな。この大一番で……」
「伏せカードもなし。相手が攻撃してこないっていうかできないって思ってるのかなあの人」
「だろうな。おそらく、新堂の2戦目と3戦目は基本コンセプトの類似する別のデッキだろう。しかし1戦目は基本コンセプトの時点でエリーが先止めしちまった。だから枝葉の部分がわからない。それは危険を冒さず完勝するという見地からすれば完璧な決闘だったが、その強さが裏目に出ている。今重要なのはその枝葉だ。枝葉がみえなければ全体のコンセプトの微妙な違いもみえてこない。そして1戦目のデッキが謎になることで、新堂は行動の自由を得た。仮に、1、3、4が同じデッキだとしても、エリーにそれを感知する術はない。もう後の祭りだ。第5戦目に再度そのデッキが来る可能性をも考慮しなければならない、が、逆にエリーは、【バニシング・クロック・パーミッション】をここで使えない。ザ・ワールド以外に攻撃手段を持たない【ワールド・ロック】を使うしかない」
「ここで使ったら第5戦の先手番に手の内丸ばれの【ワールド・ロック】だけが残る。だが得意の先手番にはファーストデッキを残したいだろう。しかしそうなると結局4戦目のデッキは自動的に決まる。こう考えていくと、エリーは元々5戦マジで闘う気はなかったのかもな。3連勝か、あるいは1戦ぐらいはくれてやって3−1でフィニッシュするつもりだったのかもしれない。いずれにせよ先手を取って勝てるところできちっと勝ちきるための布陣。しかし、もうここで1戦くれてやるわけにはいかない。なんせくれてやったらそれで試合終了だからな」
「相手にプレッシャーをかけて寄せていくための手練手管が、逆に自分の行動の自由を奪ってるのか。セカンドデッキはリードを前提とした戦略。だが、現実は後手に回っている。エリーは未だ新堂の動きを読み切れていない。異変には気づいたろうが、対応がまるでできてない」
「セットモンスターのコントロールを得る。《墓守の偵察者》か。面倒な壁だが奪ってしまえばどうということもない。この2体のモンスターを生贄に捧げ、《E−HERO マリシャス・エッジ》を召喚」
ショウ:8000LP
エリー:5400LP
気前よく2体の生贄を貪り登場した、鋭利なエッジがエリーを切り裂く。
(三連続……違う、四連続。同じタイプ。同じ攻め。だけど違う!)
力と技の風車が回り、父と母が妹にツインシュートを決めるかのような猛攻。
(ショウが見えない。私の中のショウの「像」が、どんどんぶれて膨張していく)
「……ターンエンド」 翔は、3戦目までとは違い、黙々と攻め立てていた。
「私のターン、ドロー……です。私は、私は……《ダンディライオン》を手札コストに《ライトニング・ボルテックス》を発動! 《E−HERO マリシャス・エッジ》を破壊し、トークンを2体展開……」
(わからないから、わからないから、守るしかない。とにかく、守るしか……)
「僕の勘定でいくと《X・E・N・O》が《墓守の偵察者》と実質1:1交換。その後実質的見地からは手札損失なしでエッジ召喚。これに《ライトニング・ボルテックス》は下策。本来ならもっと引きつけるべきだが、押しこんでいいのか引きつけていいのか判断がつかなくなっている。相手との距離が見えなければ正確な打ち落としも影を潜めざるをえない。苦し紛れに綿毛を撒いたようだが、連続攻撃と貫通攻撃を得意とする【マリシャス・ビート】相手にはほとんど何の時間稼ぎにもならないだろう」
| 3週目 |
| ショウ:ハンド5/モンスター0/スペル0/ライフ8000 |
| エリー:ハンド3/モンスター2(トークン/トークン)/スペル1(セット)/ライフ5400 |
(全体除去を序盤から使うというのは追いつめられている証拠だ。2〜3揺さぶりつつ、正面突破を図るのがベスト、か。いい具合だ。この試合、いい具合だ。いい具合、だよな)
順調。まさに順調。それは、気味が悪いぐらいの順調具合だった。
「ドロー……手札から《E−HERO ヘル・ゲイナー》を召喚。トークンを攻撃する」
(トークンはあと1体残っている。手札を温存しながら守る? でもそれだと……)
エリーは迷っていた。【ぶれる悪意】にしてやられた、あの頃の残像に包まれて。
「……ターンエンド。(これでいい。これでいいんだ。このまま攻めれば……)」
(ショウの手の内は十分見た。だけど惑わされる。ショウは、ショウはどこ?)
「私のターン、ドロー……カードを1枚伏せる。ターンエンド……です」
| 4週目 |
| ショウ:ハンド5/モンスター0/スペル0/ライフ8000 |
| エリー:ハンド3/モンスター1(トークン)/スペル1(セット)/ライフ8000 |
(ショウが動く瞬間をもう一度見切る。動いた瞬間がチャンス。いつ動く……)
「俺のターン、ドロー……特にどうということもない。が、攻撃は続行する」
直線攻撃。しかし2戦目とは違い、翔は既に崖っぷちを脱していた。
(動いて……こない。ショウがわからなくなっていく。私は、どうすれば?)
既に道は開けていた。翔は振り返らない。ひたすらに、殴りつけていく。
「手札から《E・HERO エアーマン》を召喚。デッキから《E−HERO マリシャス・エッジ》を手札に引き入れ、バトルを仕掛ける。《E−HERO ヘル・ゲイナー》でトークンを攻撃」
(これを全部通したら残りライフ3600。次のターン壁を出せばゲイナーを未来に飛ばしつつエッジ、壁を出さなければそのまま攻撃されエッジは温存。向こうに伏せ除去を引かれたら……)
「リバース、《聖なるバリア−ミラーフォース−》を発動……」
「(焦ったか。手が早過ぎる。)かまわない。ターンエンドだ」
「この局面、流石にプレッシャーのかけ方がうまいな新堂は。優位に立ってからは、必要最小限の動きで厳しく攻め立てている。これではエリーの方が、しびれを切らして大駒を切っちまう。根幹部分でのビートだが、枝の分かれは二通り、エリーに迷いをもたらす。だが一方、新堂はペースを掴んでいる。相手の手の内も把握してるしな」
「後半に突入したにも関わらず、デッキを特定されていないのは大きい。実質80枚を相手にしているようなもの。しかも奇策に走らない分、誤差が見えづらい。だけど誤差は存在する。優位に立った以上は、策を見せるより策をチラつかせる方が効果的、ということか。これでは巻き返しのためのチャンスをうかがいづらい」
「なんだ? エリーの動きが止まった? どんどん鈍くなっている」
エリーはカードを引いたまま動きを止める。呆然として動かない。
「う……」 まるで何をすればいいのかわからなくなったかのように。
「どうしたんだ? おいディムズディル。おまえならわかるだろ。どうしたんだ?」
ディムズディルはこの試合あまり喋らない。彼は、遠くを眺めていた。
「“わかる人”扱いされるのは心外だが……エリーには、“芯”がないんだ」
「あの生娘には中身がないのさ」
「“中身”がないだと? これは異なことを言うな『R』。あれ程の才をさして……」
ジンはエリーを擁護する。しかしローマは、「ガン!」と拳を壁に打ち付ける。
「何も成長しちゃいない。昔、あの生娘の頭を軽くなでてやったときからな」
「……」 「“貴方のようには決してなりたくありません”だとさ。笑えるぜ」
「それは、いつ、どこでの話だ? いったいどういう接点だ?」
「知りたいか? 簡単な話だ。説明してやれよ、ゴライアス」
ローマとジンの後ろには、いつの間にか紳士が立っていた。
(ゴライアス。裏コナミ最古参の1人か。相変わらず怪しい男だ)
「かつて、世界最強の決闘者がヨーロッパに住んでいました……こんな語りだしでよろしいでしょうか」
「ああ、つづけてくれ」 ローマとゴライアスは確実に何かを知っていた。それは、少し昔の話である。
「その決闘者は実に強い決闘者でした。その血は、当然のように娘の代にも受け継がれていきました。母親もよかったのでしょうか。才能の芽は確実に育っていたのです。娘の思惑とは関係なしに」
(世界最強の決闘者……娘の代……なんだ? この胸騒ぎは。俺の知らない、裏コナミの秘密?)
「ある時その決闘者は言いました。“娘には、決闘者になってほしくない”と。そのとき、聞き役を務めていた当時の裏決闘者達には何が何やら全くわかりませんでした。しかしその謎はあっさり解けるのです。娘は泣いて帰ってきました。なぜでしょう。娘はたった一つのことをしただけなのです。“勝負”、なんと不幸でなんと笑える話でしょうか。父親から与えられた、勝負師としての過剰な器と、母親から譲り受けた気弱で聡明な性格は、何も知らぬ少女から友達を、笑顔を奪っていったのです。ああ、悲劇」
「演出過剰だゴライアス。馬鹿が馬鹿だったってだけの話。俺は気を利かして“慰めて”やったんだぜ。そんな連中はさっさとふり捨てればいいとな。だがあいつは逃げだした」
| 5週目 |
| ショウ:ハンド5/モンスター0/スペル1(セット)/ライフ8000 |
| エリー:ハンド0/モンスター2(セット/トークン)/スペル3(セット/セット/《レベル制限B地区》)/ライフ5400 |
「ドロー……手札から《サイクロン》を発動。《レベル制限B地区》を破壊する。《E−HERO ヘル・ブラット》を特殊召喚。そして! 手札から《E−HERO マリシャス・エッジ》を生贄召喚。貫通攻撃を行う!」
「うっ、ならリバース・トラップ《グラヴィティ・バインド−超重力の網−》を発動」
「わかった。エンドフェイズ。デッキからカードを1枚引いてターンエンド」
「ドロー……《デス・ラクーダ》を反転召喚。効果によりデッキから1枚ドロー。そして《デス・ラクーダ》をセット状態に戻す。私はこれでターンエンド……します」
| 6週目 |
| ショウ:ハンド4/モンスター1(《E−HERO マリシャス・エッジ》)/スペル1(セット)/ライフ8000 |
| エリー:ハンド2/モンスター2(セット/トークン)/スペル2(セット/《グラヴィティ・バインド−超重力の網−》)/ライフ5400 |
「ドロー……ターンエンド」 翔は焦らない。冷静に手を揃えていく。死刑宣告を下すために。
「ドロー。《デス・ラクーダ》の効果を発動。デッキから1枚ドロー。カードを1枚セット。ターンエンド」
膠着は守備型のエリーの望むところの筈。しかし、エリーにはビジョンがみえない。勝てる未来が浮かばない。蛇に睨まれた蛙のように、気押され続けるのみだった。
「くぅぅぅぅぅうう! 煮え切らん! ベルク! 今すぐあそこへ行くぞ!」
「誰が行くか。1人で向こうの壁につっこんで1人で死ね」
「なんと忌々しい。こんなもので……こんなもので……」
(うるっせえなあ。寝れないだろうが。うるっせえなあ)
「なぜだベルク。なぜあの場所に我がいないのだ!」
「そういう組み合わせだからだろ」 「身も蓋もないことを言うな!」
「相手をみることに長けた女は、そして“それ”をプレッシャーとして相手に伝える才能をもった女は、自分の勝負中の“否定”により相手を失うことを恐れた。相手を失うことを恐れた女は相手の顔を更に窺うようになった。相手相手相手、そこに中身はない。そんなやつを強者としてアリにしている、決闘界の情けないこと情けないこと」
「成程。合点がいった。そんな人間が一端相手を見損なえば、そこには何も残らない。エリーが動けぬわけだ。優勢を築いた新堂は黙々と攻め続けている。成す術なし、か。だが、一つ解せんな。それほどまでに“否定”で相手を失うのが怖いのならば、闘わなければいい。あるいは、負ければいいだけの話だ。そうだろう、ローマ」
「倒錯した連中さ。バスター家の人間が背負う余計なもんは、俺には目障り過ぎる」
「バスター!? おまえ、今なんと言った! まさか、エリザベートとは……」
ローマはニヤリと笑った。そして、知らなかった人間を嘲笑うかのように言った。
「あいつのフルネームはエリザベート=バスター。おまえが今想像した通りだよ」
「裏コナミの創始者にして最強の決闘者、バスタートーナメント=バスター=アサルトバスター卿の……」
「一人娘だ。だから言ったろ? 付き合いがあるって。どうした? カラスが鉄壁を食らったような顔だな」
「曰く、霊長類最強の決闘者。曰く、決闘豪帝(バスター・エンペラー)。その一人娘だというのか」
「だから血はいいわけだ。むしろ良過ぎるといってもいい。なにせ“あの”“バスター”だ。だがあいつは、あの生娘は帝王の道を歩くことを恐れた。本能と感情の間をいったりきたりしているのさ」
「人一番感知力の高いエリーは、自分のデュエルに向けられる嫌悪の念に敏感過ぎた、か」
「そして逃げ出し、戻ってきた。だが、何一つ変わっちゃいない。誤魔化すのが上手くなっただけだ」
「エリーは、決闘者に憧れているんだ。正確に言えば、憧れしかないんだ」
ディムズディルは静かに語りだした。いつもとは違い、少しトーンが低かった。
「かもな。正確には、おまえと、本人は絶対認めないだろうが、ローマに憧れている」
「受け入れる能力に長けたエリーは、しかしそれ故に相手の顔色を窺って生きるようになった。そして今のエリーは、相手の顔色をうかがいながら決闘者になろうとしている。いや、本人からすれば、決闘者でいつづけようとしている。合わせようとしているんだ。自分の居場所を、自分がいていい隙間を探そうとしているんだ。相手にも合わせつつ、デッキを毎回のように変えて他人を飽きさせないように、かつ、相手の長所をうまくひきこんで流れの中で勝利をつかむ。だが、そんなものはまやかしだ! 自己矛盾に向き合っていないだけだ。取り繕うだけがデュエルなら、そんなものは最初から必要ない。土俵に上がることすら!」
「ああ、おまえに会うまではそんな感じだったよ。土俵にすらあがろうとしなかった」
かつてエリーは、己の能力を最大限生かし、誰からも好かれる美女だった。彼女は勝負の場から離れることで、人を遠ざける忌まわしい本能を、人を近付ける為の武器としたのだ。しかし……。
「僕は傍観者を決め込む彼女の本質を引きずり出しただけだ。エリーの中の決闘者とは“勝利を目指す者”。エリーにとって、決闘者であるためには、嫌われないように、かつ、勝利を目指さねばならない」
隠しきれないもの。憧れを嘘にしないためには、今日のように全てをみせなければならないときもある。しかし、それはそもそも真実なのだろうか。そこに、本物を突きつける意思はない。
「相手依存、結局はそう言いたいんだろ。ああ、確かにそうだろうさ。そうだろうともよ」
「しかし僕は思う。己の主張をフィールドに賭けれない者が、はたして決闘者といえるのか?」
「きついな。だけどおまえは、あいつを引き込んだんだろ。それがいいと思って」
ディムズディルは遠い目をした。己は聖人君子ではない。そう言っているようだった。
「……僕を買いかぶるなよストラ。僕は単に気に入らなかっただけなんだ。エリーが幸せかどうかなんて最初から度外視している。僕を“いい人”だと一瞬でも思ったのなら君は愚かだ。僕も、そしておそらくローマも、エリーのことが気に食わなかった。絶対に負けたくなかったんだ。それだけの話なんだ。そう、それだけの話さ」
| 7週目 |
| ショウ:ハンド5/モンスター1(《E−HERO マリシャス・エッジ》)/スペル1(セット)/ライフ8000 |
| エリー:ハンド3/モンスター2(セット/トークン)/スペル3(セット/セット/《グラヴィティ・バインド−超重力の網−》)/ライフ5400 |
新堂翔。彼はは感じる。先程まではあった熱が引いているのを感じる。負ける気はしない。だが不思議と、勝つ気もしない。自分が勝利者として腕を持たれる未来はみえる。だがしかし、その壇上にに勝利というものがチャンピオンベルトとして置いてある実感がわいてこない。翔は今、恐ろしく冷静であり、自分でも嫌なくらいに隙のない翔だった。まるで、作業を遂行するかのようにカードを解き放っていく。
「ドロー……終わりだ。《大嵐》を発動。さっさと打ち消せよ。そこのそれ、カウンターだろ」
「カウンタートラップ、《魔宮の賄賂》を発動!」 動きに窮するエリー。しかし、打たざるを得ない。
(わかる。この決闘は俺の勝ちだ。こちらの力を全て絞り出さなくても間違いなく勝てる)
「効果によりドロー……《悪魔の誘惑》第三の効果を発動。弱小トークンのコントロールをこちらに……こいつを生贄に《邪帝ガイウス》を召喚。そしてガイウスの効果により超重力の網を除外」
「リバース! 《奈落の落とし穴》を発動! ガイウスをゲームから除外する」
「何の問題もない。バトルフェイズ、《E−HERO マリシャス・エッジ》で貫通攻撃」
ショウ:8000LP
エリー:3400LP
(残りライフ、問題なく削りきれる。誇ればいい。俺は勝てるんだ)
しかし言葉とは裏腹に、翔は動きを止める。なぜであろうか。
「あれ? 新堂の動きが止まった? あいつ、なにやってんだ?」
(俺は……俺はいったいなんなんだ? そしてアイツは――)
新堂翔、彼は動きを止めた。そして、懐から何かを取り出した。
「ほらよ」 「え?」
ショウはエリーにぽいっとある物を放り投げた。
「これって確か……“スーパーはるか君”、だっけ」
「うちの旗印なんだ、それ」 「旗印?」
「折角決闘者として旗揚げするんなら旗印がいると思ってさ。これだってもんをつくりたくなったんだ。だけどよお。これが全然思いつかないんだよな。カードゲームは万屋っつってもどんなんにすればそれっぽくみえるのか全然アイディアが湧いてこない。頭抱えて……で、こうなった。ひっどいよなあ。我ながら最悪のモデルだ。けどいざつくってみると結構気に入ってるんだそれ。なんか俺らっぽいだろ。見慣れると愛着も湧くぜ、その人形」
翔は何をしようとしているのか。それは、本人にもよくわかっていないこと――
「アンタが何を考えてるかは知らないが、俺はさ。本気でやりあうって言いあった以上はやれること全部やろうと思ったんだ。頭悪そうな意見だが、最高の決闘をやるには最高の決闘者であるべきだと思うんだ。他にも色々あるかもしれないがとりあえずはこれだろ? あんま根拠ないんだけどさ、その最高の決闘者とやらに近づくためには、信念? みたいなものがいるような気がした。だから俺は旗印をつくってこいつに込めた。『カードゲームは万屋』、ありとあらゆるもん取り揃えるだけ取り揃えて最後まで仕事をやり抜く、それが俺の決闘だ。なあ……」
新堂翔は、迷った。自分が今から言おうとしていることに。
「こんなこと試合中に聞くようなこっちゃないんだろうな」
「え?」
「だけど一つ聞かしてくれ。あんたは、なんだ?」
「うぁ……」
突き付けられた質問にエリーは固まる。それが、意味することはなんなのか。
「俺さ。楽しかったんだぜ。そんで嬉しかった。あんたが強かったからだ。俺が言ったとおり、力を温存せず本気で勝負をかけてきてくれた。特に一戦目は震え上がったよ。だってさ。予定より全然ヤバかったんだぜ。一戦目は五分五分くらいでうまく次へつなげようと思ったら生まれて初めてぐらいのぼっこぼこだ」
(ショウは何を言おうとしているんだろう。この局面で、もう試合は終わるのに……)
「あんたのデュエルには押しつぶされるような感覚を味あわされた。“やめたい”“逃げ出したい”そう思わなかったといえば嘘になる。だけど、そんぐらいアンタは強いんだ。超えてやる、そう思った」
ショウの拳は心なしか震えているように見えた。なぜ? それはすぐにわかる。
「殴り続けて、殴り続けて、登り続けて、登り続けて、登り切ったと思ったら見渡す限りなんもなかった。なあ、教えてくれ。あんたは何者だ。そして俺はあんたの何だ! あんたは……あんたは……あんたは壁打ち用の壁か! 俺はあんたの敵にすらなれないのか! 俺じゃ不足だってのか!」
エリザベートの顔が真っ青になるのと、地面にカードが落ちるのはほぼ同時だった。翔は、どうしても言わずにはいられなかった。彼は登頂困難な山を登った。しかしそれだけだった。2人の間には何も通わない。彼が覚えた空虚感は、かつて彼をゲームから最も遠ざけたもの――
「カードから手を離しただと? おいディムズディル……なんか言え。なんでもいいから何か言え!」
ストラに怒声まがいの要求を投げられたディムズディルは、掴まれ乱れた服を直しながら言った。
「デュエルは、デュエルはお互いをぶつけるものだ。決闘とは闘いを決めること。闘いを決めるとは自らの闘い方を、自らの闘い様を、闘いへ向けた意思を、自分で決めることだ。だが……」
「……」 ジンは黙って立っていた。他方ローマは、腹から言葉を絞り出すように語っていた。
「おい天才。おい瀬戸川刃。答えろ。何も主張しない決闘者が勝者なんてものにになれるのか? 勝者になる資格のない者が、敗者になれるのか? あの生娘が勝者にも敗者にもなれないとしたら、その相手は勝者や敗者になれるのか? 決闘者の見た目を真似をすれば、決闘者に憧れれば、相手に気を使えば、それで決闘者になれるのか? 答えろよジン。“勝負”って言葉を生みだした国の生まれの、おまえなら答えられるだろ。勝負ってのは勝者と敗者が生みだす芸術だ。なあ答えろよジン。俺はあと何人くだらない敗者未満を潰し続ければいいんだ? 俺達はあと何回くだらない勝利未満を、決闘者未満をゴミ箱に捨て続ければ気が済むんだ?」
ローマは壁に拳を打ちつけたまま独白した。それはまるで、血を吐くような言葉の繋がりだった。
「その問いに答えるには俺は未熟すぎる。だが、未熟さから生まれるものもあると俺は信じたい」
ジンは眼下に広がるデュエルフィールドを見渡した。そこにいるのは、ショウとエリー。
(私が何かって? 私は何なんだろう。あの頃、ただ楽しくゲームをすることしか考えていなかった私。だけど私がゲームすると嫌われた。みんなが嫌な顔をするのが心の底から嫌だったから、勝負事は避けるようにした。私は顔色を窺うのが上手いみたい。だから嫌われる? だけど自覚してからは、人の顔色を窺うことに長けたお陰で、嫌われることはなくなった。みんなが私を愛してくれる。満足だった。自分から勝負を挑まなくても、世の中のいろいろなものを見れば楽しい……)
(それでいいと思っていた。あの日までは――)
「ダルダル! こっちこっち!」 「そんな急がなくても試合は逃げねーよ」
「逃げたじゃん、決勝以外。なんで私に教えてくれなかったの? ひどい!」
「おまえは大会とかに興味ないんだろ」 「見るのは別。見るのはいいの」
「へーへー。にしても盛り上がってるよなあ。確かに、この規模は今までにないわけだが」
「ダルも出ればよかったのに! そしたらもっと盛りあがったかもしれないじゃん。もったいないよ」
「一応出たんだけどな」 「え?」 「本戦のしょっぱなであっっっさり負けた」 「あ……ごめん……」
「別に気にしちゃいねえよ。そんなことよりあっちを見るんだな。実況がでかいマイクもって立ってるぜ」
「青コーナー……この男が歩くところ決闘の隕石降り注ぐぅ! ディムズディルゥゥゥゥ! ブラックマァァァン! 今シーズンはなんとここまで無敗! 怖いぐらいに絶好調。どこまで連勝記録を伸ばせるか! その異常なまでに冴えたデュエルは今日も観客を失禁させること請け合いだあ! 今大会の戦績は……」
「ほらほら、ディムがきたよ!」 「わかってる。みりゃわかるさ」
「あ、こっちに気づいたみたい! ディムがんばってーっ!」
「めんどうくせーなあ。そんな狂ったように応援しなくてもいいだろうが」
「まったくだ。耳が痛くてしょうがねえ。少し黙ってろ。寝れないだろ」
「おいおい。うるさいのは別にエリーだけのせいでもないだろ、ベルク」
「おい片目。ディムズディルに何があった。あいつ、普通じゃないぜ」
「普通じゃない、か。そうかもな」 「折角の高額賞金がパーだ」
「フォッフォッフォ。雁首そろえてなにをしとるかと思えば……」
「あ、いつかのお爺様。お爺様も来ていらっしゃったんですか?」
「エリザか。そうじゃ。きとったよ。2回戦負けじゃがのお」
「誰に負けたんですか? お爺様が負けるだなんて」
「デッキウォッチャーにも見きれぬものがおったということじゃ。今大会のディムズディルは傍目にも異常に好調のようじゃが、それを止められるとすれば、あいつしかおらんじゃろうて」
「かもな。ま、どうでもいいが」 「あいつか。確かに、そうだろうな」
「それでは赤コーナー……世界で最も気の狂った構築屋の登場だ!」
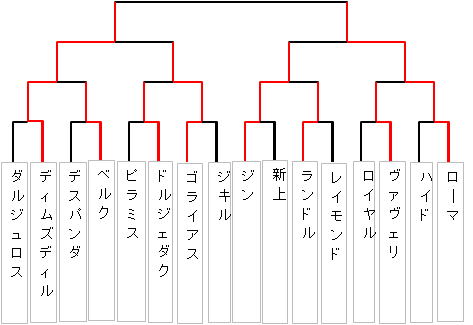
※棄権:バルザック=ローファル(リザーバー:ドルジェダク=ヤマンタカ)
※失格:ベルメッセ=クロークス(リザーバー:ピラミス=マスタバ)
※棄権:ドルジェダク=ヤマンタカ(二回戦。ゴライアスは不戦勝)
「なんであれが事故らない! カモン! ローマ=エスティバーニ! おぉっとのっけからすさまじいまでのブーイングぅ! しかし全くうろたえない! うろたえないぞローマ!むしろ心地よさげに歩いているぅ! 強者はこうあるべきとばかりに悠々と歩いているぅ! 二回戦、準決勝と苦戦しつつも、要所で強烈な一撃を決めて勝ち上がってきたローマ。決勝もまた伝説を築いてしまうのかあ?」
「あの人。昔お父様と一緒に……」
「知っているのか? エリー」
「ほんのちょっとですけど。どういう人なんですか?」
「欧米最強とも噂されている。ディムズディルのチームメイトだ」
「ディムの……」 「恐ろしく強いぜ。あんにゃろうわな」
「お父様の方が強い……と思う。たぶん」
「たぶんかよ……お、向かい合ったな。始まるぞ」
(なんかピリピリしてる。当然? 決勝戦なんだから当然? それにしてもなんか怖い。ディムの表情がどんどん険しくなっていく。闘う人間の眼? ローマは……なんだろう、あれ)
「ローマ、やはり君が上がってきたか」 「だったらどうなんだ?」
(聞こえないけど、ディムの方からなんか話してる? なんだろう……なんだか哀しそうな……あ、ローマの表情が変わった。なんだろう。なんだろう。すごく、怖い)
「僕の最後の試合、君で終われることを感謝する」 「……」
「試合形式はコード1995。それでは決勝戦、はじめぇ!」
(私は見てしまった。あの2人のデュエルを。最初こそゆったりした立ち上がりで、ディムも、そしてローマも観客に応える余裕をもっていた。だけど、闘いが進むにつれ、2人は決闘にのめりこんでいった。私達のことなんか当然眼中になく、2人は延々と闘い続けた。2人はずっと、怖いくらいの気迫で闘っていた。そして私はそれをずっと見ていた。“伝説の一戦”、そう呼ばれる過酷な闘いを私はずっと見ていた。そのとき私は……そうだ。私が、私が欲しかったものは……違う。今の私は最低だ。だって私は――)
「決闘者であることを捨てきれなかった?」
「血が邪魔をしたのさ。そのくせ、孤独な勝利者になることも拒んだ。それがあいつだ」
(勝者は孤独。『脱構築型デッキ構築の申し子』らしい意見だな。昔からこいつは、あまりに奇抜なデッキで勝ち続けたがゆえに孤独だった。誰もあいつをコピーすることはできない。存在自体がオリジナルな決闘者。しかしそれは、羨望と嫉妬と憎悪の対象にしかならない。ローマはそんな中勝ち続けた)
「どんな綺麗事を並べようと、俺達は相手を不幸にするために決闘をやっている。メタゲームとは相手を陥れるための行為だ。ファンデッキ? 相手を喜ばす? はっ、そんなことを言うやつが一番信用できないな。自覚のないエゴイストなど醜悪なだけだ。愛を説きたいなら十字架でもかけな」
(私は真剣デュエルを捨てた。捨てたつもりだった。だけどあの2人の決闘を見て……。私は“綺麗なエリー”で居続けるつもりだった。だけど、だけどディムはそんな私にデュエルを仕掛けてきた)
(私はずっと抑えていた。だけどディムはそれを見抜いていたのかな。私に勝負を挑んできた。それも、本気の勝負を挑んできた。私は、挑発にのっちゃいけないと思いつつ、ふと気がつくと闘っていた。だけどディムは強くて、そして怖くて、私は負け続けた。その時、悔しいと思ってしまった。そして私は徐々に、自分の中の封印を解いていった。嫌われるのは嫌。だけど、だけど私は勝負がしたかった。嬉しがったり、悔しがったりしたかったことを、私は思い出してしまった。勝負の道に入れば私はどこかで“嫌われてきた自分”を曝け出さなくてはならなくなる。それでも、それでも私はもう一度戻ることにした。幸い、私の横にはディムがいる。ディムやダルと一緒なら、強くて、決闘者なみんなと一緒なら……私は、戻ることにした。できると思っていた。だけど違う。私は、まだ何もしていない。何もしていないのに、何かが生まれるわけがない)
「わりぃ、な。俺は何を言ってるんだろうな。くっだらない願望を押しつけて……忘れてくれ」
(違う。違う違う違う違う違う。ショウがいってしまう。違う。そんなのは絶対に違う。だって私は……)
自分が求めていたものはなんだったのだろう。自問自答、いや、最早自問自答など必要なかった。
「お願いです。話し続けてください。1秒でも2秒でも、貴方が私に愛想を尽かしていないなら、いえ、たとえ愛想を尽かしていたとしても、1秒でも2秒でも続けてください」
「言えっていわれてもな。ただ、一人ぼっちになった気がしただけだ」
「一人ぼっち」、そう言われたエリーの心には、どすんと釘が刺さっていた。
(私は言葉が好きだった。デュエルが好きだった。一緒にいられるから。だけど違う。ショウは私に応えてくれた。だけど私は何もしていない。ショウは? ショウはずっとデュエルをし続けてくれた。誰のためかなんてどうでもいい。デュエルし続けてくれた。それは真実。自分の全てを賭けてデュエルを続けてくれた。デュエルをするということは、それ自体が人と人との交わり。じゃあ私は? ショウのことがはっきりみえるかどうかで揺らいでいた。私は、私は……私は自分のことを度外視していつのまにかコミュニケーションの失敗を相手の所為にしていた。私は、私が嫌いな私を相手になすりつけていた――)
エリーは思う。自分が本当に行くべきステージがどこであったのか。エリーは考える。
(受け入れるだけの私。ぶつけなければ……反発をうけずにすむ、私はそう思っていた。私は、私は結局のところ誰よりも自分のことしか考えていない。相手に何もぶつけない私は、相手の心に何も残さない。相手は自分のやったことを反省するぐらいで、私に対しては……。私は自分のデュエルの本質を忌避するあまり、決闘を成立させるもう一つもの、自分のことをおざなりにしていた。相手に配慮すること、それが不要なことだとは思わない。だけど、私達は、少なくともショウは決闘者。闘うためにここにきている。ショウは決闘者としての私を信じて、私を倒すためにあらゆる苦難にぶつかっていった。じゃあ私は? 本当に何も見えていなかったのは誰? 決闘者としての体裁を整えるために、ろくに向き合ってもいない自分をぶつけたのは誰?)
「くだらない話につき合わせて悪かったな。もうじき終わりだ。ターンエンド」
(私にできることはなんだろう。「決闘者だ」なんて言える? 何もない。私の器には何も入っていない)
状況は最悪だった。勝ち目などないように思えた。デュエルはもうすぐ終わる。終わるのだ。
(なにを言っているんだ俺は。もうこの勝負から得られるものはない。いや、勝負から得られるものなど最初からなかったのかもしれない。そんなものは、妄想に過ぎない……)
「私のターンです。デッキから1枚ドロー……(墓地には《墓守の偵察者》《ダンディライオン》《デス・ラクーダ》。向こうのライフは7200。こちらの攻撃力ではとても削りきれるレベルじゃない。私の力じゃ……違う。今必要なのは力じゃない。必要なのは折れない心。私は、この一瞬に全てを捧げる)」
「手札からモンスター・カードを1枚セット。スペルを2枚セットして……」
(空っぽの身体しかないのなら、私はそれを貴方に賭ける。私の覚悟で、貴方に賭ける。どう足掻いたって私には貴方を見つめることぐらいしかできない。だから私は、私が見届けた貴方に賭ける)
エリーが賭けたのは単勝一点張りの馬券のような道筋。癖でもパターンでもなく、単純に、この期に及んでも、たとえ失望を深めるような状況にあったとしても、ショウが力強く、力強く攻め上がってくれる人間であることに、エリーは己の全てをゆだねた。エリーはこのとき自覚する。自分が本質的に「負けたくない」人間であることを自覚する。だからこそ現にここにいるのではないか。その事実は、ある一つの証拠が物語っていた。
(手が震えてる。怖いんだ。そうだ、そうだよね。怖くなきゃダメ。猛獣ひしめく檻の中を遠くから眺め掌握するだけの作業を闘いとは言わない。そして、私が向かうべきは闘いの場。3戦目の、4戦目の辛さも一番奥には負けたくなかったという気持ちが渦を巻いていた。そうだ。私は勝ちたいんだ。私は勝ちたかったんだ。まずはそこから始めなければ駄目だった。私は勝ちたい。だから怖い。怖くていい)
「ターンエンド」
| 8週目 |
| ショウ:ハンド2/モンスター1(《E−HERO マリシャス・エッジ》)/スペル1/ライフ8000 |
| エリー:ハンド1/モンスター1(セット)/スペル2(セット/セット)/ライフ3400 |
(最後もやはり消極策。そうだろうな。そうだろうさ。ならこちらは、積極策を貫きとおす)
翔にできることは最早それだけだった。本気を最後まで貫き通す、それだけが彼の……。
「ドロー……最後まで【マリシャス・ビート】全開だ。《E−HERO ヘル・ゲイナー》を召喚」
【覇王システム】の常套手、《E−HERO ヘル・ゲイナー》召喚。当然、これで終わるわけもなく。
「更に《リビングデッドの呼び声》を発動。墓地から《E−HERO マリシャス・エッジ》を特殊召喚。ヘル・ゲイナーを未来に飛ばして効果発動。マリシャス・エッジAに二回攻撃を付与する」
「エッジが2体。貫通攻撃の三連打!?」 「ミラーフォースはもうない。無傷はありえねえ!」
「無傷どころか、これをまともに食らったらもう終わりですよこんなの。なんて攻め上がりだ!」
(決闘に嘘をつくわけにはいかない。最大の攻撃力で試合を終わらせる。これで最後だ)
新堂翔は現状で最も高い突破力を形成する。しかも手札には《E−HERO ヘル・ブラット》と《邪帝ガイウス》。万が一突破しきれない場合は、これでとどめを刺すという布陣であった。
「バトルフェイズ、マリシャス・エッジAでセットモンスターを攻撃する!」
「(きた! 私は……受けきる) 《素早いモモンガ》。このカードが戦闘によって破壊されると同時に、1000ポイントのライフを回復し、デッキから同名カードを2体展開します」
「構うかよ! 《E−HERO マリシャス・エッジ》の効果を発動。貫通ダメージを与える!」
ショウ:8000LP
エリー:1900LP
「マリシャス・エッジAの攻撃はまだ続く。《素早いモモンガ》Bに貫通攻撃!」
「《素早いモモンガ》の効果発動。1000ポイントのライフを回復」
ショウ:8000LP
エリー:400LP
(ディムと勝負して負け“続けた”理由はここにあった。ディムは私の欠陥をうち砕ける強さを知っていた。そして私はその一ヶ月後ディムに一度だけ勝った。そして一端別れて……あれから私は何も成長していない。無我夢中だったあのときより更に退化している? あのとき、あのとき私はどうやってディムに勝った?)
「モモンガモモンガうるせえな! これで終わりだ。マリシャスエッジBで《素早いモモンガ》に攻撃!」
(自分を自分のものにしようとしないこと。それは結局、デッキに翻弄される惨めさと同じ。だったら!)
「三度目はありません! 《次元幽閉》を発動! マリシャス・エッジBをゲームから除外します」
(なんだ? なぜあいつはエッジAではなくエッジBを除外した? いったい何を……まさか!)
「……ターンエンド」 翔は一瞬何かを感じたもののエンドを宣言。これ以上、何があるというのか。
(なんにもない。ここからは実力さえ路傍の石くらいの価値しかない。それでも、この意思だけは……)
「ドロー。《強制転移》を発動。《E−HERO マリシャス・エッジ》と《素早いモモンガ》のコントロールを交換」
(やっぱりか。こちらの攻撃力を逆手にとった一手。ここにきて味な真似を! だがそれ以上はない!)
エリーのデッキは守備重視。更なるアタッカーの召喚は想定しづらい。現に、エリーはそのまま攻める。
「バトルフェイズ、《E−HERO マリシャス・エッジ》で《素早いモモンガ》を破壊、更にダイレクトアタック」
ショウ:2900LP
エリー:1400LP
「バトルフェイズ終了」 エリーはこれに賭けていた。翔が己を貫くことに賭けていた。
「やってくれるな。だが、これでバトルフェイズ終了ならその攻撃は仇花だ!」
しかし翔の言うとおりこのままではエリーに勝ち目がない。しかし、エリーの思いはまだ終わらない。
(私には何もないから、だから、この大きな流れの中に身を委ねる。信じて委ねることが、私の覚悟)
「手札から《貪欲な壺》を発動。墓地の《墓守の偵察者》《デス・ラクーダ》、そして3枚の《素早いモモンガ》をデッキに戻し……2枚ドロー。《暗黒界の取引》を発動。リバース、《リビングデッドの呼び声》! 墓地の《創造の代行者 ヴィーナス》を特殊召喚。効果発動。1000ライフを支払い《神聖なる球体》2体をデッキから特殊召喚。ヴィーナスと《E−HERO マリシャス・エッジ》を生贄に捧げる!」
「ヴィーナスとエッジの2体を生贄に……まさか! この局面でアレを!?」
Arcana Force XXI - The World
(エッジの連続攻撃で5100点。さらに『世界』の能力で時をとめ、追加の3100点で俺のライフを削りきるというのか。馬鹿な! コインが裏を向ければ、俺の墓地のトップ、《E−HERO マリシャス・エッジ》が手札に戻る。雑魚に貫通攻撃を見舞えば間違いなく俺の勝ちだ。いや、百歩譲ってそれはいい。五分五分のギャンブルには理解の余地がある。おかしいのはそれ以前だ。こんな細い未来のために、あんな、あんなプロセスをたどるのか。あそこで俺が、ちょっとでも気分を変えていたらどうするつもりだったんだ。それに、あいつのドローだって、コインだって……)
事実、どうすることもできないだろう。しかしそれでもエリーは薄氷の上を歩いた。闘い続けるために。
「今の私には、今まで見てきた記憶はあっても確証はない。これは相手依存な、か弱い闘い方かもしれません。ですが私は今度こそ貴方を信じます。貴方の強さを、前に進む意思を信じるからこそ私を委ねます。依るのではなく委ねる……貴方を信じるということが、同時に自分を信じるということ。それが私の決めた戦い方、私の“賭け金”です……今、私は怖い。だけど、怖いということは闘っているということ。私は……闘います」
エリーはコインを投げた。そしてその軌道を見守った。コインは……表だった。
「エンドフェイズ、ザ・ワールドの効果発動! 貴方のターンを『否認』します」
「万屋側の人間としては『おっかねえなあ』とでも言えばいいんかな。そういや俺と闘ったときもバクチみたいな闘い方をしていたっけ。だが、今はもっとおっかねえ。“みたいな”すら下につかねえ。俺がエリーと闘ったとき、俺はあの娘のスタイルを知った。だが、こいつはもうスタイルじゃない。自分を切り出すような決闘。ショウ、おまえがみようとしたのはこれだろ? “決闘者”が顔を出してるぜ。一番おっかなくて、一番逃げ出したくなる場面でだ。そこで踏み込むのもまた決闘者ってか? いってこいよ、うちのバカ野郎」
「奇跡、だよな」 「はい、奇跡です」 「まぐれ、だよな」 「はい、まぐれです」
翔は一瞬呆然とした。だがしかし、そこにあるものが、今はっきりとみえていた。
「ここにあるのは、おまえの意思か?」 「はい。それだけは……譲れません」
「はっ……はっは……ははははは! いいじゃないか。だったら! 喜んでサレンダーしてやる」
そう言い放つと翔は反転した。翔だけじゃない。エリーも反転した。そして、2人は走った。
「成程。流石に二度目の“まさか”はないでしょうからねえ。ここで流れを向こうに渡しきらないために、息継ぎ無しのサレンダーで一端流れを切った、といったところでしょうか」
「ゴライアス、だからおまえは裏コナミ最弱なんだよ」
「はてさて。ローマさん、それはどういう意味ですか……」
ローマは立ち上がり窓に近づきガラス越しにショウとエリーを見た。そしてそのまま何も喋りはしなかった。面倒くさかったのだろうか。代わりに、ジンがゴライアスに向かって言葉を引きついだ。
「おまえの言っていることも間違いじゃない。むしろ正しいだろう。だが、正しさはそれ1つではないということだ。エリーが絶対的に・作業的に強者として君臨しているときには抗うことが闘いだった。しかし今回、エリーは弱者の立場から、洞察と投身と幸運からなる三種の神器によってあの布陣を完成させた。“自分”以上の成果。あの瞬間線は引かれたのだ。ならばここは引くしかあるまい。サレンダーとは、単なる降参ではない。認めるということだ。そして、決闘には始まりと終わりが必ずある。そして始まるべき瞬間と終わるべき瞬間がある。この試合は、あれこそが終わるために最もふさわしい様式だったということだ。そしておそらく、次の試合にサレンダーはない。線が引かれるとすれば、それはどちらかのライフがゼロになったときだけだろう。次の闘いの行方は、俺にも全く読めん。今、この瞬間から生まれていく以上は」
(『世界』はもう通用しない。私が使うデッキはファーストデッキ。私にはこれしかない。これで勝負を)
エリーは、既に攻め筋を見切られている『世界』を捨て『否定』を取った。元々がやや大ざっぱな『世界』。三度目はないという判断だった。彼女は、最も得意とする戦術に全てを委ねる道をとった。
(悪意の二重奏はまだ効いているはずだ。まだ、策は終わっていない。向こうが委ねるというのなら、正面から打ち砕く。これが、最後の戦いだ)
【ROUND5】
新堂翔(2勝)VSエリザべート(2勝)
第51話:2人の決闘
「引きます。準備はよろしいですか?」
「いつでもいいぜ。つーか早く引け。うずうずしてるんだ」
「私の先攻、ドロー。手札から《豊穣のアルテミス》を召喚。カードを2枚伏せターンエンド」
「ドロー……(アルテミスを先に出すということはカウンターを伏せている可能性が濃厚。迂闊に《増援》でも使おうものなら前回のように《強烈なはたき落とし》を食らうかもな。だが、何もしかけず先手のペースに呑みこまれるわけにもいかない。ここは、ガツンと出鼻をくじく!)」
エリーはショウを突き放す。しかし一方でそこには信頼と覚悟が生まれていた。生まれていたからこそ、彼女は全身全霊で突き放すことができる。そして翔もまた、全身全霊を賭けて追いすがる。
「手札から《E−HERO ヘル・ブラット》を特殊召喚。出ろ! 《邪帝ガイウス》! 効果発動!」
「手札を1枚捨てカウンター罠《天罰》を発動。ガイウスを否認します。更にアルテミスの効果発動!」
(カウンター罠がきた。となると残りは……いや駄目だ。既に先手の術中、そんなことよりも考えるべきことは他にある。1ターン目は論理だ。《天罰》はガイウスには効いてもエッジには効かない。特殊召喚→生贄召喚がこちらの常套手だと散々学習している以上、当然ガイウス・エッジは警戒の範疇だろうが、1ターン目から確率5割以下のギャンブルに臨むわけはないだろうさ。アルテミスの打点は低くもないが高くもない。こちらの初手が打点で勝負をかけるに適したそれの可能性も十分にあったんだ。打ち得な筈の《強烈なはたき落とし》を使ってこないのも妙だ。となると、あの伏せカードは……いやまてよ。あいつには、光属性には《オネスト》という奥の手がある。あのカードなら伏せる必要もない。打点に対する完璧なる否定として機能するだろう。しかしどうする? 憶測は十分だが確信のようなものは依然としてない。どうする? ここで俺は何をすべきだ?)
翔の脳裏に様々な考えが浮かんでは消え、浮かんでは消える。そして彼は、ある決断を下す。
「メインフェイズ2、《地砕き》を発動」 「カウンター罠《魔宮の賄賂》を発動! 否認します」
翔の動きを正確に察知、鋭く叩き落とすエリー。この状況での賄賂は1:1交換で損失ゼロ。更に次のターンでは、生き残ったアルテミスによる手痛い一撃が翔を襲うだろう。そしてエリーが後続のカウンターを引けば更なるプレッシャーが翔を覆い尽くすだろう。しかし翔はこのとき、別の視点を持っていた。
(そっちで来たか。だが、それは一つの真実を示している。読み合い以前の真実を!)
「アルテミスの効果発動。デッキから1枚ドロー」 「カードを1枚伏せる。ターンエンド」
| 2周目 |
| エリー:ハンド4/モンスター1(《豊穣のアルテミス》)/スペル0 |
| ショウ:ハンド3/モンスター0/スペル1 |
「私のターン、ドロー……(一度《オネスト》を召喚してアルテミスと共に攻撃、手札に戻すのもいいけど、むしろここは手札に《オネスト》があるという向こうにとっては未知な情報を最大限利用すべき。向こうの反撃を、《オネスト》で返り討ちにしてペースをつかむ。一手崩せば一気に封殺できるはず)」
「バトルフェイズへ移行、《豊穣のアルテミス》でダイレクトアタック!」
(単騎攻撃。無駄な攻撃は一切せず、付け入る隙を見せない、か)
エリー:8000LP
ショウ:6400LP
「モンスターを1体セット。カードを1枚伏せる。ターンエンド」
隙のないエリーの攻撃。しかし、翔は既に散々学習していた。
「ターンエンド……か。ならそこだ! 《マインドクラッシュ》発動!」
「え?」 「宣言するカードは《オネスト》だ! さ、出してみな!」
翔の不意打ち。さしものエリーもノーセットではどうにもならず。《オネスト》が墓地に送られる。
(《天罰》と《魔宮の賄賂》じゃ単純打撃相手には心もとない。俺のデッキはバリバリの打撃重視だってのにそれは妙だろ。カウンターを一発も打つ暇なくアルテミスがやられていた可能性も十分にある。しかし、それは妙だよな。となればおまえには計算があったんだ。打撃が相手でもどうにかなる計算がな。正直のるかそるかが冷や冷やだったが、高度な合わせ打ちを前提とする否認戦術の遂行には、どこかで素直な部分が出てしまうことを、高い授業料を払って既に学習させてもらった。色々読むのはおまえだけじゃないんだよ。悪いが、その《オネスト》には早めに退場してもらうぜ。そいつは相当に厄介だからな)
「ドロー……いっくぜえ! 《E−HERO ヘル・ブラット》を特殊召喚。更に、こいつを生贄に《E−HERO マリシャス・エッジ》を召喚。バトルフェイズ、《豊穣のアルテミス》を攻撃だ」
(パワーファイターは《オネスト》で処理する予定。対抗は不可能)
エリー:7000LP
ショウ:6400LP
「2枚セット。エンドフェイズ、カードを1枚引く。ターンエンド。(ダメージは与えた。ペースをつかむ)」
「確かに、私は《オネスト》を持っていました。だけど、あたらなかったらどうするつもりだったの?」
「確かに、おまえが捨て駒程度にアルテミスを展開した可能性もある。が、100%それはない!」
力強くそう言い放つ翔。まるで予知能力者でもあるかのように、彼はそう断言した。
(おまえは先手ゲーを得意とする。厄介きわまりない戦術だ。けどな。先手ゲーってのは、意外とその先手を取る瞬間が隙だったりするんだよ。知らなかったか? 俺も今知った。精々動揺しな)
賭けに勝った形の翔。精神的優位に立つことをも計算にいれた闘い様。しかし、エリーは考える。
(違う。ショウのこれは賭け。あの時の気配、私ははっきり感じた。だけど、何を根拠に……)
エリーは、翔の行動がある程度の勝算とある程度の覚悟の産物であることを、翔の動きから辿った。
(そうか。先手を取ることに拘泥する瞬間を狙い、私の足跡を客観的に読んだ。最初の1ターン目は、相手がどうでるか、相手の手札がどうなのか、それらについてなんら絞りがかかっていない。絞る為の最初の一手を打ちに行くことになるけれど、投げた釣り糸を辿られてしまうリスクがあったってこと? 流石、抜け目のない相手。だけどそうとわかった以上、ここで尾を引くわけにはいかない)
エリーの未熟。エリーの【バニシング・クロック・パーミッション】には抜かずの刀のような側面があった。それだけに、連戦において露わになる未熟。しかし、未熟は補完していけばいい。大事なことは、一つ一つに向き合っていくこと。エリーはそう考え、更なる闘いに己を研ぎ澄ましていく。
(流石に動揺はしないか。だがこれで、初戦は有利だ)
火花散る二人の攻防。翔の奇襲がエリーを討つが、討たれたエリーも黙って引き下がりはしないだろう。既にエリーの脳内には新たなルートが開拓されていた。勝負の行方は、まだ誰にもわからない。
「くっ、試合がしたくてたまらん! なぜだベルク。なぜ我があそこにいないのだ!」
そんな2人の決闘に観客席もにわかに活気づく。何かが、何かが変わり始めていた。
「そういう組み合わせだからだろ」 「きぃさまというやつはあ!」 「うるせえよ……」
ベルクはうざそうに顔を横に向けた。と、そこには見知った顔があった。
「あん? 耄碌じじいか。あいつもみてるのか? どいつもこいつも暇だな」
ヴァヴェリもまたじっと見守っていた。老人もまた考える。2人の決闘を考える。
(こやつらは強い。わしよりも……口惜しいが、口惜しいが一方で血が滾る。まだまだ隠居を決め込むまいという、更なる気力がわき上がってくる。ならばみせてもらおう。一でも二でも学ばせてもらおう。こやつらの試合は長引く。なぜかはわからんが、この試合は長引く予感がしてならん)
| 3周目 |
| エリー:ハンド2/モンスター1(セット)/スペル1/ライフ7000 |
| ショウ:ハンド1/モンスター1(《E−HERO マリシャス・エッジ》)/スペル2(セット)/ライフ6400 |
「ドロー……フィールド上の《スケルエンジェル》をリバース、デッキから1枚ドローすると共に、このカードを上級モンスターの生贄に捧げる。召喚、《風帝ライザー》。貴方の時間を止めます。効果発動! 《E−HERO マリシャス・エッジ》をデッキトップに戻す」
「やらせるか! リバーストラップ《亜空間物質転送装置》を発動!」
「同じ手に何度もやられるわけには! 《魔宮の賄賂》を発動、否認します!」
(ドローは止まるが、その前に1枚引いた。やつは、ここで仕掛けるか?)
(1つ1つ、丁寧に消していく。360度、全ての死角をゼロに近づける)
「ターンエンド」 「伏せにビビったのか? それとも今のが読みか?」
「いーえ。どっちかというと虫の知らせです」 「どーだか……」
エリー:7000LP
ショウ:6400LP
「リカバリーも早い。流石だ。エリーは、エリーさんはやっぱり強い」
「だが、ショウもくらいついている。ゲームは、まだ揺れてるぜ」
揺れている。しかし翔は感じ取る。徐々に、支配が広がっていくのを。
(まただ。またこの空気。遠く離されそうになる。既に、限界ギリギリか)
「空」のエリーは距離を支配する。空から正確に相手の動作を限界づける。
「ドロー! 手札から《早すぎた埋葬》を発動。《邪帝ガイウス》を特殊召喚」
しかし翔もまた一歩も引かない、いや、引けないのだ。近づかなければならぬのだ。
(だがな、それでもこの一戦は譲れない。とっくの昔に、譲れない一戦になった)
(こちらの手の内は既に見せた。組みついてのラフファイトが狙いのはず。だけど、ショウは見落としていることがある。このデュエル、5戦まで続いたことによる利は貴方だけのものとは限らない)
(エリーとデュエルを続けてわかったことがある。いかにエリーでもカードの限界は超えられない。ならばこそ、アイツの本気、正確無比な否定の連打は時としてこちらが組みつく好機となる。そして組みつけばこちらの方が上だと既に判明している。必要以上に怯える理由は最早ない。1つでも勝っていると確信できれば、それは希望となり、突破口となる)
2人の思いがフィールド上に乱れ飛び、主導権を求めてぶつかりあう。
「やれ! ガイウス! ライザーに攻撃だ」 「ガイウスを止めて、ライザー!」
帝最強のツートップがしのぎを削る。ガイウスは闇の次元を生みだし、ライザーを引き入れ滅そうとする。一方、ライザーは風の障壁を生みだし、ガイウスを吹き飛ばし消そうとする。この二つの力は全くの五分。互角の攻防、二つの力が消滅していく。そして、2人は、更なるステージに突入していく。
(互角? だけどライフアドは取った。カウントダウン……“5600”)
「負けられないんだよ。モンスターカードを1枚セット。ターンエンド」
| 4周目 |
| エリー:ハンド3/モンスター0/スペル0/ライフ7000 |
| ショウ:ハンド1/モンスター1(セット)/スペル1(セット)/ライフ5600 |
「(エッジが手札にある以上、迂闊に壁を出すのは命取り?) 私のターン、ドロー……」
(こちらの手札にはエッジがいる。向こうは当然それを考慮する。そこが狙い目だ……)
お互い資源のつきかけた現状、しかしそれでも、2人は全神経をお互いへ注いでいた。
(これは? ショウにはまだある種の余裕がある? 消耗戦気味の、この局面での余裕……)
エリーは「新堂翔」をつぶさに観察していた。翔に油断はない……が、一方で見えるもの。
「(おそらく、より激しい闘いになる。もしかすると持たないかもしれない。だけど、私は最後までこの決闘に身を委ねます。)ドロー……カードを2枚伏せる。私はこれでターンエンド」
エリーは手札の《神聖なる球体》をセットすることなくターンを回した。特段の意味もなく至弱のカードをセットするのはむしろ相手に流れを渡す。そしてそのこと以上に、エリーはある巨大な流れに自ら身をゆだねようとしていた。次は翔のターン、彼もまた、より大きなうねりを予感していた
「ドロー……とりあえずカードを1枚セット。でもってだ。さっき伏せておいたこいつを裏返すことができれば、この決闘はより激しくなるだろうさ。それが嫌なら否認しな。その手段があればの話だが」
「ショウ、構いませんよ。私もそれを望んでいます。決闘のために。そして勝利のために」
翔は悟った。強敵なのだ。わかっていたことではあるが、目の前の相手は強敵なのだ。おそらく、エリーはその可能性を薄々察していた。察してた上で自分にも相手にもお膳立てをしていたのだ。
「そうかよ。おそらく、あんたが見きった通りだ。この試合、まだまだ激しく続けようぜ。手札を1枚伏せてリバース。《メタモルポット》の効果発動。お互いに手札を全て捨て、5枚引きなおす」
「完全に見切ってたわけでもありません。だけど、私は身を預けます」
「身を預けても、勝利を預ける気はないんだろ」 「はい、まったく」
「……」 「……」
「なあ、15分ほどここで使っちゃ駄目か?」 「少し、時間をかけませんか? ここ」
異なる口から異なる言葉。しかし、その意味するところは同じだった。
「同じか。当然、断るわけないな」 「問題は、それをやっていいのかだけど……」
時間無制限とはいえ1ターンの制限時間は一応ある。遅延行為に該当したりはしないのか。
「この試合のルールは俺達で決めるんだろ。だったら、いいじゃないか。なにも問題ないだろ?」
翔はいたずらっぽく笑った。そんな、彼の考え方に、エリーもまた同調する。
「“今日中に終われ”ばいいんでしたね。2人でいいデュエルをしましょう。その上で、勝ちます」
「さってと。おい審判の旦那。15分だ。15分たったら再開、いいだろ? 悪いって言ってもやるぜ」
是非も無しだった。「2人の決闘」は、ここへきて更に深まっていく――
「ローマさん、この試合の責任者は貴方です。どうなさるおつもりですか? この状況を……」
「違うな。この試合の責任者はあいつら……てめえの闘いをてめえで決めるのが決闘者だ」
「それでは、不問にすると?」 「あのルールの意味。気づくのが遅すぎるぐらいだ。雑魚共が」
『雑魚共が』。しかしその響きには、そう見下すような音もなく。ローマは、厳しく問い続ける。
「なるほどな。だが、世の中一般はおまえほど強くもない。野暮用に出させてもらう」
そういうとジンは出ていった。ふと見ると、ゴライアスもどこかへ消えていた――
「どいつもこいつも、手遅れすぎる連中だ。せめて、くだならい決闘だけは見せるなよ」
――北門――
「流石にそろそろ帰ろうぜ。もうここにいたってしょうがないだろ」
「ああ、わかった。だが、ちょっとまってな。これを片付けたら……」
「さってと、今日どこいく?」 「ファミレスだろファミレス……」
そこには決闘者が数人いた。しかし誰もが、帰宅寸前である。
「さってと……ん? ありゃなんだ?」 1人の男が声をあげた。
「せっかちなことだな。メインディッシュを残すとは」 若い男がいざ1人。
「おまえたちがどこへいくのも勝手だが、一つ知らせておくことがある」
「な、なんだおまえは!」 「こいつ、なんて怪しいやつだ!」
「別に怪しくはないさ。おれは瀬戸川刃。通りすがりの決闘者だ」
「せ、瀬戸川流! あ、あの殺人流派の瀬戸川流が何の用だ!」
「試合場に戻ってみろ。面白もいものがみれる。それだけだ」
「な……今更試合だと!? さっき見たが何の盛り上がりも……」
「おっと手が滑った」 刃は、北の出口を一刀両断に切り裂いた。
「な、なにしやがる!」 驚いたのは決闘者達。しかし刃は涼しい顔だ。
「いや、急に決闘盤をふりましたくなってな。特に理由はないが、ここを通ろうとした人間を一刀両断に切り裂いてしまいそうな気がする。無論そんな気がするだけの話だが……」
「くっ、しかたない。いったん試合場にいってから別の出口を探そうぜ」
「あ、ああ。(なんてクレイジーなやつなんだ。ぶったぎりやがった)」
試合場に戻る数人を尻目に、ジンは壁に寄り掛かった。
「裏コナミの人間として、多少は、振興活動に寄与せんとな。機会を与えれば人が変わることもある。無意味なことかもしれんが、より多くのものに試合をみせたい……甘いか?」
――南門――
「中で飯も食えるとは思わなかったな。そんじゃ、帰るか」 「そうだな……あ、あれは!?」
南門出口から退出しようとする決闘者達の目の前には、紳士の風貌をした1人の怪人。
「ぬぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅっっっっっっ! はぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!」
紳士の腕が破裂したかと思うと、そこからは得体の知れぬ、カード型の触手が伸びる。
「おやおやどうされました? 小生のことなどお気になさらず、ささ、お通りください」
『お通りください』と言われたところで通れる人間等いない。悲鳴をあげて、走って逃げる。
「おやおや。こちらの出口を使われないのですか? しょうがありませんねえ。不可抗力不可抗力」
――東門――
「明日は俺の試合だからな。フリーデュエルにつきあってくれてありがとよ」 「どういたし……あれは!?」
東門付近。今日も熱心な2人が仲がよさげに和気あいあいと歩いている。しかし、そこにはあの男。
「オォー――――――――――――――――――――――ム! ずぅおおおおおおおおおおおおお!」
そこには謎の修行僧が坐禅を組み、カードを火種とした蝋燭に囲まれ、怪しげな呪文を唱えていた。
「お、おい……」 「あ、ああ……」 2人の決闘者は眼と眼でで示し合わせ、そしてその場を静かに離れた。
――西門――
「大丈夫か? 食べ過ぎなんだよ……」 「わりいな。遅くまで……」
西門付近。やはり帰宅の道を進む男達の前には、ある女の影。
「道を教えてほしいんだけど。試合場ってどこ?」
「え? そりゃ……向こうにまっすぐいけば……」
「試合場はどこだって聞いてるのよ! それをお!」
その女は、鎌を振り回し壁を切りつけた。
「う、うわあああああ! に、逃げろぉ!」
「あれ? いま試合やってるんだっけ? どーでもいーや」
ベルメッセは、特に何も考えていなかった。彼女は寝た。
――闘技場――
「まったく、なんだってんだあの紳士は……ん? おまえらも戻ってきたのか?」
「あ、ああ。なんか面白いことをやっているようだが……あれ? まだやってるぜ」
「本当だな。あっさり終わったんじゃなかったのか。2対2、接戦なのか?」
「つーか、なんか感じないか? このピリピリした空気、いったいどういう……」
「そんなものはちゃんと見ていればすぐわかる。だからおまえらは三流なんだよ」
「な、なにい!? てめえ誰に向かって物を言って……、お、おまえたちはーっ!」
戻ってきた多数の決闘者が一斉に振り向く。そこには、三人の決闘者がいた。
「西日本決闘者同盟ソリティアの会の……大日本九州帝国三巨頭!」
「村坂剛」「新上達也」「神宮寺陽光」、そろい踏みであった。
「ちっ、あいつらこっちじゃ無名の癖していいデュエルしやがる」
「同感だな村坂。栽培力がどんどん上昇している。おい神宮寺、ローマにやられた傷がうずくだろう。別におまえは帰ってもいいんだぞ」
「抜かすな新上。知ったことか。この試合は、この試合はな。間違いなくベスト8レベルだ」
「す、すげえ! 九州三強の、あのプライドの高い神宮寺がベスト8入りを明言した!」
「そこまでの闘いだっていうのかよ。まさかベスト8だなんて……本気で言っているのか!?」
「なんだかよくわからねえが、なんだかよくわからねえが……この試合、見るべきなのか?」
「さってと。そろそろだな。はじめるとするか。最後の大勝負をな」
新堂翔は立ちあがった。100の戦略を、彼は練りに練った。
(エリー、10分間ずっと俺のこと見つめてたな。すごい集中力だ)
(最終局面、リスクを冒してでも勝ちに行く。その為の観察。ショウの気配を全て感じ取る。嘘も、本当も、全て。全てを受け入れて、全てを賭ける。最後まで、最後までやりぬく)
エリザベート=バスターと新堂翔。生き方も、出自も、デッキも、戦略も、全く違う両者であったが、1つだけ共通することがある。それは今、彼らが同じ土俵で決闘を行っているという事実。それだけでいい。それだけで2人にとっては十分だった。彼等は闘う。お互いの力でその価値を高め合った、勝利を掴むために。
全くの五分に終わった五戦目を経て、遂に六戦目が始まる――
「そんじゃいくぜ! 再開だ! 俺は手札から《悪夢の代行者》を通常召喚。バトルフェイズ、《メタモルポット》と《悪夢の代行者》でダイレクトアタックだ!」
エリー:4500LP
ショウ:5600LP
「はぁ、はっ……(10分間も、そして今もやはり強烈なプレッシャー、見る方も大変なんだろうが見られる方も大変さ。10分考えた。考えたが……結論は一つ。その場を閃きを優先する。そして、閃きを生かすためには、後手に回らないこと。あいつのペースの千分の一ミリでも崩しておくこと)」
(ショウは必ずどこかで仕掛けてくる。仕掛けずにはいられない人。だから、そこを察知して潰せばいい……というのが1ラウンド目の私。だけど、ショウもそれを当然理解している。だから、更にその先を……)
「ターンエンド」 「そこ! 《サイクロン》を発動! このターンに伏せたカードを破壊、否認します」
(意地でも先手は取らせない気か。上等) (攻めに回ると強いのは向こうも同じ。好きにはさせない)
このターン、翔はライフでエリーを逆転した。しかし、既にエリーの反撃は始まっている。今の《サイクロン》はまさに起点だった。そして意思表示だった。ショウがエリーから離されまいとするのと同様に、エリーもまたショウに崩されまいと必死に食い下がる。そこには、何の不純物もなく――
「なんだろうな。すっげえくやしいんだよな」
アキラは言う。「悔しい」。謎の感情だった。
「なんとなくわかります。なんでしょう、これ」
若い決闘者達は、拳を握りしめていた。
(この敗北感。僕は敗北感を感じているのか?)
| 5周目 |
| エリー:ハンド5/モンスター0/スペル1/ライフ4500 |
| ショウ:ハンド4/モンスター2(《メタモルポット》《悪夢の代行者》)/スペル1/ライフ5600 |
「ドロー……手札から《ライオウ》を召喚。《メタモルポット》に攻撃!」
(当然狩られるよな。だが、ライフを優先的に減らしにいくその狙いは……?)
(カウントダウン……“4400”……“2500”……“600”……いける!)
「カードを3枚伏せてターンエンド」
(確かに《大嵐》くらいしか多重除去は入れてないが、やってくれる)
エリー、ここで決意のフォーセット。他方、翔の脳裏には危険信号。
(これは軽視できる状況じゃない。防ぐには? 攻める、それが処方箋だ)
「俺のターン、ドロー。《悪夢の代行者》を生贄に捧げ《E−HERO マリシャス・エッジ》召喚」
完全否定されるわけにはいかない。少しでも早く、袋小路からの事前脱出を試みるショウ。
(《聖なるバリア−ミラーフォース−》でも《強制脱出装置》でもどんときやがれってんだ)
4枚伏せに対して単騎突破は難しい。だが、壁を薄くするには攻めるしかなかった。
「バトルフェイズ、《E−HERO マリシャス・エッジ》で《ライオウ》に攻撃! ぶっ壊れな!」
この試合第二戦を皮切りに何度も繰り返された光景。しかし、今のエリーは一味違う。
「手札から《オネスト》の効果発動! 攻撃力を吸収! その威力をそのまま貴方に!」
「4枚伏せるなら伏せで止めろよな。くっそお。一番嫌いなカードだよ、そいつは!」
エリー:4500LP
ショウ:2500LP
「もう《マインドクラッシュ》ない……もんね。はっ、はっ……うっ!」
エリーは口元に手をあてた。極めて少量だが、彼女は血を吐いていた。
(限界、かな。だけどまだもって。まだ、私はデュエルを終えたくない)
(あれは……そういうことか。あれだけの観察力、集中力は器を壊す)
既に5戦目、それも5戦目は120%の集中力で臨んでいるエリーだ。エリーの身体はディムズディルやローマ程強靭ではない。その上で、中断中も含め今までの以上の負荷をかけているのだ。
(もっとも、ボロボロなのはおまえだけじゃないさ。おかげさまでな)
翔もまた、そんなエリーの尋常ならざるプレッシャーに耐えてきたのだ。ディムズディルの決闘波導とは似て非なるがさりとて劣るものでもない強烈なプレッシャー。それは、ショウを確実に蝕んでいた。
(延々とやりたいところだが、そろそろ決着の時としては頃合いかもな)
(わかる。ショウはここから一気に勝負をかける。なら私は、その機先を制す)
「一筋縄じゃいかねえ。やっぱ強いなエリーは。ん? おまえは……」
「やってるね桜庭さん。あっちみてると、ちょっと妬けちゃうかも」
桜庭遥の後ろに現れたのは斎藤聖だった。彼女は、少しだけ遠くをみて言った。
「桜庭さん、いつかまた勝負してくれない? またどっかでドジって負けちゃうかもしれないけど」
「ああ、いいぜ。どうせ当分は引っ越したりしないからいつでも遊びにきな。どうせ暇で貧乏だ」
「ありがと」 「デュエル、か。あいつらも、今カードを引きたくて引きたくてしょうがないんだろうな」
| 6周目 |
| エリー:ハンド1/モンスター1(《ライオウ》)/スペル4/ライフ4500 |
| ショウ:ハンド3/モンスター0/スペル3/ライフ2500 |
「私のターン、ドロー……いきま……え!?」
「瀬戸川流万屋術奥儀『我チャピンと無ック』」
(ショウが気配を消していく。これは……)
(また聞きのまた聞きのうろ覚え、さてどうなるか)
「おまえの技だな。ジン。どっかで教えたのか?」
「『無運沙流賭』。教えた覚えはおろかあった話した覚えもないな」
(流石ショウ。いやがおうにも舞い上がるこの局面で……だけど!)
エリーはその身に全ての力を集中した。残りの全ての力を賭けて翔の懐に飛び込み、超高速かつ超精密なバニシング・クロックを刻む。その為のコンセントレーション。一瞬、会場の体感温度は氷点下まで下がり、そしてエリーが動くとともに、その一挙一動は熱をもって迎え入れられる。これが、紛うことなきエリーの全力。限界点の闘い――
「《豊穣のアルテミス》召喚。バトルフェイズ、アルテミスでダイレクトアタック!」
天使再臨。カウンターの申し子が《ライオウ》と共に翔に迫る。
「(制空圏に触れた。ここだ!) 《聖なるバリア−ミラーフォース−》発動」
すかさず翔の反撃。温存していた反射鏡を眼前に形成……しかし!
「《魔宮の賄賂》発動! さらに、賄賂のドローに対して《強烈なはたき落とし》発動!」
「なっ!?」 縦に横にの否定二重奏。思わずながらも、翔は苦闘を強いられる。
(カウンター2発。アルテミスによりデッキから2枚ドロー。潰しながら増やすのか!?)
エリーは突き進む。局地的に時間を止めながら、翔の喉元に向かって突き進む。
「《リビングデッドの呼び声》を発動。《E−HERO マリシャス・エッジ》を特殊召……」
「《強制脱出装置》を発動! 《E−HERO マリシャス・エッジ》をバウンスします!」
【バニシング・クロック・パーミッション】全開。超高高度からの超高速否定弾。だが翔も!
「やらせるかあ! 《エネミーコントローラー》発動! エッジを生贄に《ライオウ》を奪う」
《ライオウ》を奪い盾とすることで難を逃れた翔。しかし逃れただけ。ピンチは続く。
(少しは怯むかと思ったんだけどな。ほぼ完璧に打ち込まれた。虎の子のエネコンがこの様だ)
ここにきてエリーは怒涛のラッシュを繰り出した。その勝算とは何か。翔はここでも考える。
(これは一種の慣れだな。エリーのタクティクスは俺にとって初見だった。そして、三戦目あたりではその初見の不利がなくなることもあり【二つの悪意】がこちらに圧倒的優位をもたらした。しかし、俺はもう【マリシャス・ビート】を5〜6戦分みせている。加えてこの総力戦。俺がエリーのデッキに慣れたというのなら、向こうも俺のデッキに慣れている。単純な意味において、アイツはこっちの、【マリシャス・ビート】に慣れたんだ。こうなってくると、不利なのはこちらか? あちらの、直接攻撃以外のラッシュはこの試合初めて見るが、こっちは逆に嫌というほどその攻め筋をみせつけてきた。中期戦ではそれが撹乱に一役買ったが、長期戦ではそれが諸刃となる、か。実際、基礎となる攻め筋自体は唯一単純。サイドチェンジどころかデッキチェンジもない“6戦目”は無謀だったか?)
(そちらの攻撃力は確かに高い。けどこちらにはこちらなりのラッシュがある。学習に学習をさせてもらった今なら、ラッシュでも十分にショウを抑え込める。こちらの攻め筋を広げつつ相手の攻め筋を狭める、この闘い方なら、半歩先を歩ける。半歩、半歩でも先を歩ければ勝てる)
(最早小細工も通用しないだろう。それ以前に、使えそうな小細工がもうない。だが……)
「はぁ……はっ……負けません。いえ、勝ちます。絶対に私が勝ちます。ターンエンド」
「エリーがラッシュをかけてきた。だけどショウさんだってそう簡単に……あの、どっちが勝つと……」
だが、信也はそこまで言いかけて何かに気がついた。ある異変が、会場というか空間を覆っていた。
(みんながこの試合に集中している。それだけじゃない。勝敗に興味をもっていない。というか視界にない。なんでだ? 当の2人はあんなに勝ちたがっているのに……)
信也はこのとき、一瞬だが空間を俯瞰した。それは、彼の才能なのか。
(そうか。あの2人が純粋に勝利を目指して闘っている。だからこそ、観客にとっては最早勝敗など結果でしかない。勝利の意思を背に高められた決闘に魅入っているんだ。だけど、だとしたら僕は?)
異端者は考える。この決闘に心を震わせられながらも、一方で気を迷わせる自分を。
(だったら。だったらみせてください。貴方達の闘いを。僕は僕なりに見させてもらいます)
「やっぱまた聞きのまた聞きじゃこんなものだろう。が、クソの役ぐらいには立ったかもな」
「え?」 『また聞きののまた聞きの思いつき』。だが、『2』手先の奥行を隠せればそれで十分だった。
(最高に美味い勝利を味わいたい。しかしそれには条件が3つ。1つは、最高の決闘者同士であること)
奇襲は桜庭戦で、相手に見せつける闘い方は斎藤戦で、粘り強さは瀬戸川戦で、信念はディムズディル戦で、それぞれ培ってきた。そしてそれらをかき集め、旗印に込め、決闘者として旗揚げした。
(そして1つは、最高の決闘であること。最高の決闘とは、最高の決闘者同士が互いに1つの頂点に向けてお互いを意識し、お互いがしのぎを削り合い、前に、前に進み続けることだ)
エリーは今最高にスリリングな相手として己めがけて向かってきている。翔には最早、何の不満もない。
(そして最後の、最高の勝者の条件、最高の決闘者同士が最高の決闘を行った上で……勝つことだ! やつはスペルを一気に消費した。例えアドは増えても、そこには最早計算等ない。この一点、全てをぶつけて通るか否かだ! 通してみせる。そして勝つ!)
彼が求めるものはあくまでそれだった。最高に美味い勝利というからには、勝利を目指すのが必定。
「俺のターン、ドロー……手札から《ならず者傭兵部隊》を召喚。効果発動。《ライオウ》を破壊する。そんじゃ、《ダーク・コーリング》を発動。危ないところだったが……この大細工で決まりだ」
《増援》の二番手三番手、傭兵部隊が生引きから《ライオウ》を切り崩す。その先にあるのは何なのか。
(《E−HERO マリシャス・デビル》? だけどそれならばこちらには《シャインエンジェル》という防御がある。デビルは貫通も耐性も持たない。リクルーターで受け止めサーチで……違う!)
「墓地の代行者と悪ガキ、更に手札から《E・HERO バーストレディ》をゲームから除外!」
Evil Hero
Darkness Inferno Wing
| 《E−HERO ダークネス・インフェルノ・ウィング》 融合・効果モンスター 星8/闇属性/悪魔族/攻2500/守2100 「E・HERO フェザーマン」+「E・HERO バーストレディ」+「E−HERO ヘル・ブラット」 このモンスターは「ダーク・フュージョン」による融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードが守備表示モンスターを攻撃した時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手ライフに戦闘ダメージを与える。 このカードが戦闘によってモンスターを破壊し墓地へ送った時、破壊したモンスターの攻撃力か守備力の高い方の数値分のダメージを相手ライフに与える。相手がコントロールするカードの効果によってこのカードが破壊された時、 相手にその元々の攻撃力分のダメージを与える。 |
相手に動向を読まれないための方法。それは盲点を作ること。しかし盲点を作るとは? 色々な方法が考えられるだろう。その内、翔が今回取った方法は単純だが効果的な方法だった。あらかじめデッキにたった1つ、違う色を忍ばせておき、そのまま放置する。そして乱戦、混戦になるのを待つ。待つというよりは自らそうなるよう奮闘する。相手が強敵ならば自然とそうなるであろう。そんなとき、効いてくるのがこの1枚。【ぶれる悪意】とは全く関係ない所に位置する《E・HERO バーストレディ》が、翔の活路を切り開く。
(構築するだけ構築した上で“一点”外す。それが裏稼業のやり方なのさ)
(迂闊だった。この系列の可能性もゼロじゃない。ゼロじゃなかったのに)
「混戦になれば、盲点はより盲点となる。伊達に温存してたわけじゃないんだぜ」
エリー対策ラストの一手。いかに観察力が高くとも、忘れてしまえば意味はない。
(しまった。さっきのショウの無の構えは、単なる陽動。ラッシュを止めるためのものではなかった。三戦目のシャッフルも、これも、ショウは私の視点をずらしにくる。そして全てはこのときのために――)
「《E−HERO ダークネス・インフェルノ・ウィング》で《豊穣のアルテミス》を攻撃する!」
Darkness Inferno blast
漆黒の翼を広げ、悪魔が天使に向けて突進する。進化前より更に禍々しくなった掌を、更に鋭くなったその爪を、アルテミスの細い胴体に向けて突き立てる。内部からの超高熱が、天使を溶かす。
「《豊穣のアルテミス》を破壊する。更に効果発動。守備力分のダメージを与える」
Darkend Inferno!!
エリー:1900LP
ショウ:2100LP
「王手だ。うかつに破壊しようものならその時点で首が飛ぶ。守備表示で守ろうとしても、首が飛ぶ」
エリーがデッキに入れている可能性のある除去といえば大量除去の《ライトニング・ボルテックス》か、必ずしも打点に頼らないことを活かした《ハンマーシュート》か。投入の有無はわからないが、いずれにせよ封殺。そして、守備表示の壁には貫通と焼却で2500以上のダメージ。まさしく王手だった。
(あ……はは。デュエルに勝つってたいへん。ほんっとたいへん。どうしよっか……ライザーも脱出装置も、オネストも使ってしまった。手札には《マジック・ストライカー》《シャインエンジェル》……)
| 7周目 |
| エリー:ハンド3/モンスター0/スペル1 |
| ショウ:ハンド1/モンスター1(《E−HERO ダークネス・インフェルノ・ウィング》)/スペル0 |
「私のターン……(流石に駄目かも。あの《ダーク・コーリング》で私は上をいかれてしまった。さし合いでは勝てても、奥行きで負けている。だけど、それでもあと一度だけ甘い夢を真剣に見ていたい)」
(流石に「勝った」。これは勝っただろ。だけどなんだ。この心臓の高鳴り具合は)
高ぶるショウの中に高ぶる己を見たのか、エリーは一回深呼吸をした。エリーは数秒目をつぶった。そして様々なことに思いを巡らす。と、そのとき、彼女は眼をあけ声を張り上げた。
「ショオーーーー! デュエルとは、デュエルとはなんですか!」
「そんなもん右から左に言えるか。そういう質問はディムズディルにしな」
「だったら! ショウ! 貴方は、貴方はデュエルを愛していますか?」
「どうだろうな。だが少なくとも、俺は今このデュエルを誰よりも愛してるぜ」
「ショウ、私も、私もこのデュエルを愛していると言っていいですか?」
「許可を与える権利なんてない。だがな! あんたがこの試合を愛してくれないなら俺は失恋だ!」
「私はこの試合を、この瞬間を生きていたい。ドロー……リバースカードオープン!」
エリーは、《メタモルポット》発動直前のターンに伏せた最後のカードをリバースする。それは、およそ伏せるようなカードではなかったが、エリーがショウを信じることで、ショウを信じる己をフィールド上に賭けることで、その所産として伏せられたカードであった。エリーは、飛んだ。
「《クロス・ソウル》発動。手札から《シャインエンジェル》を通常召喚。更に《クロス・ソウル》をゲームから除外して《マジック・ストライカー》を特殊召喚。いくよ! 《E−HERO ダークネス・インフェルノ・ウィング》《シャインエンジェル》《マジック・ストライカー》 を生贄に捧げ……現れて! 不可視天使!」
Invisible Angel Arkeliza
| 《不可視天使 アークエリザ》 星8/光属性/天使族/攻1500/守3000 このカードは通常召喚できない。自分フィールド上に存在する光属性天使族モンスターを含むモンスター3体を生け贄に捧げた場合のみ特殊召喚する事ができる。このカードの特殊召喚に成功したとき、フィールド上のカード1枚を持主の手札に戻してもよい。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃することができる。このカードは相手プレイヤーの攻撃を受けたとき守備表示に変更することができる。バトルフェイズ終了時、任意の表示形式に変更した上で次のバトルフェイズ開始時までこのカードをゲームから除外する。このカードの効果によって除外されている場合、自分ターンのスタンバイフェイズ毎にフィールド上にセットされたカード1枚を持主の手札に戻してもよい。 |
(見えないにもかかわらず……綺麗だな。先の試合で正体を確認したから、それを思い浮かべたからか? いや、違う。今回の召喚にはあいつの気持ちがこもっている。こんにゃろうが)
「誓約効果によりバトルフェイズは行わない。ターンエンド」
(切り札中の切り札ダークインフェルノをもってしても決着をつけることができなかった。それどころか目の前には難攻不落の不可視天使。強い。やはり途轍もなく強い。全てを賭けて挑んでくる今のエリーは、ディムズディルやローマにも匹敵するかもしれない。喜べよ、俺。楽しめよ、俺。何の不満があるってんだ?)
【バニシング・クロック・パーミッション】のもたらす絶望感をもってしても、消せないものがあるのか否か。
(わかっている。ショウは最後まで諦めない。だけど貴方が諦めないでくれるからこそ、私は消し続けることができる。動き続けることができる。そして、最後まで動き続ける。勝利のために)
(それでも、それでもチャンスはあるはずだ。帝に不可視天使、生贄確保のための《クロス・ソウル》だろうが、バトルフェイズを経ていないおかげで不可視天使はいまだ除外されてない。向こうだって必死なんだ。隙を細かく消す余裕なんてないはずなんだ。チャンスはあるんだ……)
「俺のターン、勝負はまだまだこっからだ、ドロー……」
(ショウの眼は死んでない。何か、光明を見出した?)
(《ダーク・コーリング》。《E−HERO マリシャス・デビル》を出せば、攻撃力3500でバトルに勝てる!)
翔の手札に舞い込んだ一筋の光。しかし、翔はこの時思考の足を止めた。一瞬の、悪寒。
(《クロス・ソウル》があるということは《洗脳−ブレイン・コントロール》もあるってこったろ。まだでてないからそろそろ……いやそういうこっちゃないだろ。要はこっちの手札との相談だ。こっちには《大嵐》がある。目の前の伏せを除去れるんだ。が、問題は通常魔法タイミングでしか伏せを割れないということ。返しのターンで《強制脱出装置》を伏せられるというのが最も怖い。しかしそんな仮定いらないだろ今は。事態は切迫している。そんな悠長なことを考えてる場合じゃないんだ)
「メインフェイズ。俺は……俺は……」
(殴れ! 殴るんだ。ここは殴る一手しかない。他に方法などあるわけがない。殴る……)
しかし翔は動かない。翔を襲った根拠不明の直観。他に手があるとでもいうのか。
(ここでターンエンドと言ってしまったら酷いことになるぞ。不可視天使で1500、他に600以上のモンスター……さっき生贄にしたマジストを蘇生して殴るとか……そんなんで綺麗さっぱり決着がつく。いくら打点に頼らないっつったって600以上はたくさんあるだろ。ここで《ダーク・コーリング》を握りしめたまま死んだらそれこそ後悔……)
しかしこの時、『後悔』という言葉を思い浮かべたそのとき、翔は何かが吹っ切れた。
「後悔……はっ、俺は勝つためにここにきた。俺の決断は、努力賞をとるためのもんじゃないんだよ! ターンエンド! そっちにまわすぜ。殴りきれるもんなら殴りきってみろ!」
| 8周目 |
| エリー:ハンド1/モンスター0/スペル0/※《不可視天使 アークエリザ》除外中 |
| ショウ:ハンド2/モンスター0/スペル0 |
「ドロー……(ショウが何を考えているのかがいまいち掴めない、かな)」
つかめないはずである。本人も、はっきり口で説明できないのだから。努力賞云々は兎も角、確率的にはエリーが600以上のモンスターを手札に引き入れる可能性の方が高い。しかし翔はターンエンドと言った。言ってしまった。翔は今猛烈に後悔している。しかし言ってしまったものは仕方がない。
(くるなよ。くるんじゃねえぞ。単騎で殴れ。それだけで終われ。終われよ……)
(翔の考えがどうであれ、ここは攻撃するだけ。それだけははっきり見える)
エリーはここで当然の選択をする。その選択は、お互いにとって正論だった。
「バトルフェイズ、帰還した《不可視天使 アークエリザ》でダイレクトアタック」
エリー:1900LP
ショウ:600LP
「カードを1枚セット。ターンエンドを宣言……逆王手……です」
(逆王手、か。おっそろしい状況だが、なんとか生き残った、か)
(頭が痛い。今すぐバタンキューしたい。でももうすぐ終わるから。私が勝つにせよショウが勝つにせよ、この試合はあと1〜2ターンの内に終わる。予感というよりは確信。決着は、すぐにつく)
「ショウ、これが私の精一杯。今度は貴方の精一杯を見せてください。ターンエンド」
「ああ、そう願いたいもんだ。そんじゃ引くぜ。俺のターン……」
(このドローだ。ギリギリまで引っ張った結果の最後のドロー。勝つも負けるもこのドロー次第。あの一瞬の閃きがただの錯覚かどうか、愚行かどうかもこのドロー次第。神に頼む気はしないが、しないが……)
「引き当ててみせる! ドロー……はっ! そういうことかよ!」
(ショウの顔が変わった。わかる。これは、最後の勝負を賭ける顔)
「きたきたきたきたきたきたきた遂にきたぜえっ! 最後の大勝負をかけるカードがな! 《ダーク・コーリング》発動! 墓地の《E−HERO マリシャス・エッジ》と《E−HERO ダークネス・インフェルノ・ウィング》をゲームから除外。融合デッキからこいつを出すぜ!」
Evil Hero Malicious Fiend
「更に《大嵐》を発動。カードを1枚伏せてターンエンドだ。俺は、バトルフェイズをおこなわない」
「あ、あれは! あれは第三戦と同じ光景! マリシャス・ゾーンだ!」
「あの効果を1日に2度使う馬鹿がいるとはな。アレが決まればショウが勝つ!」
| 8周目 |
| エリー:ハンド0/モンスター0/スペル0/ライフ1900/※《不可視天使 アークエリザ》除外中 |
| ショウ:ハンド0/モンスター1(《E−HERO マリシャス・デビル》)/スペル1(セット)/ライフ600 |
「ドロー……スタンバイフェイズ、《不可視天使 アークエリザ》の効果発動。セットカードを戻す」
「リバース。《悪魔の誘惑》第二の効果を発動! このターン、バトルフェイズに突入しなくてはならない」
「……わかりました。メインフェイズ……何もすることはありません。ここで使うべきカードもありません」
エリーはドロー後静かにターンを進行した。それは、本当に静かだった。
「バトルフェイズ、《不可視天使 アークエリザ》帰還。アークエリザで……」
(おかしい)
この時、翔はそう思った。淀みのない攻撃宣言への流れ。その動作があまりに淀みのないものであることに、翔は不安をかきたてられた。確かに1ターンの「待ち」は翔に決断への選択肢をもたらした。しかし、1ターン待たれたという意味ではエリーも同様。エリーはその分追加のドローを得ているのだ。ショウは……観念した。
(《オネスト》、か。1500のダメージで……俺のライフは完全に削られお釣りがくるな)
「いいぜ」 翔は、小さな声でそう言った。
(手札もゼロ、伏せカードもゼロ、万策尽きはて、おまけにろくなライフも残っちゃいない。この状況下で打てる手なんてそりゃないさ。だが、後悔もない。やれることは全部やった。だったら喰らうしかないだろ。サレンダーはしないぜ。最後のバトル、派手にやってくれ)
そのときだ。エリーは静かな己を解き放ち、持てるすべての力を込めて宣言した。
「《不可視天使 アークエリザ》で……《E−HERO マリシャス・デビル》にアタック!!」
最早不可視ではない。圧倒的な存在感と共に天使は空を舞う。天からの告知を伝えるべく、大剣を構え、翼を広げ、デビルめがけて一直線。そこに迷いは一切なく、その姿には美しさが垣間見えた。
「(最後まで、最後まで戦い抜く。さあマリシャス・デビル……) 闘い抜いてこい!」
ショルダーアーマー、レッグアーマーを脱ぎ捨て、巨大なウイングをパージ、悪魔の申し子としての矜持だけを背負い、デビルは不可視天使に向かっていく。デビルは頭部ユニットの6本の刃を放った。だがそれはすぐさま弾かれた。デビルは左手のクローを射出、不可視天使を狙うがこれも駄目。しかしデビルには、デビルには一握り分のエッジがあればそれで十分だった。デビルのライトクローと、アークエリザの大剣が交差する……と、その瞬間、巨大な爆発が巻き起こる。煙に包まれ視界は最悪。だが、それでもわかることが1つだけあった。それは、この闘いに終止符が打たれたという厳然たる事実。終幕の鐘はなったのだ。
「強かった。あんたは強かった。憎たらしいぐらいにな。だが、いい勝負だった。それだけは言える」
煙が晴れ、相手の顔を見ることができるようになる。と、その時、翔はその異変に気がついた。
「エリー……」
「Au revoir」
エリーの眼には、涙が浮かんでいる。彼女は、絞り出すように声をあげた。
「はい、本当にいい勝負でした。今日のことは忘れません。私の……負けです」
【エリーVSショウ】
第一戦:エリー
第二戦:ショウ
第三戦:ショウ
第四戦:エリー
第五戦:ショウ
(3枚目の《オネスト》は、引かなかったのか……)
少し遅れて届く真実。翔は少し当惑していた。エリーは、そんなショウに握手を求め、手を数秒握ると、翔に背を向け一目散に走り去って行った。翔はその間、何も言えなかった。エリーの次のデッキトップは? どうでもいいことだ。最早そんなことはただの事実に過ぎない。試合は、終わったのだ。
「ほらよ、千円。見物料代わりにくれてやる。おまえに払う理由はないけどな」
「そーいうこった。俺も見物料代わりにおいとくぜ。精々カードでも買いな」
アキラとストラは共に千円を差し出した。「見物料」、2人ともそう言った。
「じゃあ僕は誰に見物料を払えばいいんですか。まあ、とりあえず総どりしときますけど」
そう言い残すと信也は三千円もって帰っていった。その顔は、少しばかり興奮していた。
(壮絶な戦いだった。あんな決闘が繰り広げられる場所で、僕は、僕はどうすべきなんだろう)
「おーおー若いっていいな。さてと……ん? あいつ、今さっき総取りって……おいディム……」
既にディムズディルは消えていた。ストラは「やれやれ」といった調子だった。
「あいつでも、たまにはこういうことあるんだな」
(紙一重、だが、最後まで闘う姿勢を崩さなかった新堂が千分の一ミリ差で勝利した)
ディムズディルは1人で廊下を歩いていた。その手には一枚の紙。
「ローマが見たらどんな顔で笑うのやら。僕も甘くなったものだ。今すぐにでも破棄したいくらいだが……もう少し持っておくか。戒め……何のだ? まあいいか。そんなことは……」
「エリザベートに千円」。そんな内容の文章が、雑な字で書かれていた。
(僕にもくるだろうか。真に死力を尽くして闘える、そんな瞬間が……)
「ローマさん、貴方は、貴方ならどうこのデュエルを総括しますか? 是非お聞かせ願いたい」
試合が終わり、無言で部屋を出ようとするローマの眼前、ゴライアスは、扉の前により立ちそう聞いた。しかしローマは何も答えなかった。かわりに、強烈な右ストレート。ゴライアスの顔をかすめていったその一撃はドアに直撃、当然の結果として開くドア。ローマは、開いた出口から立ち去る際にこう言った。
「そんなことは自分でやれ」 ローマは、1人で闇の中へ消えていった。
「はっ、あっはっはっはっはっ!」 「ジンさん、どうされました?」
「実に、実に正論だ」 ジンもまたそう呟くと、何時の間にやら消えていた。
「やったじゃないか。会心の勝利ってやつだ。とうとうやりやがったな」
駆け寄る桜庭。しかし翔はそれほど喜んでいない様子にみえた。
「ん? どうした? うかない顔しやがって」 「全然駄目だ」 「ああ?」
「全然実感がないんだ。なんていうかその……勝ったっていう……ギリギリ過ぎて……」
翔は不満げにそう言った。それを聞いた遥は、頭をポリポリ掻いた後おもむろに一言。
「楽しかったか?」 「ああ、楽しかった。最高にな。それだけははっきり覚えている」
「だったら今日のところはそれで十分だろ。十分過ぎて釣りがこねえか?」
遥にそう言われた翔は、一回大きく息を吐いて同意した。
そうだな。それでいい。むしろそれだけでいい。今日のところはそれでもう十分だ
【こんな決闘小説は紙面の無駄だ!】
対戦構想自体は初期段階から存在しましたが、どうも勝敗やらなんやらは僕が決めることではなかったようです。数か月ごとに入れ替わる入れ替わる。以前考えたプロットが軽く12個ぐらい御釈迦になりましたが最早どうでもいいこと。兎に角今は現にデュエルをしていた人達に感謝します。さてさて、一端ここを去る前に聞くだけ聞いておきたいことがあります。このシリーズどうだった? おもろかった? たまにはハイエナみたく《貪欲な壺》

↑気軽。ただこちらからすれば初対面扱いになりがちということにだけ注意。

↑過疎。特になんもないんでなんだかんだで遊べるといいな程度の代物です。
![]()
![]()
![]()