�@
�@�����ҒB�́A������k�����ɂ炯�č��������������Ă����B��E��y�̗̈悩��n�ʁE���_�̗̈�Ɏ���܂ŁB�����Ɍ����~�͖ܘ_�̂��ƁA���̗��R���Ȃ��Ȃ�ƂȂ��s������x�ɂ͌��������R�ƂȂ�������B�������s����̂́A�_��Ȃ���̉��Ƃ͌���Ȃ��B
�@"��̌���" �����Ƃ������̌��܂̏��������݂̂��Ӗ��������@�̐��Y�n�B���ɂc�n��S�P�Ԃ���S�U�Ԃ܂ł́A�ʏ� �w�f���G���o�C�p�X�x �ɂ������Ԍ����̍̌@�ʂ͐��ł��P�`�Q�𑈂��Ɖ\����Ă����B�������܂��A�����ɋQ�����D�����̘T�B���ł̒��ł��̂������B�����ɂ͐��`���R�����Ȃ��B����Ƃ���Ί[�Ɖ����������Ղ̌��Ђ̂݁B���������ݏo���Ռ��g�́A�Ŗ�̘T�B�ɂƂ��Ă���Ζ���̂悤�Ȃ��̂������B���E���҂ɂ����錈������S�����A����͓����Ɂ\�\
�u�o�A�o�A�o�A�o�[�C�\���\����@�o�A�o�A�o�A�o�[�C�\���\����@�������I���u�������ā`�V�����l�����荞�ށ`�`�`�n�C�I�@�n�C�I�@�n�C�n�C�n�C�I�@�s�j�ł̋V���t�ō~�Ղc�`�I�v
�@�w�I���x �w�j�Łx �Ƃ������Â��P��ɂ͎����킵���Ȃ��قǗz�C�ɉS��������̂̓o�C�\���E�X�g�}�[�h�B��̌����̏�A�ł���A�����ɂ͍ő����X�����ْ����ȂǂȂ��B����̂͂������]�̂݁B�͔C���ɓ�����ꂽ�����Ղ��� �u�e��ɂ��ĔڂȂ炸�v ��n�ł����̗e�B�s�ǖ������p���݂���B
�u�s�j�ł̖����K�[�����h���t�t���V�������B��ɂӂ��킵�����͋C���łĂ邾��B���́s�n���_ �b���������� �`�����t�ł��炱�̃K�[�����h���t�̗Y���т̑O�ɂ͖��́B���ʔ����B��������I�v
�@�o�C�\���̔��������܂�B�Ŗ���قǂ̗Y���тŁs�t�H�g���E�o�^�t���C�E�A�T�V���t��ł����Ƃ��A���̂܂܃A�b�p�[�J�b�g�Ń_�C���N�g�A�^�b�N�����߂�B
�u����Ń��C�t����������ȁB�^�[���G���h���v
�@�ɂ���o�C�\����������������ƌ�����B �u�Â��ȁv�@�����P�l�̒j�͓����Ȃ��B�ނ́A��̌����ɂ�����V�Q�҂ł͂������B���������ƌ����ɂ����Ă͂ނ���ÎQ�B���m��ʃt�B�[���h�ł����Ă������͌����B�邪�@���ɈÂ��Ƃ��A�ނ́A�[�N�g�E�v���Y�}���b�N�����ޓ��͏�ɐC���ŏƂ炳���B
�u���̃^�[���A�h���[�B�ア�z�ق� �w�h����Ώ��Ă�x �Ɛ����ɋ��ԁB���������̃[�N�g�E�v���Y�}���b�N�͈Ⴄ�B�S�Ă͂��̃f�b�L�Ƃ������̏���͂̒��ɗp�ӂ���Ă���B�ɒB�␌���Ō������f�b�L��g�Ƃł��v�����H�@���͂��̏���͂̒�����I�m�ɑI�яo���B�s�A�N�Z���E���C�g�t���B�s�t�H�g���E�p�C���[�c�t����ꏢ���B���ʔ����B��n�́s�t�H�g���E�X���b�V���[�t�Ɓs�t�H�g���E�o�^�t���C�E�A�T�V���t�����O���邱�ƂōU���͂͂R�O�O�O�܂ŏオ��B�o�g���t�F�C�Y�A�O��������|���Ă����I�v
�@�ꑫ��тʼn��������s�t�H�g���E�p�C���[�c�t�́A�ڂɂ��Ƃ܂�ʑ��ƂŃK�[�����h���t�̎����������B�����̎���͏I���A�C����������绂���V���I�̎n�܂肾�B
�u����Ă����ȁB�����ōŏ㋉��|���Ƃ́B���������F�͉����B�h�[�s���O�����Ƃ���ł��̌��ʂ̓G���h�t�F�C�Y�܂ł����������Ȃ��B�����ɂł����ݒׂ��Ă���v
�u���ȂǎN�����̂��B�s���r���O�f�b�h�̌Ăѐ��t���B��n����s�t�H�g���E���U�[�h�t����ꏢ���B���̂Q�̂ŃI�[�o�[���C�l�b�g���[�N���\�z�B�����A�s�m��.�Q�O �a��y�u�����A���g�t�v
�u�c�т��G�N�V�[�Y�ɉ��������B���傢�Ƃ����R���Ă������B���̃^�[���A�h���[�B�s���C�I�E�t��ʏ폢���B�o�g���t�F�C�Y�A�s�m��.�Q�O �a��y�u�����A���g�t�ɍU�����d�|����v
�@�s���C�I�E�t�B�Q�̌����\�͂����D�G�ȉ����ł���œ_���P�X�O�O�Ɛ\�����Ȃ��B�������[�N�g�E�v���Y�}���b�N�̋a��y�u�����A���g�͂Q�P�O�O�܂ōU���͂������Ă���B���̂܂܂ł͋ʍӁB�������[�N�g�͓������B�d�|����ȏ�͍���Ƃ݂�ׂ��B�s�ːi�t���s���k�t���B��̑S�e�����������Ƃ��ɂ͂����x���B�����ׂ��͍� �\�\ �s���Ȃ�o���A�|�~���[�t�H�[�X�|�t�B�����˕Ԃ����s���C�I�E�t�B
�u����㩎����Ă邶��Ȃ��́B�����`�`�`���A㩂ɂ������̂͂�����̕����I�@���C���t�F�C�Y�Q�A�s�j�ł̖����K�[�����h���t�t�Ɓs���C�I�E�t���Q�[�����珜�O�I�@�s�J�I�X�E�\�[�T���[�t����ꏢ���I�v
�@�E��Ɍ��A����ɈŁA�Q�̖��͂����֏p�̃G�L�X�p�[�g�B�����m�ɂ��Ă͈ٗl�ɒb����ꂽ���̂ƁA�����ɂ��d�����ȍ��߂����̊댯���߂����B�ނ̎�ɂ���č������ꂽ���p�͂��Ƃ����肪�u���[�A�C�Y���̑�^�ł������Ƃ��Ă������̉ʂĂ܂ŏ�������Ƃ����B���ꂱ�����o�C�\���̖{���B���̂Ƃ���s���C�I�E�t�͎̂ċ�ɉ߂��Ȃ������B�s�ːi�t���s���k�t����D�ɂ͂Ȃ��B�������������Ă��邩��ɂ͉�������B�����v�킹�邱�Ƃ��ł���Ώ㓙�A㩂�点�邱�Ƃ��ł���Ζ��X�B�ň��A���̂܂ܑł����ꂽ�Ƃ��Ă���n�ɂ͌�������B
�u���ʔ����B������u�����A���g�I�@�_�[�N�E�o�j�b�V���E�}�W�b�N�I�v
�@�֒f�̍����p���ʂ�߂�����ɂ͕�W����c��Ȃ��B
�u�s�J�I�X�E�\�[�T���[�t�B���ꂱ�����M�l�̃G�[�X�Ƃ����킯���v
�u�����������邺�B�J�[�h���P���Z�b�g���ă^�[���G���h���v
�u��������B����ȘH�T�ɂ��܂��̂悤�Ȍ����҂����Ă���āB���̃^�[���A�h���[�B�X�^���o�C�t�F�C�Y�A�s�^�C���J�v�Z���t����J�[�h���P����D�ɉ�����B�s���̋��t���v
�@�\�[�T���[�̖��p�͕�n���p���狖���� �w���O�x �B�������u�����A���g�̃G�N�V�[�Y�f�ނ͂n�q�t�Ƃ����`�ŕی삳��Ă���B�h�傪�َ����ɔ���ꂽ�Ƃ��Ă��A�f�ނ͕�n�ɗ�����̂݁B
�u��n�́s�t�H�g���E���U�[�h�t�Ɓs�t�H�g���E�p�C���[�c�t�����O�B�����s�c�C���E�t�H�g���E���U�[�h�t�I�v
�u��点�邩��I�@Chain Reverse�I�@Void Trap Hole�I�I�v
�@�o���̗���騂̐����グ��Ƃ��A����͏u���ɔߖւƕς��B�����̗ւ������[���ݍ��ݒf�E�B���Ƃ����̎��p�V�āB�V�����n�����Ȃ��B������O������������Ȃ��B���ɗ�����Ƃ����ߒ��������ȗ����A�C�t�����Ƃ��ɂ͖��E�����B�����s�����̗��Ƃ���/Void Trap Hole�t�ł���B
�u�c�O�������ȁc�c������H�@�����́c�c�܂����c�c�s�^�C���J�v�Z���t���c�c�v
�u�����B��n�̌��������R�̏��O���ꂽ���Ƃɂ����ꏢ�����\�ƂȂ�B���ꂪ���̃G�[�X�s���C�g���C �\�[�T���[�t�I�@�s�c�C���E�t�H�g���E���U�[�h�t�ȂǏ��F�͂��ׂ̘̈I�����ɉ߂��Ȃ��I�v
�@�ꌩ����ƁA�S�g�𔒂Ɛōʂ�ώ��ҁB�������Ă��̐��̂́s�J�I�X�E�\�[�T���[�t�Ɠ����̋֏p�m�B�s�J�I�X�E�\�[�T���[�t���������閂�͂����킹�邱�Ƃŋ֏p��҂ݏo�����̂Ƃ͔��ɁA���́s���C�g���C �\�[�T���[�t�́A���Ɍ����Ïk���邱�ƂŐV���E�ւ̔����J���B
�u���ʔ����B���̒��ɏ�������I�@�V���C���E�o�j�b�V���E�}�W�b�N�I�v
�@���E�����B���퓯�l�̔\�͎ҁB��o���L�����S�����B
�u�J�[�h���P���Z�b�g���ă^�[���G���h�v�@�u�������I�@���o�[�X�J�[�h�I�[�v���v�@�u�ȂɁI�H�v
�u�s�Ŏ����̉���t���B���O���ꂽ�s�J�I�X�E�\�[�T���[�t����ꏢ���B���̃^�[���A�h���[�B�c�O�������ȁB�P�x�o�����s�J�I�X�E�\�[�T���[�t�͓��ꏢ�����\�Ȃ�B���ʔ����c�c�v
�u��点�邩�I�v�@�u������ׁI�v
| Chaos Sorcerer Attack Point�F2300 Defense Point�F2000 Special Ability�FBanish |
VS | Lightray Socerer Attack Point�F2300 Defense Point�F2000 Special Ability�FBanish |
�u�͂��c�c�͂��c�c�͂��c�c���ȁv
�u�M�������A�܂������������W�J�ɂȂ�Ƃ́v
�@�P�^�[����A�݂��̏�ɂ͋ٔ����ꂽ���߂Ɣ��߂̋֏p�m���ɂݍ����Ă���B�s�f�����Y�E�`�F�[���t�B���݂��̃G�[�X�������A�ɂ��������������s���Ȃ��������ɂ���B
�u�ӂ��c�c�N�N�N�c�c�n�[�n�b�n�b�n�b�n�I�@����͌���I�@�Ȃ�Ƃ����^���I�v
�@�˔@�A�[�N�g�E�v���Y�}���b�N�����o���B�v�킸���P��o�C�\���B
�u�ǂ������B�����Ȃ���o���ċ����ł��������B����Ƃ��c�c�v
�u���݂���D���g���s�����G�[�X���ɂݍ����B���̏����͂����ł��a���ɂ��Ȃ����v
�u����H�@���܂�����ł������҂��H�@�������Ă������낤�����B�́B�����邺�v
�u�m���ɁB���������������I�@���ʔ������Ƃ��v�������B���Ƒg�܂Ȃ����o�C�\���v
�u�ȂƁH�v
�u�����ȑO��Team Galaxy�Ƃ��������ŃL���v�e���Ȃǂ߂Ă����̂����A������Ƃ͌�����������d�ō���Ȃ������B���́s���C�g���C �\�[�T���[�t�������G�[�X��ׂ����Ƃ����̂ɂ�����͂�����킩�낤�Ƃ��Ȃ��B����ǂ��납���̃t�F���b�N�X���x������n���B���͂��������������B���ɂ����̌����҂���̌����ɏo�����Ă����̂������Ă݂�ΗJ�����炵�v
�u����ō��x�͉��Ƒg�������āc�c�{�C�Ō����Ă�̂��H�v
�u�{�C���B����Ȗ�X���ɌN�̂悤�Ȍ����҂Əo���Ȃ�Ďv�������Ȃ������B�\�[�T���[�𗝉����A�\�[�T���[���������A�\�[�T���[�ŏ�������N�����炱�����Ƒg�ނɂӂ��킵���v
�u�˔�Șb���������Ȃ��B�������낻��\����ɕԂ�炫�����Ǝv���Ă����B���܂��́s���C�g���C �\�[�T���[�t�Ɖ��́s�J�I�X�E�\�[�T���[�t�����킳��܂��ɖ��G�B���Ă�A���Ă邺�v
�u���ӂɊ��ӂ����o�C�\���B�`�[�����́c�c�������ȁc�c�B�s���C�g���C �\�[�T���[�t�͌����P�O�O���߂Ă���B���ās�J�I�X�E�\�[�T���[�t�͌��ƈł��T�O�F�T�O�B���킹��P�T�O�F�T�O�B�悵�A�킩�������I�@�w���炩�ȏ���Ƃق�̂�����Ƃ̗��BOY's�x ���I�v
�u�����˂��B�����˂��������Ƃ��������ȁv
�u����Ȃ�k�߂� �w
�u������I�@�������I�@�������ɖ��G�̃R���r���a�����������I�v
�@���ɒa���������ɋ���ׂ��c�C���Y�B����͂��Ă����\�\
�u�ӔC�Ƃ��Ă��������v
�@�Ƃ���y�j�̒�������A�����M��������n�ޔN�̊w���ŁA�����ڂ̑O�̏��q���w�����炱�̂悤�ɔ���ꂽ�Ƃ�����A������l�ň���L�����p�X���Ŕ���ꂽ����������낤���B��Ԏ҂����邾�낤�B���������Ȃ��Ƃ����̒j�A�W���b�N�E
�u���܂��A������Ȃ�ł��ŒႾ�B�ƍ߂���ƍ߁B�����Ȃ����惉�E�c�c�v
�@�ӂ�����ȁB������B�����͒P�Ȃ�`�[�����C�g�Łc�c���d�Ƃ���������������݂邪�A�N����荇�����Ƃ͂��Ȃ��B���ʂ̖��͂��̊w�F �\ �{�u�E�}�C�P�� �\ ����k�Ȃ̂��{�C�Ȃ̂��B��k�Ȃ琸�X���Ă�낤�Ɣނ͍l����B��҂��͂P�O�O�{�}�V���B�����������͏������g�b�v�u���z�i�֎~�J�[�h�j�B�ň��̃h���[��z��ł��Ȃ��悤�ł̓J�[�h�Q�[�}�[�ƌ����Ȃ��B
�u�ǂ������f�b�L��g�B�����B�ڍׂɌ����B���ׂ��ɓ`����v
�@�w�F�������m�荇���̂��Ƃ͂ЂƂ܂������A���E�͏��q���w���Ɏ��������킹��B�����畷���ׂ��������ɂȂǂȂ��B�e�Ɋp�����邾�������B�Ȃ������B�Ȃ����̏ꏊ��m���Ă���B
�u�e�C�����畷���܂����B��������Ȃ��ł����B���ꂩ������������̂ɁB�o������߂āA�g���������Đ������̂ɁB�Ȃɂ��Ȃ����Ȃ�āB�Ȃɂ��c�c�Ȃ����Ȃ�āv
�@�Ȃ����̃^�C�~���O�Ŗڂ�w����̂��B�₢�����ɂ��Ȃ��B
�u�I������ȃ��E�B�܁A�B�̒��ɓ����Ă����X�撣�c�c�v
�@����܂ŗF�l���������̉�𑬂₩�Ɏn������B�{���̓e�C���̌����s�c�E�X�e�[�v�����t�ōǂ��ł�肽���Ƃ��낾�������ɂ��Ȃ����̂͂��傤���Ȃ��B�������ׂ��͓��ʂ̖��B�]�v�Ȍ��𗘂��͖̂ܘ_�̂��ƁA���t���炸�Ȃ͎̂�X�^�`�������B�Ȃ����ړI����ȗ�����̂��i���w���ɂ��Ă͖��ɒZ���X�J�[�g�𐧕��ɂ����낭�ł��Ȃ������Z�܂ŒH���ċ��t�ɕ�������������Ƃ��낾�j�B�@�u�����ɐg�������v�@�Ƃ͂����肢���B����𗝉����Ă邨�ꂪ����Ȃ�ړI����ȗ����Ă������Ǝv�������B���̒ʂ肾�B���E�͈�U��������B���������̐��ɂ́A�����Ƒ���̑��ɑ�O�҂�����Ƃ������Ƃ�m��˂Ȃ�Ȃ��B���ꂾ���琼�̐l�Ԃ͐��E�ς������č���B�`�[���f���G�������`�A�ꌩ����Ǝ�����L����_�ł͗ǂ����Ƃ����߂̂悤�Ɏv���邪�A�s���ȑO��Ƃ��āA�l�Ԃ͌ǓƂł��邩�炱������ʂ�ʂ�c�c����������������ł����Ȃ������B���E�͊��ɐ�ւ��Ă���B�\������x�̋�s�̊Ԃɓ��ʂ̕��j���m��B�ނ͂��������j�������B
�u���傤���Ȃ��B������Ƃ����������v
�@���̏ꍇ�A���U��͕K���������Ƃ͌����Ȃ��B����ł����͋������҂��̂��挈�B
�u�����āA�����āA�킽���{�C��������ł���B�{�C�Łc�c�v
�@����ȏ㒝�点��̂͋���B�����炩�璝�邵���Ȃ��B
�u�~�B�B���傤���Ȃ������B���x���������Z�����āc�c�v
�u�c�c�v�@���̖������ō��ɖʓ|�������B
�u���S����B�����璚�x�ɂ��v
�@���q���w���̊炪�ς����Ɩ��邭�Ȃ�B������̋C���m��Ȃ��ŁB�ʓ|���ɔY�܂�������E�͍l����B�������͎̂������B�Z�����͉̂R�ł͂Ȃ����{���ł��Ȃ��B����Ȃ�ɖZ�����̂͂����̂��ƂŁA���̋C�ɂȂ�ǂ��ɂ��ł����B�ԓx�����܂�Ȃ�����A���Z�Ƃ������t�ɊÂ��Ă����������Ɣ����ΕԂ����t���Ȃ��B����������ꏊ�����悻�ň��ł��������Ƃ������A���̃~�B�Ƃ������Q�T�Z���`�ȏ���w��̗��ꂽ���q���w���ɑ���{������܂�Ȃ��B���E�̓����������o���Ɖ�������������ł���P���j��A�����̎����ƈꏏ�Ƀ~�B�Ɏ�n���B
�u���̃����̒ʂ�ɍw�����ɍs���Ă��̃����̒ʂ�ɕ����v
�u�ցH�@���H�v�@�u���̊w�����Ō�������C�Ȃ̂����܂��́v
�@�~�B�����Ă���̂͊w�����B�m���ɓ����ɂ����B
�u���c�c���Ɓc�c����A�����́c�c���ƂŁc�c�v
�u�Ԃ��Ȃ��Ă����B�ނ�K�܂߂Ă������肻�̂܂܂��܂��ɂ���Ă��B���̑��肿���Ƃ�����Ē��Ă��邱�ƁB�悭�킩��Ȃ���������̂������ �w���o����x �ƌ����Έꂩ��\�܂łȂ�Ƃ����Ă����B�����͑厖���B���ɂ��̃X�J�[�g�B����Ō���������������c�c�v
�u���A�������B�p�����c�c�v
�u���ꂵ���v
�u�݂���c�c�����c�c�v
�u�������Ƃ����v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�` �w���� �`
�i�ǂ�����H�@����ȏ�Ƒ��Ȃ����ň��������킯�ɂ������Ȃ��B���R��v�����ׂ����B����A�e�C���͂�������ɍ����������炷�B���[�h�������ɌĂԂ��́A�e�C���̂����ł��������������ɗ��B�p���������̘b�ɏ��Ƃ��v���Ȃ��B�Ȃ�P�l���B���₢��҂Ă�B���d�H�@�~�B�̈ӎv�d���Ό���r�������`�ɂ��Ȃ����w���Ȃǂł���̂��H�@�ƑP�I�Ȏv�z��A���t���邾���̌��ʂɂȂ�͂��Ȃ����낤���B����ނ��낻�̉\���̕��������B�킩���Ă͂������Ƃ����A����͒��X���Ȗ�肾�B��ߐ��̉ƒ닳�t�Ƃ͈Ⴄ�B�ŏI�I�ɂ� "�g��" �Ƃ���܂Ŏ���ɓ����Ă���B�ʓ|�ɂ܂�Ȃ��b�����A�������ƂȂ�����~�X�͋�����Ȃ��j
�@���E�͍l����B
�i���傤���Ȃ��B�ؓ��𗧂Ăĉ\�Ȍ��藝�l�߂ōl���邩�B�h���[�t�F�C�Y�A�f�b�L����P���h���[�B�X�^���o�C�t�F�C�Y�c�c�����A�܂��͂��߂ɏ������肫�B���ȏ��I����������邱�Ƃŋɗ͕Ό���A���t���Ȃ��B�P�P�̒m���ɔ����̂��肻���ȃ~�B�ɂƂ��Ă��L�v�Ȕ��B�����ł������莞�Ԃ�����Ă��烁�C���t�F�C�Y�ɓ���B���C���Ƃ͉����B�N�w�I�ɍl���鎞�Ԃ͂Ȃ��B�琬�Q�[�������Ƃ��āA���̏�ʼn����K�v�Ȃ̂����l����c�c���炢�̌y�����]�܂����B���ꂩ��ǂ����Ă����������B�ړI�B�����Ăǂ�������ړI���ʂ����邩�B�ߒ��B����A�҂Ă�c�c�j
�@�����ƍl����B
�i�����Ȃ��̓I�ɂȂ肷����̂��댯���B���������Ɨh�炬�����ȃ��[�e�B�[���̎v�l�������D�݂ɗU�����Ă��܂��\��������B����Ȃ��Ƃł́A�{�u�̉���Ȗϑz�ƕς��Ȃ��B�U���H�@�������B�厖�Ȃ̂̓o�g���t�F�C�Y�A���ۂ̐ڂ����B���葫��肠�܂�D������������A�ŏ��̂P�l�Ƃ��ĉߏ�Ȋ��҂ƌ��z������ɈႢ�Ȃ��B�O�������J�Ɉ����͓̂��R�����A�ߕی�ɂȂ��Ă��܂��Ắc�c�B������Ƃ��Ă����܂�ˑ������ƍ���B�����c�c����c�c�Ȃ�c�c�c�悵�j
�@�l�����B
�@����͂����ƁA�^��Ŏl�ꔪ�ꂷ��j�F�W���b�N�EA�E���E���h�ƁA����t�̏��q���w�������ҁc�c�̌��K���F�~�B�́A�S���܂� "�ŏ��̈��" �ł���B�������A�����Ƃ����ɈႢ�Ȃ��B
Duel Episode �P�O
Round the clock�`�����J�b�v�����`
�u���̕������₷���ł��ˁB�����ƁA����ς�A�������Ȃ炱�̂��炢�̕��������Ǝv���܂��v
�@�~�B�͐T�d�Ɍ��t��I�т��E����ڂ𗣂��Ȃ��B���ɏo����Ă��܂����B�������������Ƃ�������̂͊o��̏�B�e�C���ɋ�����ꂽ���Ƃ𒉎��Ɏ��B "�Ԃ����Ă���" "������" "�S�O����" "�����������̂�" ��ꐺ�́@�u�ӔC���v�@���S�̑I�����ł���Ƌ�����ꂽ�B�e�C���̊ɂ\���������C�ɂȂ������A��肭�������ȏ�͑吳���B�~�B�̐S�����o�N�o�N�ƁB���E�̒ʂ��Ă����w�͗\�z�ȏ�ɑ傫�������B����Ȑ����Ƃ���ɂ���l�Ԃ��猈���������Ă��炦��B�����l����Ɖ������������Ƃ��}�ɒp���������Ȃ�B�~�B�͎v�����B�����������B��邾������ď��߂ė�Âɂ��̂��l���邱�Ƃ��ł���B��肭�ĕ|���Č����āA�����Ă������Ȃ����̐l�ƂQ�l�ŁH�@�N���ɋ~����v���������Ȃ������~�B�͊������B����Ȏ���ɋy�Ԃ��炢�Ȃ�g�������������}�V���B
�u�m�F���Ă����������A���ꂩ�烊�[�h�B�ɋ����Ă���������Ƃ́H�v
�u�������̊댯���������@����ʂ苳���Ă��炢�܂����v
�@���Ƒe���ۂ������A�Ƃ������Ƃ͕t�������Ȃ��ł������B
�u����Ɋւ��Ă͖Y��Ȃ��悤�K�x�ɕ��K���Ă����悤�ɁB�Ƃ����Ă��A���炭�͂��ꂪ�K�v�ɂȂ�Ȃ����j�ōs���B����̓e�C���Ƃ͈Ⴄ�B�N�����ĈႤ�v
�u�ł���ˁv�@�u�̂��̂����Ă��������܂��ɂ��R�O�����炢�̔�͂���v
�u�����v�@�u���ꂶ�Ⴀ�����ړ����悤�B���̋߂��Ƀf���G���Z���^�[������v
�y�f���G���Z���^�[�z
�@�ʏ̃f���G�Z���B�o�b�e�B���O�Z���^�[��S���t�Z���^�[�ɑ����đ䓪���������K�{�݁B�P�Ȃ�X�g���X��������{�i�I�Ȗ͋[�����܂ŕ��L���j�[�Y�ɍ��킹�����Տ�B���ŗL���Ȃ̂� �w�M�K���e�X�x �w�K�C�f���S�[�x ���X�B���O�̗��K����m�ۂ��Ă���L���I������܊��p���Ă���A����Team Galaxy�̃G�[�X�A�M�����N�V�[�E�t�F���b�N�X�� �w�W�F�C�h�i�C�g�x �̏�A�Ȃ̂͂��܂�ɗL���ł���B
�@�~�B�ɂƂ��Ă͏��߂ē���ꏊ�B�|���B���B
�@���E���炷��Γ���݂̏ꏊ�ł����Ȃ��B
�u�����ɍ���B���������b������v
�u���H�@�������݂����Ȃ���ł����H�v
�u�f�B�X�N�𓊂����ނ��������K����Ȃ��B�{�i�I�ɂ��Ȃ���j�𗧂Ă�K�v������v
�@�{���ɂ�߂�����C�������̂��B���X�B�h���t�g�P�ʂŊ��҂����悤�Ȑl�ԂłȂ����Ƃ��炢�킩���Ă���B����ǂ��납�P�O�ʂł��L�蓾�Ȃ��B�����̊ԈႢ�ŕ��ꍞ�����B�����̐g�̒�����������ԗǂ��m���Ă���B����͂���ł����̌������B���s�͋�����Ȃ��B
�u�ꉞ�A���߂ĕ����Ă������A �w���C�͂���x �����������Ƃł����ȁv
�u�͂��B�킽���A�����Ȃ肽����ł��B�����́A�����̌������݂������āv
�u�킩�����B���ꂶ�Ⴀ�n�߂悤�B���R�����Ղ͎����Ă��Ă��ȁv
�u�ܘ_�ł��I�v�@�Ƃ��o��O��u�Y�ꂩ�����͉̂����̔閧�B
�u���ꂶ�Ⴀ������Ƒ݂��Ă���v
�@�����Ղ̓o�b�O �\ �����̏��^ �\ �̒��ɓ���Ă����B���o���Ă݂ď��߂ă~�X�ɋC�Â��B�����ׂ��������B����Ă�B�������Ă�ɈႢ�Ȃ��B�C�ɂ��Ȃ��ł���邾�낤���B
�u�����I�Ȃ��Ƃ���b���Ă����B���ɒm���Ă邱�Ƃ��������Ă邩������Ȃ����A����ɂ��Ă͖ق��ĕ����Ă���B���̑���A��������������@�艺���鎿������Ă���Ă����v
�@�~�B�͓��S�ŌȂ�p�����B���E������ȍ����Ȃ��Ƃ��C�ɂ�����Ǝv����������p�����B
�@�����ɊW�Ȃ��Ƃ���śZ�т��Ēʂ�قǁA�ڂ̑O�ɂ���R�[�`�͊Â��Ȃ��B
�u�Ƃ���ł��܂��A�f�b�L�͂ǂ�����đg�ށH�v
�u���H�@�����ƁA����́A���́A���\�Ƃ��l���āc�c�v
�@�\�z�O�̎���B�����ł܂��Ă����ɂ͂��܂������Ȃ��B
�u�f�b�L�̓J�[�h�őg�ށB����ȏ�ł�����ȉ��ł��Ȃ��v
�@�������邢�C�������B�g���W���Ȃ��b����Ȃ����ƁB
�u�s�����H�@�������B���ꂶ�Ⴀ����B�J�[�h�Ƃ͂ȂH�v
�u�͂��H�v�@�������Ïʂɏ��グ��B
�u�J�[�h�Ƃ͂Ȃƕ����Ă���v
�u�āA�N�w�I�Șb�͂�����Ɓc�c�v
�u��r�I���p�I�Șb���B�J�[�h�Ƃ̓J�[�h���j�b�g�̗��́B���ꂽ���͂��̃J�[�h���j�b�g�𑩂˂ăf�b�L��g�݁A�g�ݏオ�����f�b�L�������ՂɛƂߍ���œ�����B�����܂ł��Ȃ����J�[�h��TCG�̖{���B�J�[�h��������m��Ȃ��ĂȂɂ������肾�H�@�������B���̃J�[�h���悭����v
�@���E�͌����Ղ�M��ƁA������P���̃J�[�h�����o���Ă݂���B
�u�����܂ł��Ȃ����J�[�h���j�b�g�ɂ͂��ꂼ���������B�����ɂ܂邢�̂����邾��B���ꂪ�f���G���R�A�ŃJ�[�h���j�b�g�̖{���ɂ�����B�J�[�h���j�b�g�͊C�Ő�������邩�狙�t���l���Ă���킯���B�ŋ߂ł͗{�B�����ȁB����̕����̓v���O�����e�L�X�g�B�f�ނƈꏏ�ɉ����Ė��������o�����������Ǝv�������B�����R�A�ł��v���O��������Łs������m �u���C�J�[�t�ɂȂ�����s�����R�m �f�B�t�F���_�[�t�ɂȂ����肷��B��������ꎮ�Ƃ����̂͊ȒP�Ɍ����w�����J�b�v�Ă����x���B�J�b�v�������ՁA���̖˂��f���G���R�A�A���������v���O�����A������������Ƃł�������v
�@��Ȃ��犮���ȉ�����B�����v���ă~�B�̗l�q���f���ƁA���̃~�B�͕s����B
�u�ǂ������H�@�킩��Ȃ��̂��H�@���̐����ł킩��Ȃ��ƂȂ�Ɓc�c�v
�u�����B�킩��܂��B�Ȃ�ƂȂ��B�����ǃJ�b�v�˂́c�c���́c�c�����c�c�v
�@�Ȃ�Ėʓ|�������K�L���B�������Ă�낤���B���̎v���������Ɗ�����B
�u�킩�����킩�����B�v����ɂ���͖��@�̋ʂ��B���Ɗ�]���l�܂��Ă�B�Ƃ����Ă����̂܂܂ł͕��|�����Ďg���Ȃ������p���������Ȃ��B�����ŋʂ̕\�ʂɎ������������ނ킯���B�d�グ�ɂ���@�̏�ɛƂߍ���ŁA�����A��U�肷��Ɩ��@���g����B�����������H�v
�u�͂��I�v�@����ȏ�Ȃ����炢�̏Ί炾�B���E�͓��S������t���B
�u���A�ł��A���͂��������畷���������Ƃ���������ł����c�c�v
�u�Ȃv
�u�����ƁA���̃J�[�h���Ă����f�b�L��������Ă�J�[�h�ƈႤ�悤�ȁc�c�v
�u���������B�������炩�B���R���B����͌����̂Ƃ������Ȃ��J�[�h������ȁv
�u���H�v�@�u����̓}�U�[�J�[�h�B���܂��������Ă�̂̓R�s�[�J�[�h����B�m���Ƃ��v
�@���E�͕ʂ̃J�[�h�����o���B�����A���ꂾ�B�����݂Ă���̂͂�����B
�@�s�a�e�|���k�̃A�u���I���X�t�̗E�p���ł��ł��Ɖf�荞������̕����B
�u�}�U�[�J�[�h�����ꂾ���̋@�\�������ɂ͏���قǔ������A�����蔖���̂��S�O������Ȃ�R�s�[�J�[�h�B����ɖ{�̂ł���}�U�[�J�[�h�̃f���G���e�L�X�g�����āA���������x�����x���h���[����B������������Ղɑ}������Ŋe�������������ƂŔ�������킯�����A���̎��A�����ڂƂ��Ă̓R�s�[�J�[�h���烂���X�^�[�Ȃ�}�W�b�N�Ȃ�g���b�v�Ȃ肪�������Ă���悤�ɂ��݂���B���������ۂɂ̓R�s�[�J�[�h��ʂ��āA�����Ղ̒��S���Ɏ��߂�ꂽ�}�U�[�J�[�h�̃v���O���������������Ă���c�c�Ƃ����̂��{���̂Ƃ��낾�B������}�W�b�N��g���b�v�����鎞���A�����Ղɂ�����Ƃ�����a�������邾��B�ق�Ƃ̐k���n�͂����ȂB���ɕt����f���G���I�[�u������ʂ��������Ă���킯����Ȃ��A�����Ղɑi�������āA�����Ղ�����ʂ����������Ă���ׂ̃c�[���Ȃv
�u�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ����ł����H�@��x��Ԃ��Ă������c�c�v
�u���̘b�����Ă����Đ�����������B�����Ղ��ς����ƊJ���Ē��g��M�������ƂȂ���B���C���ƃT�C�h�ɓ����Ă�J�[�h�����ւ���c�c����ȏ�̂��Ƃ����܂ł�����Ⴕ���Ȃ��v
�u���H�@�Ȃ�ł킩���ł����H�v�@�Ȃɂ��傫�ȁA�[���Ȓn����ł�C������B
�u��Ɏ���֓����Ă����B�R�s�[�����̂́A�}�U�[�J�[�h�����W�߂�̂��ʓ|���������炾�B���̃Q�[���A�֎~�����Ɉ����������Ă���̈ȊO�͂R���܂Őς߂�B�������A��X�R���W�߂�͍̂��̐܂���Ƃ��B�����炨�オ�J�[�h���j�b�g�̉��i��@�Œ������Ă�ƌ����Ă��A�Ȃ��ŋ��������邩��ȁB���A���͐������Ȃ��B��������������邩��A�}�U�[�E�J�[�h�P���ł��R���ς߂�悤�ɂ����BTCG��Technological Card Game�ł����Ƃ��v���C���[�ɗD������������v
�i���������B���ɂ����B����ł��܂������B���肳��Ă�B���m���ɂ��肳��Ă�j
�u���������Ȃ��Ă���ȁB���ʂǂ����Œm�������Ă�������{���̊�{�Ȃ��c�c�v
�u�G���ɂ������������̂��Ƃ������Ă������悤�ȋC�����Ȃ����Ȃ���ł����ǁA���̓s�x�ǂݔ���Ă������Ă������c�c���߂�Ȃ����B���s���ł����B�{���ɂ��߂�Ȃ����I�v
�u���܂����A���̘A�����V�����J�[�h���ǂ��g���Ă邩�l�������Ƃ��Ȃ������̂��H�v
�@�莝���̃J�[�h���g�����Ȃ������Ő���t�������A�Ȃ�Č�����ɂ��Ȃ�Ȃ��B
�i�����A�ǂ������f���G�����C�t�𑗂��Ă����H�@�����̊�{���o���Ă銄�ɂ͖��m������j
�u�e�Ɋp�A�V�����J�[�h����肵���Ƃ��́A�����Ւ����̃}�U�[�X�y�[�X�ɂԂ�����ŁA���C���łS�O�A�G�N�X�g���P�T�ȓ��A�T�C�h�P�T�ɂȂ�悤�R�s�[���Ă����B�����ł������H�v
�u�͂��I�v�@�����킯�ɂ͂����Ȃ��B�������瑦�ޏ�B���Z����Ƃ̖��B
�u�g��Ȃ��J�[�h���j�b�g�̓}�U�[�X�y�[�X����O���B���ʂɏd���Ȃ邾�����B���肷��ƃo�O��B����ŏꏊ�ɂ���Ă͔����������B��{���̊�{���̊�{�ȁv
�@�~�B�͕��������x�ŃR�N�R�N�������B���܂��̓L�c�c�L���Ȃɂ����A���E�͓��S�ŕ����B
�i��̓C�J�T�}�h�~�̋@�\�c�c�́A�ʂɂ������B����Ȃ��Ƃ������Ƒ厖�Ȃ��Ƃ͂���j
�u���������B����������Ƃ��Ȃ��ƂȁB�}�U�[�J�[�h�͑厖�ɂ����B�����ՂƂ����k�Ɏ���Ă���Ƃ͂����A�`������̂͂�������B������������Ȃ����T�O�O�N�ォ������Ȃ����A�e�Ɋp�����e�i���X�͏d�v���B�����ӂ�Ɖ��邱�Ƃ��H�ɂ���v
�u��ꂿ�Ⴄ��ł����v
�u���Ă��F�X�ۏ���������Ⴀ����A����͂���ŐF�X����Ă���ɑ�R�����������B��������邾���Ȃ�܂��������A�ň��A�x���i���J�[�h����Ȃ��ă{�[���y���ɂȂ�v
�u�����e�i���X���Ăǂ�����c�c�v�@�u�����Ȃ�p�����ɗ��߁B100���������v
�i���̐l�c�c���j�@�u�ǂ������H�v�@�u�����B�Ȃ�ł�����܂���I�v
�u�J�[�h���j�b�g������Ƃǂ����̒ʔ̂Ŕ��������Â̎א_�悤�ɂȂ�B���������Ƃ���œ˂������Ă邾���ʼn����o���Ȃ��Ȃ�؋�̖V���v
�u�؋�c�c�v�@�u�ő��ɂȂ����Ƃ����������ɂȂ�Ɛ�������v
�u����Ȃ��Ƃ��c�c�v�@�u�Ȃ��Ƃ͌�����Ȃ��̂�TCG���v
�u���ꂶ�Ⴀ���x�͌����Ղ̉ʂ��������ɂ��Đ������悤�BSDT�ɂ��Ă͌�ɂ���Ƃ��āA�܂��͈�ԑ厖�ȋ@�\�A�J�[�h���j�b�g�̌��ʔ����ɂ��ĂȂ��c�c�ǂ��������̂��v
�i�J�b�v�˂�NG�B���@�̏�Ȃ���킯�Ȃ����c�c�悵�B����ł������j
�@���E�͉����烉�C�^�[�Ɖ��������o���ė���ɕ�����B�r�W���A���I�ɂ͂���Ȃ肾�B
�u�������J�[�h���j�b�g���B�����ă��C�^�[�������ՁB���̎w�̓������X���[�C���O�B�悭�݂Ă����B�J�[�h���j�b�g�̔����ɂȂ������Ղ��K�v�Ȃ̂��������킩��v
�@���E�͐e�w�����J�`�b�Ƃ��낷�B����ڂ��Ɖ����ĉ����ɂ���B
�u����������v�͂����������Ƃ��B���̉� "�`���������Ռ��g" �B�A���A�����Ղ̓��C�^�[�قNjC�y�ȓ����Ȃ��B�g�������ɂ���Ē��̓�Փx���ς��B�ʓ|�ł�����A��햡�ł�����c�c�v
�@���܂� �u�����������̂��v �Ǝv���Ă������Ƃ����߂Đ��������Ɩڂ����������Ƌ��ɁA����Ȃ��Ƃ������ƒm��Ȃ����������̖��m���p���������B�����A���E�̓��E�Ŕ��Ȃ��Ă����B
�i���܂����B���w���̑O�ʼn������o���̂͂悭�Ȃ��ȁB������C��t���悤�j
�u�m���Ă̒ʂ�A��ʓI�Ȍ���l�̐g�̂ɂ͑�Ȃ菬�Ȃ� "�C" ������Ă��āA��������߂Č����Ղ𓊂���B�����������Ɍ����� "�C" �̈����ɒ������l�ԂقǏ�������肢�Ƃ����b�ɂȂ�A����͑��ɂ����Đ������c�c���A�����Ɍ����ՂƂ����g�̓I�v�f������ł���B�J�[�h�������āA���� "�C" �����߂ă����X�^�[��������������Ȃ炻���ɐg�̂̋����͂��܂�W�Ȃ����A���ۂ͂�������Ȃ��B�����Ղ𓊂���K�v������B��ň����Ē��ڏ�������̂͂܂����������A���ł͂���Ɋւ���K�������B���� �w�����Ղ𓊂���x �Ƃ����ߒ������ɂȂ�v
�u��肭�������Ȃ��Ď��s�c�c�v�@�u�����������Ƃ��v�@�i�悩�����B�O���ĂȂ��āj
�u�����X�^�[�̔n�͂�������Ƒ����Ղ��d���Ȃ�B�l�Ԃ̐g�̂𗬂��f���G���I�[���c�c������ "�C" �Ƃ������̂��A���������Ă��������ꂽ���ɂ��Ă͏ȗ������Ă��炤�B�����Ղ�}��Ɍ����C���J�[�h�ɑ��荞�ݓ����A��������悤�₭���Ղɓ���킯�����c�c������O�̎��_�Ŋ��ɔ������炢�͔������Ă���B���̔������炢�������Ă���Ă̂��ʓ|���v
�@����Ղ�ՂB���������ɂ킩��Ȃ��Ƃ�������A����Ȃ��Ƃ��킩��Ȃ��̂��Ɠ{���邾�낤���B�{����Ȃ炢���B�S�̒��ŗ���������ė₽���ڂŌ���ꂽ��ǂ����悤�B�킩���Ă�ӂ�����ׂ����낤���B����A�ʖڂ��B����Ȃ��Ƃ͂����Ⴂ���Ȃ��B�����v�����B
�u�Ӗ����c�c�킩��܂���B���߂�Ȃ����v
�u�������ȁB����ł����B�����Ղ̒��Ƀ����X�^�[�������Ă�ƍl����B�ł����Ă������̂قnj����Ղ��d���Ȃ�B�Ⴆ�A���̑O��肠�����n���_�Ȃ͏d���J�[�h�̌��{���B������݂邩��ɏd��������H�@���ۏd���B������`�[���A�[�X�o�E���h�̃��M�����[�͋g�����������Ȃ��v
�u�g���c�c�v
�u����������͌������g���[�j���O��ς�ł�͂����B�g�b�v������ȁv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\ �n���� �\�\
�u���@�����}�W�J�����e�C���I�@���������@�̐K���ōi�E�����Ⴄ���v
�u�����P���h�v�@�u�Ȃ����U�[����y�v�@�u���J�c�N�ȁv�@�u���J�c�L�܂��ˁv
�u���Z�̃N�I���e�B�������͕̂ʂɂ����B������肻��������Ȃ��������́v
�u���������^�C�v�Ƃ͗F�B�ɂȂ肽���Ȃ��ł��ˁB���l���Ă�킩��Ⴕ�Ȃ��v
�u����͂���Ƃ��Ă��B�����̃N�I���e�B���ٗl�ɍ����̂����J�c�N�Ȃ���v
�u�����悤�̂Ȃ��Ղ��������܂��B�ǂ��ł��������ǂ悭�����Ȃ���ς�܂��ˁv
�u���܂������ă��[�������i�[�ő��荞�݂��Ȃ���ςĂ邾��v�@�u��Փx�Ⴄ������v
�u����Ȃ���f�ʂł݂�邩���Ăv�@�u����ɂ��Ă͂܂����������ł��v
�u�ɂ��Ă������l���r�߂Ă��ȁB����r�߂Ă��ȁv
�u�r�߂Ă܂��ˊm���ɁB������A���̒��������̔���������r�߂Ă�^�C�v�v
�u�ԈႢ�Ȃ��B�����A���܂��������̑��œ���������S�͂łԂ���������v
�u���R�ł���c�c���Ă���B������CG�₽��Â��Ă�ȁB�ق�ƃC���b�Ƃ��܂��ˁv
�u�����͈�̉��_���ȂH�@�ǂ��Ɍ������Ă�H�@�P���h�A�����Ă�H�v
�u�Ă܂���`�Ȃ��B�тł��H���ɍs���܂��H�@�����X�o������ł���ŋ߁v
�u�����A�������悤�B���ꌩ�I�������f�B�X�N�Ńt���X�r�[������ď���������遂�ȁv
�u����y������ł������܂����v
�u�����₪���āc�c�����I�@�������I�v
�u���o�C���āB�Ȃɂ���Ă���Ă�̂���B�K�E�Z��ׂ��v
�u�悤�₭�P���ڂ��I��������v
�u�Ȃ�ł���Q���g�Ȃ�B���A�~�c������U�����痈�܂����ˁv
�u�Z���������������疳�����덡���́v
�u�~�c��������Ȃ��B���������͂����Ȃ�̂��v
�u�������Ⴄ�����B�����������ƌ������Ⴄ���������̌�y�́v
�u�����܂���B�Ԃ����Ⴏ���������Ȃ��ł��原�̐���̌�p�҂ƌ����v
�u�o�[�J�B�����������ƌ����Ă邩��A���܂��͑��̎�肩�猙�����v
�u�������Ă��Ȃ��ł���B������ӎ����Ⴂ����B�Ă���y���\���Ⴂ������v
�u���������A���𗦂���C�T���Ȃ��āA�ǂ����ă~�c������̌���p�����v
�u����͂���A����͂�����Ă������c�c���A�o�䂳�烁�[�����Ă܂���v
�u�Ȃ�Ŗ��܂��̂Ƃ���Ƀ��[�������B���̎o�M�������́v
�u �w�Q�N���œ����̖ʓ|�L������A��Ƀ|�e�`�����Ă��āx �������ł��v
�u�R�O�f���[���Ŕ����Ă�ʉَq�ł����B�����ċA�낤�v
�u��y����ςł���˂��v
�u�܂��������B���̕��o�M�B����ł܂��S�ʂɂ��邩�猙�ɂȂ�c�c�������v
�@���̈�A�̂��Ƃ�̊ԁA�ނ�͓��R�̂悤�Ƀg���[�j���O���s���Ă���B
�@�ő��Ȃ̗̈�ł���A���ꂪ�`�[���A�[�X�o�E���h�̃��M�����[�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\ �f���G���Z���^�[ �\�\
�u������͑����z���悤�ɂ�邩��ȁB����Ɍ��킹��Ό����ɂ�����邪�A�g���[�j���O�����̒��ɑg�ݍ��߂�̂�����͂���Ŏ��͂��v
�u���ꂶ�Ⴀ�킽���͂ǂ�����v�@�u�b����v�@�u����ȕ��ɁI�H�@����ȕ��c�c�v
�u���x��肾�B���܂��̑̊i�ł͒b�����Ƃ���ł���Ă邪�A������Ƃ���܂ł͒b���Ă����đ��͂Ȃ��B����ɁA�����Ղ̖\���͗͂����ʼn��������ނ킯����Ȃ��B�C�ŗ}����B������͂ŗ}�����Ȃ�����Ƃ����Ăǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��킯����Ȃ��B�v�͊��ꂾ�v
�u����v�@�u����Ɍ��킹��A�͂œ����邱�Ƃɗ��肷����z�͐L�єY�ނ�v
�u�ق�Ƃł����I�v�@�u�L�єY�܂Ȃ��z�����邯�ǂȁA���ʂɁv�@�u���c�c�v
�u�����Ղɂ��Ă͂��̂��炢�ɂ��āB�c��R���Ԃ��炢���B�悵�A���͎��Z���v
�u�����`�v�@�ς��ς��ς��B
�@���E�͌����ՂɁs�a�e�|���k�̃A�u���I���X�t���Z�b�g����Ɠ������ݗp�̃f���G�����[���̕����������B��ɕt���Ă���X�C�b�`��M��Ɛ��їp�̃��^���f�r���E�g�[�N�����Q�̌����B
�u�t�H�[���͍��܂Œʂ�T�C�h�X���[�Ŗ��Ȃ��B�I�[�o�[��A���_�[�A�ʂĂ͔�яオ���ē�����z�����邪�Y��Ă����B���ȏ��I�Șb������ƁA�ڐ��͏�������]�[���A���̏ꍇ�͂W�Ԃɍ��킹��c�c�����������������������ȁB�m�[�g�ɏ������炿����Ƒ҂��Ă�v
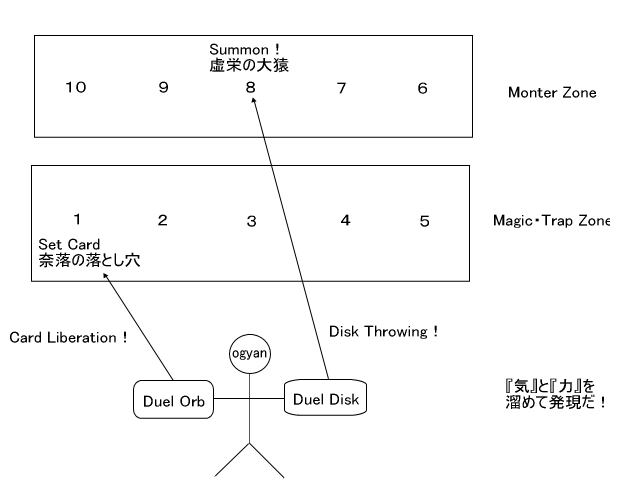
�u�����X�^�[�͓��Պp�x�̖�肩��W�ԂɗD�悵�ē������₷���B�Z�b�g�X�y���͂ǂ��ɒu���Ă������̂ɂȂ邩�炠�܂�W�Ȃ��B�s�������t�̑Ă�A�P�Ԃɒu���̂��|�s�����[���v
�u�킩��₷���ł��˂�����B�Ƃ���ł��� �w�������x ���ĒN�Ȃ�ł��H�v
�u�m���B���ȏ��ɂ悭�g���Ƃ��X�e�B�[�u�Ƃ��ڂ��Ă邾��B���������Ƃ��ɏ������O�̒�ԂƂ��đ�̂���g���Ă��邻�����B����Ȃ��Ƃ��厖�Ȃ͓̂��ՁA�b��i�߂邼�v
�@�������B�������̂��ƂȂǂǂ��ł������B�~�B�͋C��������꒼���B
�u���ۂ͓�����Ƃ��������A�C���������o�����炢�̊��o�ł�������肭�s���₷���B��ɗ��܂镂�͂��������炻��𗘗p����B�F����Ԃɕ����ԃS�~����ʼn����悤�Ȃ��́B�����X�^�[�]�[���ɍs���Ώ���Ɏ~�܂邩���̓x�N�g���ƃp���[�̖�肾�B���������Ă邩�킩�邩�H�v
�u�킩��܂���v�@�i�X�ƕԎ��������Ȃ�B
�u�킩�����B���x���͔͉��Z����邩�珶�̎g������r�̎g�������悭�݂Ă����B���x���Ă��t���ĉ��x�����H���Ă���A����ɂ���̌������Ƃ��킩���Ă���B�������v
�@���E��OZONE���N���B�����u�����̎���v����������B�~�B�ɂƂ��Ă���͖��@�g���̐��E�B���E�͌y�����r���グ�ē��݂��ނƂق�̏����g�̂܂��V�t�g�E�F�C�g�A���Ձi�f�B�X�N�E�X���[�C���O�j���s���B���̎��~�B�͊m���Ɍ����B�����[�X�̏u�ԁA�͂��ɍ��������Ă���̂��B�E�����𒆐S�ɂ��āA��]���̂悤�ɐg�̂��������Ղɗ͂�������悤�ɂ���B�~�B�̏ꍇ�A���ꉻ�͂ł��Ȃ��������̂̂Ȃ�Ƃ������ƈႤ������c�������B���̃t�H�[���͔������B����ꂽ�����Ղ͂W�Ԃ̃����X�^�[�]�[���ɖ������ՁB�A�h�o���X���������B�s�a�e�|���k�̃A�u���I���X�t�c�c
�u�Ƃ܂�����ȋ�Ɂc�c�ǂ������H�v
�u�A�u���I���X�c�c����ȊȒP�Ɂc�c�v
�u�����͂a�e�V���[�Y�̂P�̂��B�s���������t���֎~�ɂȂ�܂ł͒����Ŗ҈Ђ�U������A���̈�́B�����@���^�̂a�e�V���[�Y�͊T���ē��Ղ�����ƌ����Ă��邪�A�����͂��̒��ł��ݑ����ݑ��A�����@��̏��Ȃ��̊��ɏ������₷���Ƃ����ς�̉\�B�ŏ㋉�����y�������Ă��\��������v
�u�킽���͌��\��J������ł����ǁB����ς�˔\�Ȃ���ł����c�c�v
�u�ŏ��͒N�����Ă���Ȃ��̂��B���]�Ԃ̂悤�Ȃ��̂��Ǝv�������B����A�����ՕԂ����炨�܂����K���ɓ����Ă݂�B���ʂȕ������Ȃ����Ƃ��납��n�߂悤�B�������オ��v
�u�����c�c�悵�A�����܂��v�@�u�܂��P�A�ْ����������B�͂��v�@�u�������܂����I�v�@�u�c�c�v
�i���ʂ͕��ʂ̎��ʂɏo����悤�d�グ������B�������ݎ��̂͏\������Ă���݂���������A���䗬���������邾���ł�����Ȃ�̌��ʂ������߂�j
�u���́A�ǂ��ł��傤�v
�u�_�O�v
�u�����v
�i�Ă̒�A���t�ł͂��܂�ʂ��Ȃ��ȁB���t��I�Ԃ̂ɂ���J����j
�u������I�v
�u���̒��x�ň�X��ԁA�����̎p�������ߒ����v
�u�����v
�i�������̂��Ǝ��葫��蓮���������邩�H�@�������A�N���Ɍ�����Ƃȁc�c�j
�u������~�B�Ɏ��葫���F�X�������������̂Ɂv
�@������s��̂̓e�C���B�z�߂�̂̓��[�h�̖�ځB
�u���������Ȃ����߂ɂ����ł��ꂪ�K����͂�ł�킯���v
�u����H�@���������Ă�����ĐM�p�Ȃ������肷��́H�v
�u����Ƃł��v���Ă�̂��B�����̑����N�����Ă����āv
�u����`��ƁA�َq�ܑ������̎ӗ�͒u���Ă���������v�����āv
�u�������B�_���͂킩���ĂB�A�[�X�o�E���h�̊�������A�����ʂ�� �w�����x �v
�u�ꂽ���v
�@����o���e�C���B�����Ƃ��A���[�h�����m�������̂͂���ΊT�_�̒i�K�ł���A�ڍׂɊւ��Ă̓��E���畷�������Ƃ��唼���߂Ă���A���A����𐳒��Ɍ����̂��r�߂��邾�����Ǝv�����B
�u���ۂɂ�������Ƃ̓˔�ɖڂ��҂�A�V�`�[���̂������{�ԑO�Ɍ��ɂ߂�̂͌����Ĉ������Ƃ���Ȃ��B�_�@�[���B�b�g�����|�������тɖƂ��Ă����͖ڂ��҂��Ă��B���������[���B�{���ɏ����Ȃ��Ⴂ���Ȃ���������ɍT���ĂB����Ƃ��͏����ɂ����Ă��炤���v
�u�P�T�ԑO�̂�������X���炢�ɂ͏��C���������ǂˁB�v�����ȏゾ������z���g�B����ɂ��Ă������̑叫�͊킪���������˂��B�ܑ��Z�D�A�Ƃ�킯�x���N���ɐ��ݓn�c�c�v
�@���[�h�̓e�C���̓���@���B�����Œ@���B
�u�ɂ��ɂ��B�ɂ����āv�@
�u���邹���Ԃ�������B���K�����K�v
�u�����v
�u�c�c����ł��܂��̈ӌ��͂ǂ��ȂH�v
�u�ǂ����āH�v
�u�A�[�X�o�E���h���U�����邽�߂̃q���g����v
�u��������ˁB����Ȃ�O�ɂ��������Ƃ���v
�u���������H�@�A�[�X�o�E���h�U���@�Ȃ�āv
�u�`�[���͂̒�グ���K�v�B�悤���킩�����v
�u�c�c���܂��ɉ��������҂������ꂪ�n���������B������O���낻��Ȃ���v
�u�^�ʖڂɌ����Ă���ǂȂ��B�������������A�~�c������Ȃ��ǂ����v
�u�ǂ����낭�Ȃ��Ƃ���Ȃ���v
�u���H�@��`�܂��c�c�������ȁB�������ˁB������Z���������̘b�͒u���Ƃ����v
�u���H�@�ɐl�����ۏo���̂��܂�������Z��������Ă���B���������{�邼�v
�u�����{���Ă邶���B�܁A�ǂ݂̂�����������Ƃ͗��܂Ȃ���B��邱�Ƃ�������v
�u�����̊Ŕ̓h���������ēD�h���ăS�~���ɒ@�����ނ悤�Ȑ^�������͂���Ȃ�v
�u���v���v�B�l�Ԏ��ʂƂ��͂P�l������v�@�i�s�����B����Ȃ��s�����c�c�j
�u�v����ɁA�X�y�b�N���������Ď����ł����ė]���悤�ȃJ�[�h���R����ɂ���ƁA�����ՂƂ̔g�����킹���ꎩ�̂���肭�����Ȃ��Ȃ�B���܂��������m��Ǝv�����A�G�N�X�g���f�b�L���g���o���Ƃ������Ɏ�������B����͐ς߂����Ƃ������̂ł��Ȃ��B�����̃L���p�V�e�B�Ƒ��k���Ȃ��Ƃȁv
�u�Ȃ�c�c�قǁc�c�v�@�~�B�̓��͊��Ƀp���N���O���B
�u�悵�B�����͂���ł����܂����B���K���Ă����悤�Ɂv
�u���肪�Ƃ��c�c�������c�c�܂��c�c���c�c���āv
�u���܂��A�g�т̖����ʘb���Ƃ����炮�炢�c���Ă�v
�u�͂��H�@�S�R�g��Ȃ�����ہX�c���ČJ��z���Ă܂��v
�u�D�s�����B����ʼnƂɋA���Ă�������Ȃ��B�ق�v
�@���E�͈���̖{���~�B�ɓn���B�~�c���E�A�}�M���� �w��b���疞���I�@��������x �����ƕ]��������A�@�u���₢�₱���b�ɂ��Ă͋l�߂�������B���S�҂ȂƂ������Ăv�@�Ƃ����������B�`�[���A�[�X�o�E���h�̃����o�[�H�� �w������
�u�ǂ߁v�@�u�ǂނ�ł����v�@�u���v���B�킩��Ȃ���������킸�d�b���Ă����B���Ԃ��������͎���ɓ�����B �w����Ȃ��ƕ����Ă����̂��낤���x �Ƃ��Y�ޕK�v�͂Ȃ��B�ŏ��͂����������̂��B�������Ă����B���̑���H���Ă�Ƃ��ƐQ�Ă�Ƃ��ȊO�͓ǂݑ�����B�Œ�ł��P�O�����B���e������Ō����郌�x���ɂȂ�܂ł͑��̂��̂��ς�ȁA�ǂނȁB���S����B�k�Ŗ\�����N���悤����Ŋv�����N���悤�����܂��ɂ͊W�Ȃ��B�l�Ԃ̈ꐶ�͈�T���T���̒��ɖ��S�ł��ǂ��ɂ��Ȃ�悤�ɂł��Ă���B���S���Ċ����ɓM��Ă����v
�u���́A���́A�g�C���̎��́c�c�v�@�u���C�\�����ȁB����ɍ\����ɂ͋C������v
�@�悭�킩��Ȃ��㉟�����~�B�͋A���B���E�͖�������1�l�����Ă����B
�i�Œ���̂��Ƃ����A���Ƃ͐��̑��l�҂Ɋ�b��C����B�ŏ�����{��n���� �w�ǂ߁x �ł͕s����������̂����R�B���������Ă� �w�ǂ߁x �ł��s�����낤�B�Ȃ�Ώ��������Ă����āA���̌�̃t�H���[�̐��𐮂��Ă��� �w�ǂ߁x �ƌ��������B�������j
�@�����B���̌��t���g���̂͂��܂�ɑ��������ƌ������Ƃ����E�͂����ɒm��B��\�\
�u���́A�P�R�łɂ��ĂȂ�ł����ǁA���悻�S�ʓI�ɉ��������Ă�̂������ł��܂���v
�u��̓I�ɂǂ����킩��Ȃ��H�v�@�u�����A�ł�����A��s�ڂ���ŏI�s�܂Ŗ��ՂȂ��v
�u���܂�����ł����w�����B�ǂ߂邾��B�Œ�ł��Ƃ肠�����R�s�ڂ܂ł͓ǂ߂邾��v
�u���E���h���E���h����B�킽���̌����ՁA�F�X����Ă���l�W�������āc�c�v
�u�c�c���܂��A�����Ɛ������ǂ��H�v�@�u���H�@�����Ɓc�c�ǂ��ɂ����ł��������v
�u�킩�����B���܂��̌����Ղ̗��ɏ����Ă���ԍ���������B�b�͂��ꂩ�炾�v
�@���E�̐������Ԃ����߂̂悤�ɍ���Ă����B���̍��A "��̌���" �ł́\�\
�u���A���܂������͈�̉��҂��I�v
�u���B�́A���炩�ȏ���Ƃق�̂�����Ƃ̗������������ƈł̉��j���v
�u���̎����𐧔e����\����̂̐V�������W�F���h�B�l�Ă�� �w���[����BOY's�x ���I�v
�@�w
�@���[�Ƃ͐������n���ƈ������n���̂��Ƃ��w���B�����Ȃ�� "��" �� "��" �B�����Ĕ���Ƃ͉�ꉻ���ꂽ��ɔ������ƁA�����������͂ւ̔��t�B�s���C�g���C �\�[�T���[�t�Ɓs�J�I�X�E�\�[�T���[�t�������ׂƂ����A�V���ȂQ�l�̉�T�ɂ�鉺���オ�n�܂�B�ނ�͎�n�߂ɁA��̌����ҒB��Ђ��[����D�Ղ�ɂ����Ă����B�E�H�[�~���O�A�b�v�����˂��|����B�I���̑��_����ɁA�ނ�̐����͎~�܂�Ȃ��B
�u�K���_�[�̐����̔@�����炩���c�c���͂��v�@
�u�ЂƂ܂݂̗��▭�ȃX�p�C�X�Ɂc�c���͂��v
�@�G���͈�ڂ��ɂ����B�ނ炪�삯�������Ղɂ́s�N���{�[�t��C����c��Ȃ��B�Q�l�͌��t�ɏo���Ȃ��قǂ̏[�����ɕ�܂�Ă����B���̐S�ɓ܂�Ȃ��A�ꗱ�̖�S����Ăč炩���B���ꂪ�I
�@�w
�u�s�j�ł̖����K�[�����h���t�t�Ń_�C���N�g�A�^�b�N���I�v
�u���͂��B���B �w���b��y���x ���s�ꋎ��Ȃ�āc�c�v
�u�s�c�C���E�t�H�g���E���U�[�h�t�Ń_�C���N�g�A�^�b�N�I�v
�u���̒��܂ŃG�^�[�i���E�T���V���C���c�c���͂��v
�u����łP�X�A���B���B�͖��G���B���G�̃^�b�O���v
�u���G���B�����������B�O�̃`�[���ł͖��킦�Ȃ��������̏[���c�c��H�v
�@�Ȃ���p����P�l�̒j���]���荞��ł���B���r�ɂ͌����Ղ�t���Ă����B������Ȃ������҂��B��������̑��B�ԈႢ�Ȃ��B "��̌���" �ɕ������̂��B�������N�ɁH�@����������ɂ킩��B�����P�l�̌����҂��s�҂��m�F���ɔ��ł������炾�B�s�҂������낷���̕��e�͉��قƌ��������Ȃ������B���ʂȂ�܂��L�蓾�Ȃ��B�����������͖�B������ΑS�Ă��܂���ʂ鐢�E�B
�u�ǂ���炨�܂���������|�����킯���B���Ȃ��Ƃ��G���ł͂Ȃ��������ȁv
�u���D�͕ϑԂ��݂Ă邪��̉����͕s��ł����B�ǂ�����H�@���_�v
�u�f�G�ȉ��y�ɕς���Ă����Ɗ��҂����B�����\���邪�����v
�@�Q�l�̓��C�Ɍĉ������̂� "����" �͖����Ō����Ղ��\����B
�u���ꂻ��B�����͖�̐��E�ȂB�ⓚ���p�ł������Ă��炤���v
�@�[�N�g�ƃo�C�\�����܂������Ղ��\�����B���̌��ɏƂ炳��āB�Q�l�͗E��B
�u�����荇���ď�����I�@�s�J�I�X�E�\�[�T���[�t�A�l�I�E�_�[�N�E�o�j�b�V���E�}�W�b�N�I�v
�u�Ƃ炵�Ă݂��悤�Ŗ�̓���I�@�s���C�g���C �\�[�T���[�t�A�V���C���E�o�j�b�V���E�}�W�b�N�U�v
�@�������ނ�͒m��Ȃ������B���[�ɓ|��Ă�j���A��̂ǂ�قlj�����������Ă��������B
�u���͂������������������I�v
�u�A���Ȃ��������������I�v
�@�[�N�g�ƃo�C�\���B�Q�l���킹�ĂP�T�O�L���͂���B�������P�T�O�L�����낤�ƂQ�O�O�L�����낤�Ɛl�Ԕ�ԂƂ��͔�ԂƂ������Ƃ��J�[�h�Q�[���͋����Ă����B�ʏ�A�J�[�h�Q�[�����ɐ���������Ƃ����Ă��A���ۂ͒n��]����ɉ߂��Ȃ��B���������̏ꍇ�͈Ⴄ�B�����Ă���̂��B�����B�ɂ܂��������҂ɂ��ɂ܂��������͂���P�������Ȏ�����˂��t����B�������Ⴄ�Ƃ����������B
�\�\��Z�y�O�w�瑒�z
�u�����c�c���c�c���c�c�v
�u��X���[����BOY's���c�c�v
�@���[����BOY's����R�������̌����҂́A�Ăі�̈łɏ����Ă����B���̑������낤���Čq���A�ނ�͊���̎�����m�����B�P�A�����B�͖��G����Ȃ��B�P�A�l�͎v��������ׂ�B
�@"��̐��E" �Ƃ́A���X�ɂ��Ă����������̂ł���B
�y����Ȍ��������͎��ʂ̖��ʂ��I�z
�Ǘ��L���������܂����B�V�W�J�ł��B�u���߂Ă�Technological Card Game�v�҂��ǂ������y���݂��������B
�������ł��n�j�^���N�̓~�͊����̂ŃR�����g�~���Ȃ��ƔN���z���܂���B�R�����g���������B
���O�b�@���\���@�����b